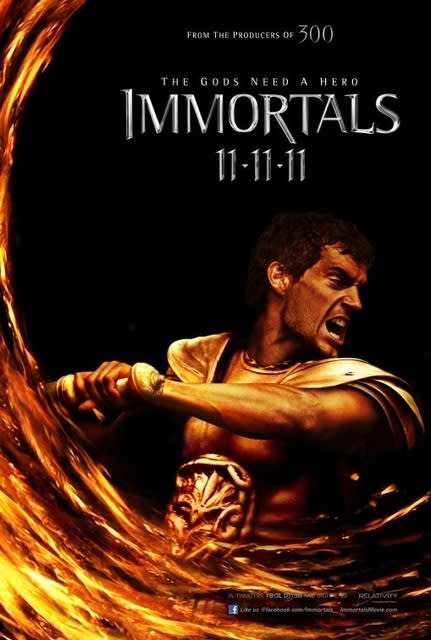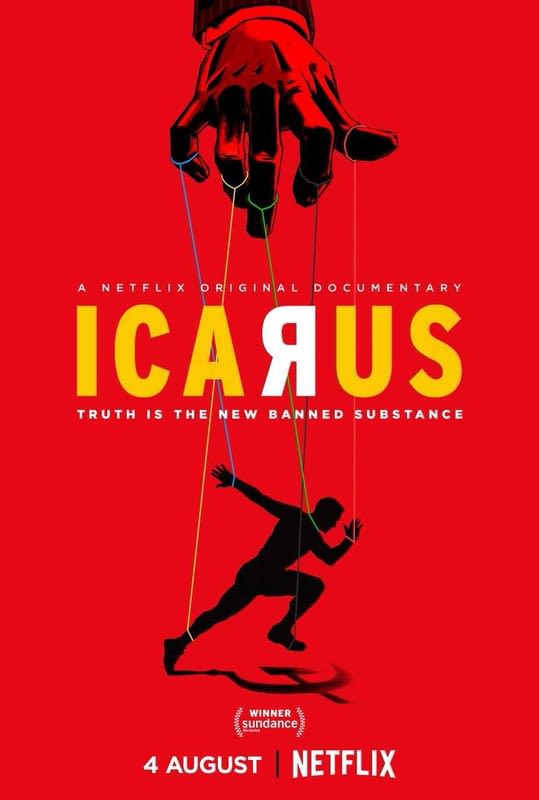映画は2004年の第1作目直後から始まるのに少しも古びていない。思い返せば『ダークナイト』よりも、『ウォッチメン』(実写映画版)よりも『シビル・ウォー』よりも早く己のアイデンティティに悩むスーパーヒーロー像を描いていた『Mr.インクレディブル』はマーヴェル・シネマティック・ユニバース全盛の2018年にいったい何を描くのか?ブラッド・バード監督の天才に裏打ちされた第2弾は普遍的な揺るぎのなさだ。
ヒーロー活動を再開して“職場復帰”するのは妻イラスティ・ガールで、夫Mr.インクレディブルは主夫として家事や子育てに挑むが、赤ん坊ジャックジャックは文字通り“怪物”で寝かしつけるのもままならない。前作で過去の栄光が忘れられずに悶々としたお父さんが今度は子育てであっという間に自信喪失してしまうのが可笑しい。Me Tooよりもずっと以前にバードはジェンダーの役割化を取っ払っていた。
華々しくアクションを繰り広げるイラスティ・ガールがカッコいい。パワーしかスキルのないMr.インクレディブルに比べ、技の数も多彩で見栄えがいいのだ。『ミッション・インポッシブル/ゴーストプロトコル』『トゥモローランド』と実写作品を経てバードのアクション演出はキレを増しており、いつになく華やかなビッグバンドサウンドを奏でるマイケル・ジアッキーノのスコアも手伝って空席となった007監督の座をお願いしたいくらいである(007最新作の監督は現在、『トゥルー・ディテクティブ』のケイリー・ジョージ・フクナガが就任している)。
大義なき戦いだったイラク戦争はアメリカに巨大な力の意味を内省させ、0年代のヒーロー映画群は何度も自らの持つ力について惑い、苦しんだ。そして弱きを助け、手を取り合うマーヴェルが主流となった今、バードは本作でスーパーヒーローを家族として再定義する。父の頑張りに気付いた娘の「パパはスーパーよ」という言葉の温かさ。スーパーヒーローは誰だってなれる。そしてあなたも誰かのスーパーワンであり、オンリーワンなのだ。
ヒーロー活動を再開して“職場復帰”するのは妻イラスティ・ガールで、夫Mr.インクレディブルは主夫として家事や子育てに挑むが、赤ん坊ジャックジャックは文字通り“怪物”で寝かしつけるのもままならない。前作で過去の栄光が忘れられずに悶々としたお父さんが今度は子育てであっという間に自信喪失してしまうのが可笑しい。Me Tooよりもずっと以前にバードはジェンダーの役割化を取っ払っていた。
華々しくアクションを繰り広げるイラスティ・ガールがカッコいい。パワーしかスキルのないMr.インクレディブルに比べ、技の数も多彩で見栄えがいいのだ。『ミッション・インポッシブル/ゴーストプロトコル』『トゥモローランド』と実写作品を経てバードのアクション演出はキレを増しており、いつになく華やかなビッグバンドサウンドを奏でるマイケル・ジアッキーノのスコアも手伝って空席となった007監督の座をお願いしたいくらいである(007最新作の監督は現在、『トゥルー・ディテクティブ』のケイリー・ジョージ・フクナガが就任している)。
大義なき戦いだったイラク戦争はアメリカに巨大な力の意味を内省させ、0年代のヒーロー映画群は何度も自らの持つ力について惑い、苦しんだ。そして弱きを助け、手を取り合うマーヴェルが主流となった今、バードは本作でスーパーヒーローを家族として再定義する。父の頑張りに気付いた娘の「パパはスーパーよ」という言葉の温かさ。スーパーヒーローは誰だってなれる。そしてあなたも誰かのスーパーワンであり、オンリーワンなのだ。
『インクレディブル・ファミリー』18・米
監督 ブラッド・バード
出演 クレイグ・T・ネルソン、ホリー・ハンター、サミュエル・L・ジャクソン、ボブ・オデンカーク、キャサリン・キーナー