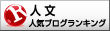http://www.vocto.biz/
一人暮らしの男性が一人で食事する時、寂しさを紛らわす為、カーディガンを羽織ったり、キャミソール姿だったりする女性が食事している姿が映像に映し出されます。収録時間は3時間40分!!!!!
不思議。









一人暮らしの男性が一人で食事する時、寂しさを紛らわす為、カーディガンを羽織ったり、キャミソール姿だったりする女性が食事している姿が映像に映し出されます。収録時間は3時間40分!!!!!
不思議。









 | さゆり〈上〉文藝春秋このアイテムの詳細を見る |
「さゆり」という小説を僕は「単行本」で読んでいる。多分、ちょうどその頃、仕事関係の人に、京都・上七軒の「置き屋」に連れて行って貰ったからだろう。
「置き屋」という呼び方が正しいのか、分からないが、その時は僕を入れて3人で行った。
しかも、お座敷に上がるのではなく、舞妓さんが休憩するコタツのある部屋で酒を飲んでいたのである。一緒に行ったディレクターが舞妓さんのドキュメンタリーを撮り、そこの「置き屋」のおかみさん(という名称でいいのか)と親しくなり、普通は入れないその部屋に案内して貰った。
好奇心旺盛な僕は、おかみさんにいろんなことを訊いた。
まず、「置き屋」の営業時間。これは24時間だそうだ。つまり、こういう事。
京都駅に着いた常連さんが一本電話を「馴染みの置き屋」に入れると、そこからはすべて「置き屋」が仕切ってくれる。お金を用意する必要は無い。まず、タクシーで京都駅に迎えに来てくれ、どこのホテルに電話しても「満室状態」でも、「置き屋」から言えば、ちゃんと希望通りの部屋が取れる。
お客はお座敷で酒を飲んで遊び、「空席の無かった帰りの飛行機のチケット」も「置き屋」が手配してくれる。もちろん、大阪空港までの車の手配も。
そして、夏と年末、年二回だけ、「置き屋」から「筆でしたためた巻紙の請求書」が届くのである。
つまり、「置き屋」は「男性にとって、遊ぶ為のコンビニ」と考えれば分かりやすい。だから、24時間営業なのである。
この「さゆり」という本、アメリカ人が書いたのだが、日本人が書いたと嘘をついても分からない位、ちゃんと調べて書いてある。その本を原作として、製作スピルバーグ、監督はあの「シカゴ」のロブ・マーシャルである。
とは言っても僕をいちばん惹きつけるのは主演の「チャン・ツィイー」。
「初恋のきた道」からずっと、彼女の大ファン。それにしても、あの少女が本当に綺麗なアジアを代表する女優になったものだ。
映画を見るのが楽しみ楽しみ。
http://www.movies.co.jp/sayuri/







小林信彦さんが「週刊文春」で女優の「中北千枝子さん」の逝去について書かれていた。要旨は、「中北千枝子さん」の存在を知らない記者が書いているのではないか・・・普通なら、写真くらい載るべき人物ではないかと言う事である。僕も同感だ。
同じ号の「文春」の堀井憲一郎さんのコラムのテーマも「訃報の記事の大きさ」だった。
堀井さんが購読しているのが「日刊スポーツ」なので、今年一年、誰がどの大きさで載ったかのランク表が掲載されていた。
一位は、プロレスラーの橋本真也さん享年40歳。
三位が本田美奈子さん。
六位がローマほうローマ法王 ヨハネ・パウロ二世。
映画「砂の器」の野村芳太郎監督が十一位。
「サウンド・オブ・ミュージック」や「ウェストサイド物語」の名監督ロバート・ワイズが十八位。
大相撲で「ヒョーショージョー」とたどたどしい日本語で「表彰状」を渡していたデービッド・ジョーンズさんも亡くなられていた事を知った。
「スポーツ紙」なので、どうしても「スポーツ界」「芸能界」の人の扱いが大きくなるのは仕方無いと思う。しかし、ここ10年くらいの全国紙「死亡記事欄」の扱いが何かしっくり来ない気がする。
つまり、「過去に活躍した人」が記者に忘れられているか、「その偉業」を認識されていないか、どちらかだと僕は思う。






同じ号の「文春」の堀井憲一郎さんのコラムのテーマも「訃報の記事の大きさ」だった。
堀井さんが購読しているのが「日刊スポーツ」なので、今年一年、誰がどの大きさで載ったかのランク表が掲載されていた。
一位は、プロレスラーの橋本真也さん享年40歳。
三位が本田美奈子さん。
六位がローマほうローマ法王 ヨハネ・パウロ二世。
映画「砂の器」の野村芳太郎監督が十一位。
「サウンド・オブ・ミュージック」や「ウェストサイド物語」の名監督ロバート・ワイズが十八位。
大相撲で「ヒョーショージョー」とたどたどしい日本語で「表彰状」を渡していたデービッド・ジョーンズさんも亡くなられていた事を知った。
「スポーツ紙」なので、どうしても「スポーツ界」「芸能界」の人の扱いが大きくなるのは仕方無いと思う。しかし、ここ10年くらいの全国紙「死亡記事欄」の扱いが何かしっくり来ない気がする。
つまり、「過去に活躍した人」が記者に忘れられているか、「その偉業」を認識されていないか、どちらかだと僕は思う。






妻は「通販」が好きである。そして、「防災グッズ」が中でも今、いちばん「ハマッテイル」(言い方は失礼かな)のである。
僕も会社の机の中に、非常用の懐中電灯を「防災グッズ」として、妻から渡され、置いてある。
http://www.mfi.or.jp/kumiya/gddispre.html
僕は、そういうところに関してだけは、「神経質」ではないので、「地震」が起こった時は、その時考えようというはなはだ「楽観的な人」である。仕事のことだと「悲観的」になるのだが・・・
僕は、自分自身が「LUCKY」な人間だと思っているところがある。人生を振り返ってみると、岐路に立った時、失敗したかなと思っても、ちゃんとリカバーできているし、家族や会社関係、友人には恵まれている方だと思う。
六本木の「キャバクラ」の女の子で、「手相」に多少詳しい子が僕の手相を見て、不思議な稀に見る手相なので、ちゃんと手相を見てもらった方がいいよと言われた。
まだ、それから、手相見に自分の手相を見て貰っていない。
「火事場の馬鹿力」と言うが、結構ハプニングには強い。だから、「地震」が来ないと思っているし、もし万一来たら・・・それなりにサバイバルできると思い込んでいる。こんな奴に限って、妻の用意している「防災グッズ」に助けられるのかもしれないが・・・





僕も会社の机の中に、非常用の懐中電灯を「防災グッズ」として、妻から渡され、置いてある。
http://www.mfi.or.jp/kumiya/gddispre.html
僕は、そういうところに関してだけは、「神経質」ではないので、「地震」が起こった時は、その時考えようというはなはだ「楽観的な人」である。仕事のことだと「悲観的」になるのだが・・・
僕は、自分自身が「LUCKY」な人間だと思っているところがある。人生を振り返ってみると、岐路に立った時、失敗したかなと思っても、ちゃんとリカバーできているし、家族や会社関係、友人には恵まれている方だと思う。
六本木の「キャバクラ」の女の子で、「手相」に多少詳しい子が僕の手相を見て、不思議な稀に見る手相なので、ちゃんと手相を見てもらった方がいいよと言われた。
まだ、それから、手相見に自分の手相を見て貰っていない。
「火事場の馬鹿力」と言うが、結構ハプニングには強い。だから、「地震」が来ないと思っているし、もし万一来たら・・・それなりにサバイバルできると思い込んでいる。こんな奴に限って、妻の用意している「防災グッズ」に助けられるのかもしれないが・・・






 | スーパーサイズ・ミーレントラックジャパンこのアイテムの詳細を見る |
以下、Amazonの解説より・・・
1か月間、すべての食事をマクドナルドのメニューで摂っていたら、体はどうなるのか? そんな疑問に、スパーロック監督が自らの肉体をもって体験し、答える超異色のドキュメンタリー。食べ始めて数日後の嫌悪感を通り過ぎると、やがて麻薬のように欲する“マック食”の中毒性が明らかになる。最初は実験を軽視していた医師や、スパーロックのベジタリアンの恋人も、彼のあまりの体調の悪化に、マック食を止めさせようとするのだが…。
体重はもちろん、肝臓などの数値の変化は衝撃的だが、同じ食事を繰り返すことが精神にも悪影響を与えるという点が興味深い。さらに驚くのは、監督のマック食と並行して迫っていくアメリカ人の食生活。何かと「スーパーサイズ」を選ぶように仕組まれたファーストフードに対する警鐘だけでなく、各地の学校における給食の実態には、けっこうびっくり。マクドナルドや給食を出す会社など、企業への批判をこうして映画にして、ヒットさせてしまうというのもアメリカの特殊な社会性だろう。偏食の恐ろしさを目の当たりにしながらも、本作を観ていると、何となくマック食がおいしそうに見えてくる…。それも不思議。
と説明されていた。どちらにしても、ダイエット中の僕は「マクド」に行く機会は無いのだが・・・アトピーゆえ、食べ物に気をつけている今、この映画に強い興味を持った。








「お酒の注ぎ方」について、再認識させられた。
ある飲み屋での事。マスターが検査で入院していて、僕が行った時は時々、マスターが「腰痛」で来られない時、臨時に来ている女性。それと、一年位前、週に二日、アルバイトで店にいた若い女性。
僕が行った時は、カウンターの中に一人、そしてカウンターの外にアルバイトしていた子が久しぶりに来たとの事で飲んでいた。店内には三人。これでも、客は多い方である。そこに、何軒飲んできたのか、かなり酔っ払ったオジサン達が4人で入ってきた。狭い店ではあるので、アルバイトをしていた子がカウンターの中に入り、女性二人でお客さんの相手をしていた。それだけでも「気持ちの良い子」である。
そして、オジサン達にお酒を注ぐ時、ちゃんと両手で瓶を持ち、「上から失礼します」と声をかけ、グラスを満たしていく。オジサン達は酔っ払っているので彼女の言葉にも気付いていなかっただろうが、僕は昔、会社の先輩に教わった事を思い出した。
僕が「制作部」の宴会で、片手でビールを注ごうとしたら、先輩はこう言った。
「ビールは両手で瓶を持って、優しく注ぐのが礼儀だよ」と。
彼女は誰に教えられたのだろう。それとも、大人になるまでの親のしつけがちゃんとできていて、自然にそういう言動ができるのだろうか。
うちの会社によく来る代理店の若い男の子がいる。まあ、「アポなし」は許せるが、「ウィース」という挨拶は無いだろう。僕のデスクの傍で喋る時も、片手を低いロッカーに置いている。髪形は、人それぞれの自由だと思うが、やはり、「はなわ」の様に先を何本か尖らしているというのは「社会人」としてどうだろう。現場のクリエーターなら、許せると思うけれど、TPOというか、「その場の空気感」が読めていないし、「礼」を失っしていると僕は思う。
やはり、「言動」は大切にすべきものだ。







ある飲み屋での事。マスターが検査で入院していて、僕が行った時は時々、マスターが「腰痛」で来られない時、臨時に来ている女性。それと、一年位前、週に二日、アルバイトで店にいた若い女性。
僕が行った時は、カウンターの中に一人、そしてカウンターの外にアルバイトしていた子が久しぶりに来たとの事で飲んでいた。店内には三人。これでも、客は多い方である。そこに、何軒飲んできたのか、かなり酔っ払ったオジサン達が4人で入ってきた。狭い店ではあるので、アルバイトをしていた子がカウンターの中に入り、女性二人でお客さんの相手をしていた。それだけでも「気持ちの良い子」である。
そして、オジサン達にお酒を注ぐ時、ちゃんと両手で瓶を持ち、「上から失礼します」と声をかけ、グラスを満たしていく。オジサン達は酔っ払っているので彼女の言葉にも気付いていなかっただろうが、僕は昔、会社の先輩に教わった事を思い出した。
僕が「制作部」の宴会で、片手でビールを注ごうとしたら、先輩はこう言った。
「ビールは両手で瓶を持って、優しく注ぐのが礼儀だよ」と。
彼女は誰に教えられたのだろう。それとも、大人になるまでの親のしつけがちゃんとできていて、自然にそういう言動ができるのだろうか。
うちの会社によく来る代理店の若い男の子がいる。まあ、「アポなし」は許せるが、「ウィース」という挨拶は無いだろう。僕のデスクの傍で喋る時も、片手を低いロッカーに置いている。髪形は、人それぞれの自由だと思うが、やはり、「はなわ」の様に先を何本か尖らしているというのは「社会人」としてどうだろう。現場のクリエーターなら、許せると思うけれど、TPOというか、「その場の空気感」が読めていないし、「礼」を失っしていると僕は思う。
やはり、「言動」は大切にすべきものだ。







 | ハチドリのひとしずく いま、私にできること光文社このアイテムの詳細を見る |
http://www.tiara.cc/~germany/index_biotope.html
この本を読んでいて印象的だった言葉。日本人が今日できる事がふたつある。30分でいい、裸足になって大地に足をつけること。そして都会の雑踏で足を緩め、空を眺めること。









 | 御祝 Congratulation―国重友美英漢字(ええかんじ)作品集TOKIMEKIパブリッシングこのアイテムの詳細を見る |
大阪の読売テレビ制作『なるトモ』で紹介されていて、興味を持ったので読みました。一つの「字」が「漢字」でも「英単語」でも同じ意味になる様に、「字」を書くという「自由さ」或いは「困難をくぐり抜けて到達した作品」・・・に、「好きな事」を本当に自分がやっているか、問い質したい思いに駆られました。








 | 生きるスターツ出版このアイテムの詳細を見る |
読みました。その文章は、「当たり障りの無い様に」「全く具体的ではなく」、子供達に新しいチャレンジをさせたいという提案でした。それは、校長の意思は感じられず、単に、「教育委員会の方針」に従って、配布した事が感じられる文章で、この本にある「情熱」は全然見当たりませんでした。最悪!!!!!