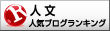今週は、仕事満載の一週間だった。テレビ局はこの時期、年末年始の「特番」の収録ラッシュになる。ロケに行ったり、スタジオに行ったり、落ち着くヒマが無い。
なおかつ、各テレビ誌等の「出版物」に番組の写真や内容の原稿を早く入れなくてはならない。年末進行で、雑誌等の媒体の締め切りがいつもより、はるかに早くなってくるからだ。
そのテレビ局側と媒体側の努力で、例えば、「ザテレビジョン」などの「年末年始合併号」が12月半ばには発行される。
その間を縫って、この一年お世話になった系列局の方々や制作会社の方々、代理店の方々、新聞社や雑誌社の方々との「忘年会」が入ってくる。
テレビが誕生したのは、昭和28年2月のNHK、8月の日本テレビ。それ以来、一日も休むことなく、50年以上も電波を出し続けているのだから、気の遠くなる話である。
あるスポーツ紙の記者に訊くと、正月休みは元旦と2日だけだそうだ。大晦日は「紅白歌合戦」が終わり、打ち上げがあって、午前2時頃仕事が終了。その「紅白」の視聴率が出るのが1月2日なので、実質的な休みは1日。
お笑い関係の、ある事務所も、年末年始は「テレビの特番」「劇場の興行」等、稼ぎ時なので、社員は休めないと聞いた事がある。
昨日、妻が手書きして、僕が文章を書いた年賀状を初めて「Kinko‘s」に出したら、校正からレイアウト、印刷まで、ほぼ二日で素晴らしい年賀状が出来上がってきた。やはり、「プロの仕事」だと思った。この年賀状作りに対する妻の情熱は、結婚してから一度も変わる事なく、10月くらいから、「来年の年賀状はどうしよう」と頭を悩ませている。
今年は満足だろう。
子供達がアトピーなので、おせち料理も「アレルギー専門のおせち」を注文しなければならない。「師走」という雰囲気に徐々になってきた。
今日、帰省の切符を買いに行ったら、結構指定席が埋まっていた。今日行っておいてよかったと思う。
この忙しさも、仕事納めが近づくにつれて納まってくる。仕事納めの日には、総務部が大会議室に午後、料理とお酒を用意して、年末の挨拶にお越しになる、この一年お世話になった人達との歓談になる。夕方頃には、スポンサーや代理店を廻ってきて、各所でお酒を飲み、かなり出来上がった若い営業部員が「廊下ででんぐり返り」をやっていたり、奇声を発していたりする。一年間の仕事から開放された喜びもあって、僕には微笑ましい風景に見える。
年末年始は、やる事があまり無い。
僕の場合は「大学の同窓会」が卒業から23年欠かす事無く、大晦日にあり、6~8人くらいで鍋を突き、「水掛不動尊」に御参りし、「夫婦善哉」で「ぜんざい」を食べ、午後9時半くらいに、僕の実家に戻り、「紅白」を見て、「日テレ」の「ナインティンナインの火祭り」を見て、午前1時に就寝。
元旦は、大概朝寝坊し、みんなが揃って、おせちや雑煮を食べる用意が出来たところで起こされる。
そして、2日に妻の実家に行く途中に、墓参りをして、「父」に孫の成長ぶりを見せ、午後、朝霧(神戸市垂水区)の実家に到着。妻の妹さん一家も来て、飲んで食べて・・・やがて眠くなり、先に寝てしまうのがいつものパターン。
2日には、「卒業した高校で、バスケット部の同窓会を兼ねた試合」があるのだが、ここ数年行っていない。
妻の実家からは「明石大橋」がきれいに見え、寒くて空気も澄んでいるのか、気分がいい。
大体、子供達は妻のお父さんに遊んで貰い、僕は携帯用パソコンでブログを書いている。
今、思い出したのだが、入社して数年経った時、「ゆく年くる年」という民放全局で同じ番組を同時に放送するという、今ではもう無い番組の中継で、滋賀の三井寺に行った。中継時間は40秒。各地のお寺の鐘の音を中継で繋いで、曲を演奏するという企画だった。
日本武道館で、加山雄三が指揮をし、まず最初の音が「三井寺の鐘」だった。とっても、寒い大晦日で、先輩と日本酒を飲みながら、年越しまで準備をし、待機。リハーサルでは加山さんは、指揮棒を振り上げてすぐ降ろしてくれたので、鐘を撞くタイミングはバッチリだった。つまり、「鐘を撞くには、一旦、吊り下げられた棒を引っ張り上げて、振り下ろす時間」が必要で、リハーサルでは加山さんが指揮棒をあげた瞬間に、フロアーディレクターから、お坊さんに「キュー(合図)」が出され、お坊さんは棒を引っ張り上げ、振り下ろす。それと同じタイミングで加山さんの指揮棒も振り下ろされたので、「中継」が来た時、ちょうどいい感じで音が出た。
さて、本番、加山さんが指揮棒を振り上げたので、フロアー・ディレクターはお坊さんに「キュー」を出す。
ところが、本番では加山さんは指揮棒を振り上げ、ちょっと、話をしたのである。「中継」が来た時には当然「鐘は鳴った後」。画面にもう一度、鐘を撞く様に指示を出すフロアー・ディレクターの姿が見え、もう一度、鐘は鳴らされ、曲の演奏が始まったのであるが、40秒の為に、夕方から何時間も待機し、「本番では予想外のどうする事もできない失敗」。
撤収して、大阪の本社に帰るスタッフ達は沈み込んでいた。
僕は何をしていたかというと、中継車に乗って、東京のキー局から来る連絡を伝えたり、本番までの時間の秒読みをしたりしていた。
余談だが、生放送でも収録でも、ディレクターの隣には、タイム・キーパーという仕事をする人が座る。この人が「秒読み」をするのである。今は、専門の会社やフリーの、女性がやることがほとんどだが、僕らが入社した頃は、僕らもやらされた。スタジオの生放送番組では、4台あるVTRのスタートから、以前、このブログでも書いた「APS」と呼ばれる、ネットしている局にCMに入る信号を送るボタンも押していた。もちろん、残り時間の秒読みは基本的な仕事。細かいところでいえば、「ステレオ放送」のスーパーを入れるキューと外すキューも出すのである。僕はこの複雑な仕事が好きだった。
「秒読み」にはルールがあって、「10・ ・8・7・6・5・4・3・2」と数える。つまり、「9」は読まないのである。理由き簡単。ディレクターの「キュー(合図)」と間違われる事を避ける為なのである。東京では「ココノツ」というタイム・キーパーさんもいるが。「フロアー・ディレクター」は、「2」までしか言わない。「1」を言うと、放送の音声に入ってしまう危険があるから。
脱線しまくった「今日の長いブログ」・・・最近、なかなかブログに書く「テーマ」を見つける時間も無く、思いつくままに、ダラダラと書いてしまった。こんな日もあっていいだろう。ゴメンチャイ!











なおかつ、各テレビ誌等の「出版物」に番組の写真や内容の原稿を早く入れなくてはならない。年末進行で、雑誌等の媒体の締め切りがいつもより、はるかに早くなってくるからだ。
そのテレビ局側と媒体側の努力で、例えば、「ザテレビジョン」などの「年末年始合併号」が12月半ばには発行される。
その間を縫って、この一年お世話になった系列局の方々や制作会社の方々、代理店の方々、新聞社や雑誌社の方々との「忘年会」が入ってくる。
テレビが誕生したのは、昭和28年2月のNHK、8月の日本テレビ。それ以来、一日も休むことなく、50年以上も電波を出し続けているのだから、気の遠くなる話である。
あるスポーツ紙の記者に訊くと、正月休みは元旦と2日だけだそうだ。大晦日は「紅白歌合戦」が終わり、打ち上げがあって、午前2時頃仕事が終了。その「紅白」の視聴率が出るのが1月2日なので、実質的な休みは1日。
お笑い関係の、ある事務所も、年末年始は「テレビの特番」「劇場の興行」等、稼ぎ時なので、社員は休めないと聞いた事がある。
昨日、妻が手書きして、僕が文章を書いた年賀状を初めて「Kinko‘s」に出したら、校正からレイアウト、印刷まで、ほぼ二日で素晴らしい年賀状が出来上がってきた。やはり、「プロの仕事」だと思った。この年賀状作りに対する妻の情熱は、結婚してから一度も変わる事なく、10月くらいから、「来年の年賀状はどうしよう」と頭を悩ませている。
今年は満足だろう。
子供達がアトピーなので、おせち料理も「アレルギー専門のおせち」を注文しなければならない。「師走」という雰囲気に徐々になってきた。
今日、帰省の切符を買いに行ったら、結構指定席が埋まっていた。今日行っておいてよかったと思う。
この忙しさも、仕事納めが近づくにつれて納まってくる。仕事納めの日には、総務部が大会議室に午後、料理とお酒を用意して、年末の挨拶にお越しになる、この一年お世話になった人達との歓談になる。夕方頃には、スポンサーや代理店を廻ってきて、各所でお酒を飲み、かなり出来上がった若い営業部員が「廊下ででんぐり返り」をやっていたり、奇声を発していたりする。一年間の仕事から開放された喜びもあって、僕には微笑ましい風景に見える。
年末年始は、やる事があまり無い。
僕の場合は「大学の同窓会」が卒業から23年欠かす事無く、大晦日にあり、6~8人くらいで鍋を突き、「水掛不動尊」に御参りし、「夫婦善哉」で「ぜんざい」を食べ、午後9時半くらいに、僕の実家に戻り、「紅白」を見て、「日テレ」の「ナインティンナインの火祭り」を見て、午前1時に就寝。
元旦は、大概朝寝坊し、みんなが揃って、おせちや雑煮を食べる用意が出来たところで起こされる。
そして、2日に妻の実家に行く途中に、墓参りをして、「父」に孫の成長ぶりを見せ、午後、朝霧(神戸市垂水区)の実家に到着。妻の妹さん一家も来て、飲んで食べて・・・やがて眠くなり、先に寝てしまうのがいつものパターン。
2日には、「卒業した高校で、バスケット部の同窓会を兼ねた試合」があるのだが、ここ数年行っていない。
妻の実家からは「明石大橋」がきれいに見え、寒くて空気も澄んでいるのか、気分がいい。
大体、子供達は妻のお父さんに遊んで貰い、僕は携帯用パソコンでブログを書いている。
今、思い出したのだが、入社して数年経った時、「ゆく年くる年」という民放全局で同じ番組を同時に放送するという、今ではもう無い番組の中継で、滋賀の三井寺に行った。中継時間は40秒。各地のお寺の鐘の音を中継で繋いで、曲を演奏するという企画だった。
日本武道館で、加山雄三が指揮をし、まず最初の音が「三井寺の鐘」だった。とっても、寒い大晦日で、先輩と日本酒を飲みながら、年越しまで準備をし、待機。リハーサルでは加山さんは、指揮棒を振り上げてすぐ降ろしてくれたので、鐘を撞くタイミングはバッチリだった。つまり、「鐘を撞くには、一旦、吊り下げられた棒を引っ張り上げて、振り下ろす時間」が必要で、リハーサルでは加山さんが指揮棒をあげた瞬間に、フロアーディレクターから、お坊さんに「キュー(合図)」が出され、お坊さんは棒を引っ張り上げ、振り下ろす。それと同じタイミングで加山さんの指揮棒も振り下ろされたので、「中継」が来た時、ちょうどいい感じで音が出た。
さて、本番、加山さんが指揮棒を振り上げたので、フロアー・ディレクターはお坊さんに「キュー」を出す。
ところが、本番では加山さんは指揮棒を振り上げ、ちょっと、話をしたのである。「中継」が来た時には当然「鐘は鳴った後」。画面にもう一度、鐘を撞く様に指示を出すフロアー・ディレクターの姿が見え、もう一度、鐘は鳴らされ、曲の演奏が始まったのであるが、40秒の為に、夕方から何時間も待機し、「本番では予想外のどうする事もできない失敗」。
撤収して、大阪の本社に帰るスタッフ達は沈み込んでいた。
僕は何をしていたかというと、中継車に乗って、東京のキー局から来る連絡を伝えたり、本番までの時間の秒読みをしたりしていた。
余談だが、生放送でも収録でも、ディレクターの隣には、タイム・キーパーという仕事をする人が座る。この人が「秒読み」をするのである。今は、専門の会社やフリーの、女性がやることがほとんどだが、僕らが入社した頃は、僕らもやらされた。スタジオの生放送番組では、4台あるVTRのスタートから、以前、このブログでも書いた「APS」と呼ばれる、ネットしている局にCMに入る信号を送るボタンも押していた。もちろん、残り時間の秒読みは基本的な仕事。細かいところでいえば、「ステレオ放送」のスーパーを入れるキューと外すキューも出すのである。僕はこの複雑な仕事が好きだった。
「秒読み」にはルールがあって、「10・ ・8・7・6・5・4・3・2」と数える。つまり、「9」は読まないのである。理由き簡単。ディレクターの「キュー(合図)」と間違われる事を避ける為なのである。東京では「ココノツ」というタイム・キーパーさんもいるが。「フロアー・ディレクター」は、「2」までしか言わない。「1」を言うと、放送の音声に入ってしまう危険があるから。
脱線しまくった「今日の長いブログ」・・・最近、なかなかブログに書く「テーマ」を見つける時間も無く、思いつくままに、ダラダラと書いてしまった。こんな日もあっていいだろう。ゴメンチャイ!