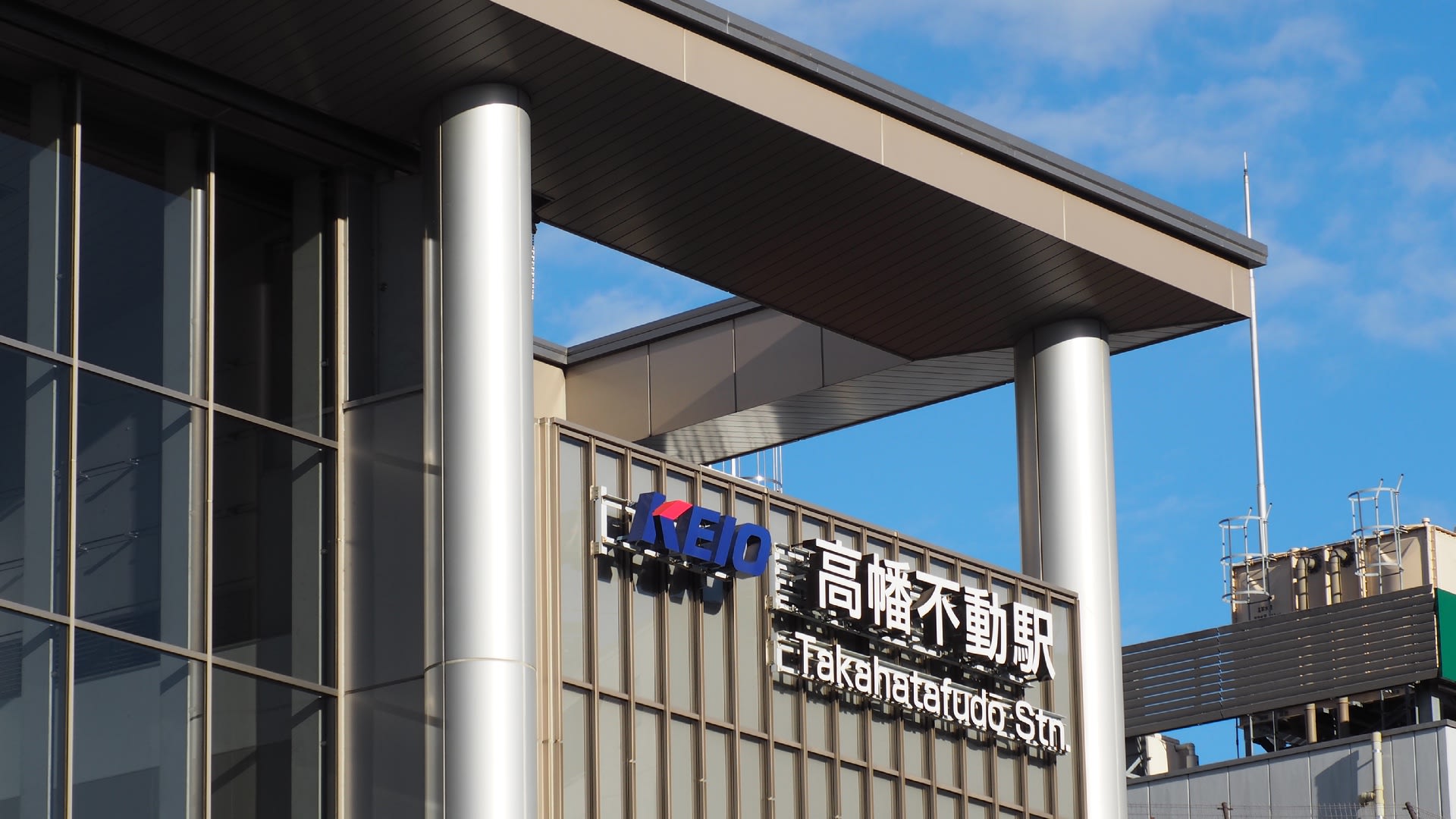JR線を見下ろす4階に部分に池上線の五反田駅がある。
山手線の内側への延伸を狙った構造ではあるが、計画はついぞ実現しなかった。
高架下を目黒川が流れて、桜の頃はさぞかしキレイだろうなと思う。

目黒川を跨いだ1000系の3両編成は、加速をする間もなく大崎広小路駅、その次が戸越銀座駅だ。
1.3kmに400の商店が軒を連ねる戸越銀座商店街、その中ほどで踏切を鳴らして短い電車が絵になる。

大井町線とクロスする旗の台駅、多摩産の木材でリニューアルしたホームは温もりに溢れている。

木造のホーム上屋、上屋と一体化した白いペンキ塗りの木製ベンチ、
一方で昔ながらの旧い駅が多いのも池上線の風景だ。西島三重子の曲の情景が目に浮かぶ。
そんな洗足池駅に現代っ子の7000系が入ってきた。

洗足池に流れこむ川はない。大小の湧水を集めて周囲1.2kmのこの池はある。
辺りには広重の名所江戸百景『千束の池袈裟懸松』にも描かれた美しい景勝地の片鱗が窺える。
自然豊かな環境だから、飛来する冬の水鳥は多いけれど、スワンが浮かんでいるとは思わなかったね。

呑川を渡って雪が谷大塚駅に飛び込んできたのは「青ガエル」リバイバル塗装。
ある年代以上の方には懐かしい色だと思う。

左に大きくカーブして行く本線に並んで、雪が谷検車区が24編成分の電留線を広げている。
こうして見ると、池上線(多摩川線)の顔ぶれは、なかなかどうして華やかだ。

池上線が東海道新幹線を跨ぐ辺りに在るのが御嶽山駅。
「おんたけさん」という駅名には信州人としては反応せざるを得ない。当然に途中下車になる。

案の定というか駅の北側に御嶽神社が鎮座していた。
天保年間、この村にあった小社に木曾御嶽山で修業をした一山行者が来社して以来信者を増やし、
やがて大きな社殿を建立すると、関東一円から御嶽信仰の信者が多く訪れるようになったそうだ。

武蔵野台地と、幾つもの川が削った谷底が入り組んだ地形をアップダウンしながら
7000系3両編成が池上駅に滑り込んでくる。もともと池上線の前身である池上電気鉄道は、
池上本門寺の参詣客輸送を目的に開業したから、この路線の中心駅と云って良い。

仏具屋や花屋、くず餅屋などが並ぶ本門寺通りを抜けると、呑川対岸の崖上に大本山の仁王門が見える。
加藤清正が寄進した九十六段の石段からなる此経難持坂(しきょうなんじざか)を登り切ると池上本門寺。
仁王門をくぐった先の大堂はかなりの大きさだ。日蓮聖人の御尊像(祖師像)を安置する。


右手に目を向けて、徳川秀忠公が建立寄進した五重塔は、関東に現存する最古の五重塔なのだそうだ。
さらに本殿裏、小堀遠州造園の松涛園は、西郷隆盛と勝海舟の江戸城明け渡し会見の舞台でもある。

今宵の一杯はこの門前町でも良かったのだけれど、やはり酒飲みのワンダーランド蒲田に向かいたい。
ということで2駅4分のラストスパート、アンカーの7000系は頭端式ホームの蒲田駅に終着する。

ガード下に立ち飲み屋が並ぶくいだおれ横丁、それに続くバーボンロードを冷やかして歩くと、
昭和な民家風が気になる。仰ぐ看板には「立飲み集会所 日本酒人」だって、入るよね、ここ。


っで今宵はビール抜きにして、秋田の酒で攻めることにする。肴は海のモノと決めた。
“春霞” は大曲に近い美郷町の酒、酒米美郷錦で醸した純米はやわらかい甘みを感じる食中酒。
アテは “紅鮭海苔チーズ ホイル焼き”、これは美味い。海苔とチーズが塩っぱい紅鮭といい感じだ。


秋田だからね。“いぶりがっこ” を箸休めに置いて、ふた皿めの “タコ刺し” は薄切りが瑞々しい。
“純米ど辛” は白神山地の酒、日本酒度+15の超辛口の酵母は「セクスィー山本酵母」だって、遊んでるね。


品書きの文字通り “大きいカキフライ”、カラっと揚がってしっかり旨味があって、レモンを絞って美味しい。
三杯めの “刈穂” は大仙市神宮寺の蔵、山杯純米生原酒番外品って重々しいこの酒は日本酒度+22。
これは効くね。重厚な旨味とハードなキレ、カキフライにかける中濃にも負けない。いい出会いだ。
それこそ短い距離ながら濃厚な池上線の呑み旅は、秋田の旨酒にほろッと酔って終わるのだ。
東急池上線 五反田〜蒲田 10.9km 完乗

池上線 / 西島三重子