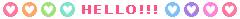
本日は、出来立て取れたて、アツアツの、小説最新話をお届けします。
先日、とあるチャットルームでの妄想にきっかけをもらって、
あっという間にプロットの出来上がったお話です。
ただ、途中、作者の私が、
ドリボ申し込み全滅という奈落に落ちたために、
再起不能になりかけましたが、
心優しき方の恩情に縋る形で、現世に戻ってこれました。
チャットに参加されていた方は、大筋はご存知ですが、
言葉に直していくうちに、
やっぱり、彼の方が暴走していきました。
MなくせにSな彼女と、
Sを装うMな彼。
なので、ラストは少し、変わっています。
どう、変わったかは、読んでからの、お楽しみ。
石川魂のレポに皆様、お忙しいかとは思いますが、
すばる君に愛されたい方は、ご一読を。
お付き合いくださる方は、続きから、どうぞ。
STORY.26 熱帯夜
梅雨明けが報じられたその日。
前日までの大雨で、地上に溜まっていた水滴が、
一気に天空へ昇ってゆくかのように、
街は、蒸し暑さに包まれていて、
それは、夜になって陽が落ちてからも、変わりはなかった。
昼の間に吹いていた風も、ピタリと止んで、
窓を開け放っていても、一向に涼しくはなかった。
「暑~~ィ」
声にしたくなくても、つい叫んでしまう。
「ねえ、エアコン、かけてもいい?」
「あかん。エアコンは、あかん。のどにくる」
「だって、扇風機の風、全っ然、涼しくないもん」
「今週末、また、ライブあんねんから。のど、痛めたら元も子もないやんけ」
彼の仕事は、歌うたい、だ。
だから、なにより、のどの調子を気にする。
ツアー中は、なおさらだ。
「じゃあ、なんか、冷たいもんでも・・・」
小さなキッチンに立って、冷凍庫を開ける。
「あ。なんにもないや」
彼がお酒を飲むための氷で、冷凍庫は、いっぱいで。
「ねえ、アイス、買ってきて?」
「はあ? なんで、オレ?」
「だって、私もう、外に出る格好じゃないもん」
「着替えたらええやん」
「やだもん。汗になるもん」
「あほか。もう汗、かいてるやん」
「ひとりでコンビニ、怖いもん」
「まだ、そんな時間ちゃうで」
「ねえってば」
「氷、食べといたらええやん」
「そんなこというんやったら、もう、今日は、なしね」
「なしって、おい。
ちゃうやんか、話、関係ないやん。
なんで、そうなるん」
「私のお願い、きいてくれないんやったら、
あなたのいうことも、きいてあげへん」
「たかが、アイスやぞ? 話、大きなってるやん」
「だって、また、汗かくもん。暑いから、汗かくこと、したないわ」
「いやいや、そん時は、エアコンかて入れるやろ?
まさか、窓開けたままでは、せぇへんし」
「でもイヤ。暑いまま、したくないもん」
「アイス食べたら、暑なくなんの?
氷では、あかんの?」
「冷たくて、甘いものが、欲しいのっ!」
「ああ、もうっ!! わがままやねんから。
わかった、買ってきたる。
アイスやったら、なんでも、ええんやな?」
「うん」
しばし、のち。
「ほら、買うて来たで」
近くのコンビニまで行ってきた彼が、白い袋を差し出した。
「いつものチョコミントで、良かったんやな?」
「え!?」
「おい、『え!?』て、なんなん」
彼から受け取った袋を覗き込む。
「バニラの気分・・・」
「あんなぁ・・・。大概にせぇ」
「後で食べる」
「なんて?」
「今、チョコミントの気分じゃないもん」
白い袋からアイスを取り出して、冷凍庫に入れる。
そのついでに、
ふと、思い立って、
そばにあったタオルを濡らして、絞る。
「・・・ったく、なんやねん」
いつもの場所に、ストンと座った彼の、
表情が、険しい。
「食べたい、言うから、買いに行ってやったのに」
近くにあった雑誌を手に、ぱらぱらとページをめくる。
横に座ると、
ふいっと、彼が背を向けた。
「怒ったの?」
背中から、彼に聞いてみる。
「怒ってへん、別に」
振り返りもせず、
目を、雑誌に落としたまま。
雑誌が読みたいわけじゃないのは、すぐに分かる。
だって、それ、
女の子用のファッション誌だもん。
怒らせたかな、やっぱし。
私は、彼の背中を見る。
華奢な肩幅。
広くは無い、背中。
外は、もっと蒸し暑かったんだろう。
汗ばんだシャツが、そこに、張り付いている。
手にした濡れタオルを、彼に渡そうとした時、
「暑っつ!!余計な汗、かいたわ」
彼が、いきなりTシャツを脱いだ。
脱いだTシャツで、顔の汗を、ごしごしっとする。
私は、手元のリモコンで、
せめても、扇風機の風を強くしてみた。
頼りない風が、彼の髪を揺らす。
「背中、拭いてあげる」
私は、濡らしたタオルを彼の背にあてた。
「ひゃっ・・・」
一瞬の冷たさが、彼の身体のほてりを、静める。
「ちょっ・・・くすぐったいやん」
汗をふき取った背中に、指で書いた文字。
『ありがと』の、4つまで書いたところで、
身体をくねらせて、彼が振り返る。
「なにしてんねん」
「背中、拭いてる」
「ちゃうやん、今、なんかえらいくすぐったかったで」
「あとひとつ、ね」
「んん?」
振り返った彼の背に、手を伸ばして、
『う』。
書くと同時に、彼の頬に、KISS。
耳元に、囁く。
「欲しかったのは、貴方が私のためにしてくれる気持ち、だから」
私は、そのまま、
彼の首筋に抱きついた。
「試した・・・んか」
「違うわ。ただ、欲しかった、のよ」
彼の瞳が、私を見つめてる。
「欲張り、やな」
「そう? 」
「そんで、ええわ。欲しいもん、諦めてるより、ずっと、ええ」
「そのために振り回されても?」
「オレには、面倒な駆け引きは、出来ん。
動けるときは、動いたるし、アカンと思うたら、そう言うし」
「今は?」
見上げた私に、彼の香りが降りてくる。
汗に混じった、かすかな、煙草の匂い。
耳元に、彼の唇が触れる。
息がかかる。
「オレが出てる間に、寝室のエアコン、かけたやろ?」
くすくす。
小さく笑う私を、彼の手が抱き寄せる。
「窓の外、室外機の音がしてる」
敏感な、耳ね。
「オレを誰やと、思うてるん」
「歌のうまい、小っちゃいおっさん?」
「おまえ、しばくぞ?」
言葉の端で、彼が笑った。
「誰が小っちゃいねん」
そこ?
「大きなるトコ、見せたろか」
なにげ、自信満々なんですけど。
「食べてみる?」
にやり、と、彼が笑った。
「甘いミルク、たっぷり、かけたるわ」
くすくす。
「だったら、冷やさないとね。冷凍庫で」
「よっしゃ。ほんなら、冷凍庫ん中、行こか」
私から離れて起き上がった彼。
「アイスに負けんくらい、ドロドロに溶かしたる」
くすくす。
もうちょっと、イジワル、してみる?
「溶かすだけで食べない気なら、止めといて」
「なん?」
「甘いもん、苦手でしょ?」
「待てや。話が・・・」
「私、アイスより、甘いわよ? 食べ切れる?」
満面の笑みが、彼に広がる。
「極上の甘いもんは、特別や」
濃厚な甘い蜜に誘われた蜂が、羽音をたてて、夜の闇を、狂い飛ぶ。
溶け出した香りが、静寂に流れこみ、
むせかえるほどに、立ちのぼる。
熱帯夜の気温が、また少し、上がった。
FIN.
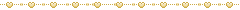
ランキングに参加中です。よろしければ、ご協力を。
関ジャニWEBランキング
にほんブログ村 男性アイドルグループランキング










