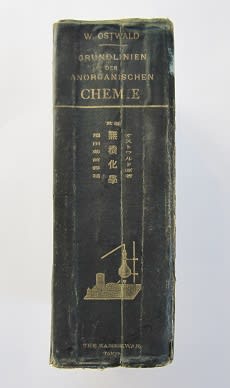佐藤文郷のことが気になっていた。 「宮沢賢治とその周辺」(川原仁左エ門編著)『「農界の特志家」(佐藤文郷)301頁~』に見られたからである。また「新校本宮澤賢治全集 第十六巻(下)補遺・資料篇360頁」にもとりあげられているからでもある。何かで佐藤のことに付いて記した文を読んだ気がしていたのだが古いことなのでその本が思い出せなかった。整理をしていたら見つかったので紹介をしたい。
八戸分場時代の思い出
平川 甚四郎
八戸分場は本場が青森市石江から黒石へ移転にきまったので、南部地方へも分場設置の要望がでた。当時当局としては尻内地区を目標に物色したが敷地と経費の関係で八戸の旧南部城趾、今の八戸小学校の場所に決定した。そのためか土壌は砂利混りやら表土、心土は勿論作土は色々で試験に随分苦労したが反面作物の選定に都合よかった。水田は城趾の南下「長根リンク」の水下であった。
試験地は田畑共余り広くないのに品種の比較試験を主に各種耕種法等に畑作は南部地方特産の大小裸麦、大小豆、粟、稗、蕎麦、菜種、玉蜀黍、馬鈴薯から各種蔬菜花等に至るまで優良品種の種苗の配布と耕種法改善の指導に努めた。それで南部三郡に亘り委託試験地を設け、之が調査指導にも乗り出すので仲々多忙であつた。職員は場長と私の二人で外に常農夫一人に見習生助手として当時長内孫太郎、前田直三郎、松原庸一、大村末吉、三浦儀一、佐藤多一郎等が居られた。事務室、農畜舎は南側に、場長官舎は正門(今の南部会館真向)の右側にあった。私の官舎が無かったので大正五年二月に就任して江渡旅館に下宿していたが、五月に世帯をもつたので常海町の船越香邸(当時群農会長、後に県農会長)の近所の寂しい所に借家して通勤したが、何分試験場の仕事は今時と違って朝は人夫の指導で六時には出勤、晩は晩で作業は日没までやり、その後後始末をして帰ったので帰るのがいつも夜八時過ぎになった。それに日曜として休めないとあつて新妻に一、ニ回逃げられることもあったが佐藤場長の母堂と奥さんに面倒を見て貰った事を今でも時折当時を追懐して笑って居ります。
初代分場長は三戸町出身の盛岡高農卒で三本木畜産学校教諭から就任された、佐藤文郷技手で仲々の勉強家で試験計画から万端に亘り識見は高かった、殊に大正六年から全国的に育種(品種改良)に主力を注ぐことになったが、何分試験地は狭いので従来の試験も地方のために縮小する事も出来ず苦労した。
佐藤場長は仲々の貴公子でお酒は強い方ではなかったが煙草はよく嗜むほうでした。趣味として囲碁、謡曲は熱心でその面で地方民と広く交友を結び信望があつた。当時の本場長は大脇正諄技師で県の勧業課長兼務で月に1,2回分場へも参られた。大脇場長は玉蜀黍が大好物で之を焼いて食べるので場長用として試験地外へ特に作ったものであった。
大正七年八月一日東北6県農事試験場長会議を八戸分場に開くことになつたので何か珍しいものを作る様にとの命令でであった。それで場長と相談して先ず玉蜀黍と蕃茄を出すことを計画し成功したので場長から賞められた記憶がありますが、其の頃東北地方では露地で8月1日までに蕃茄の完熟は出来なかったらしく、全く今昔の感がある。大脇氏は大正8年から寒地稲作栽培の論文で博士号をとられ間もなく秋田県勧業課長兼試験場長に転任された。その時の記念に私は「農者国本」の一葉を揮毫して貰って書斎に掲額崇敬している。大正7年から黒石本場の中村胖場長代理は宮城県技師へ転任になりその後任として丹治七郎技師が参られたが中村氏は一ヶ年位で再度黒石本場へ復帰したので、丹治技師は八戸分場長として参ることになり佐藤分場長は大脇氏の斡旋で岩手県軽米の製麻会社の試験地の技師として分場長を退任された、佐藤氏も当県技手であったのでせめて技師(高等官)に昇格してからの退任であればと心ある者から惜しまれた。
丹治分場長は1年位で米国シャトル大学へ留学のため退任、その後任として北大から佐藤弘毅氏が来任されたが之亦2年位で郷里福島県相馬農学校長に転任のため退任された。佐藤文郷氏は軽米の試験地に一年半位で辞められ岩手県農会技師就任され私も会議等で時々会って八戸分場時代を語ったが、岩手県農会在任4,5年で盛岡市で他界された。丹治七郎氏は米国から帰朝後 宮城県農事試験場長に就任、私も2,3回訪問した事があったが其後九州の熊本の試験場長に転任 水稲挽化栽培で名をなしたが丹治氏亦熊本で他界された。郷里は福島で未亡人は書道を教えている。
私は大正9年春八戸分場から県の穀物藁工品検査所へ転任となりましたが当時は佐藤弘毅分場長在任中であったので私の分場在職中初代分場長佐藤氏、2代丹治氏、3代佐藤氏と3代に亘った次第であります。
大正10年か、佐藤氏の後任に岩田豊技師が分場長に就任、間もなく分場は今の五戸町へ移転になった。
(五所川原市役所)
青森県農業試験場六十年史 昭和34年11月1日 発行 139頁より