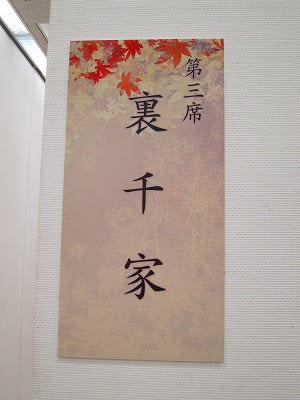北風の強い一日でした。
今日はお稽古でしたが、小さなお茶室ですから吹き飛ばされてしまうのでは・・・と稽古中の人と顔を見合わせてしまいました。
それ程まで、寒い日でしたが、お点前をしている人は汗が流れております。今時の若者は、ハンカチなども持たないのか、腕で汗を拭っております。見かねた人が、ティッシュを持って来てくれました。

栗の茶巾絞り
なぜ汗をかいているかというと、学園祭が終わり、幹部も交代して、新体制でお稽古が始まりましたので、今まで、風炉のお点前しかしなかった2年生が炉を、盆略だった1年生が風炉へと、変わったからです。
やっていることはそれ程変わらないのですが、みんな大汗です。

お稽古が一段落のお茶
しゃべりぱなしですので、咽はからからですの、この一服は何よりのご馳走です。

信号で止まって
夕日に一条の雲ですが、何でしょう??
信号で止まっている間の1枚ですが、1枚だけで信号は青・・・・不思議な雲です。
今日はお稽古でしたが、小さなお茶室ですから吹き飛ばされてしまうのでは・・・と稽古中の人と顔を見合わせてしまいました。
それ程まで、寒い日でしたが、お点前をしている人は汗が流れております。今時の若者は、ハンカチなども持たないのか、腕で汗を拭っております。見かねた人が、ティッシュを持って来てくれました。

栗の茶巾絞り
なぜ汗をかいているかというと、学園祭が終わり、幹部も交代して、新体制でお稽古が始まりましたので、今まで、風炉のお点前しかしなかった2年生が炉を、盆略だった1年生が風炉へと、変わったからです。
やっていることはそれ程変わらないのですが、みんな大汗です。

お稽古が一段落のお茶
しゃべりぱなしですので、咽はからからですの、この一服は何よりのご馳走です。

信号で止まって
夕日に一条の雲ですが、何でしょう??
信号で止まっている間の1枚ですが、1枚だけで信号は青・・・・不思議な雲です。