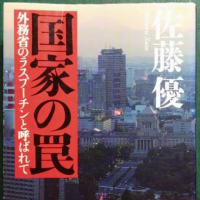佐藤優氏を知るために、初期の著作を読んでみました。
まずは、この本です。
佐藤優『国家の罠 ―外務省のラスプーチンと呼ばれて』

ロシア外交、北方領土をめぐるスキャンダルとして政官界を震撼させた「鈴木宗男事件」。その“断罪”の背後では、国家の大規模な路線転換が絶対矛盾を抱えながら進んでいた―。外務省きっての情報のプロとして対ロ交渉の最前線を支えていた著者が、逮捕後の検察との息詰まる応酬を再現して「国策捜査」の真相を明かす。執筆活動を続けることの新たな決意を記す文庫版あとがきを加え刊行。
国家の罠 ―外務省のラスプーチンと呼ばれて
□序 章 「わが家」にて
□第1章 逮捕前夜
□第2章 田中眞紀子と鈴木宗男の闘い
□「小泉内閣生みの母」
□日露関係の経緯
□外務省、冷戦後の潮流
■「スクール」と「マフィア」
□「ロシアスクール」内紛の構図
□国益にいちばん害を与える外交官とは
□戦闘開始
□田中眞紀子はヒトラー、鈴木宗男はスターリン
□外務省の組織崩壊
□休戦協定の手土産
□外務官僚の面従腹背
□「9・11事件」で再始動
□眞紀子外相の致命的な失言
□警告
□森・プーチン会談の舞台裏で
□NGO出席問題の真相
□モスクワの涙
□外交官生命の終わり
□第3章 作られた疑惑
□第4章 「国策捜査」開始
□第5章 「時代のけじめ」としての「国策捜査」
□第6章 獄中から保釈、そして裁判闘争へ
□あとがき
□文庫版あとがき――国内亡命者として
※文中に登場する人物の肩書きは、特に説明のないかぎり当時のものです。
「スクール」と「マフィア」
外務省には、東大閥、京大閥、慶應閥といったいわゆる学閥は存在しない。代わりに、外務省用語では「スクール」と呼ばれる、研修語学別の派閥が存在する。それらは、「アメリカスクール(英米派)」、「チャイナスクール(中国派)」、「ジャーマンスクール(ドイツ派)」、「ロシアスクール(ロシア派)」などに大別される。
さらに、外務省に入ってからの業務により、法律畑を歩むことの多かった人々は「条約局マフィア」、経済協力に関しては「経協マフィア」、会計部門の専門家は「会計マフィア」というような派閥が存在する。また、近年は主要国首脳会議(サミット)のロジ(宿舎、通信、車回しなどの裏方作業)を担当する「サミットマフィア」というグループも頭角を現してきていた。
人事はもっぱら「スクール」や「マフィア」内で行われ、情報もなるべく部外へは漏らさないことで、省内にはいくつもの閉鎖した小社会が形成されることになった。これがよい方向に出れば、専門家集団としての活力を十二分に生かすことができるし、悪い方向に出れば、不正の温床になってしまう。
2001年に露見した内閣官房報償費(機密費)詐取事件やタクシー券詐取事件は「サミットマフィア」の体質を解明することなくして理解できない。同様に、鈴木宗男氏を巡る外務省疑惑は、「ロシアスクール」の体質を解明することなくして理解できない。
外務省の場合、対露政策については、欧州局長の指揮下、ロシア課長が具体的戦略を策定し、それが通常日本の外交政策となる。欧州局長なりロシア課長が「ロシアスクール」の有力者で占められているときは特に問題は生じない。しかし、人事の巡り合わせから局長、課長がロシア専門家ではない、あるいは「ロシアスクール」に属していても能力的に劣る人物の場合には、実質的な意思決定が「ロシアスクール」の親分格の人々によってなされることになる。この親分格にあたるのが丹波實氏(外務審議官、駐露大使を歴任)であり東郷和彦氏(欧州局長、駐オランダ大使を歴任)だった。
人事についても、公には人事課に決定権があるのだが、ロシア関係者、中国関係者や会計関係者については、「ロシアスクール」、「チャイナスクール」、「会計マフィア」ががっちりと握っている。組織内部に異なる潮流が存在するのはよくある現象であり、これが組織を活性化する基盤となることも少なくない。そして、同じ考えをもつ人同士がグループ、つまり派閥を作るというのもごく自然な現象である。
派閥があれば必ず抗争が生じ、それはまた必然的に人事と結びつく。しかし、派閥の存在が肥大化すると、往々にして抗争自体が自己目的化しはじめることになる。そうした動きを組織が抑えきれず、組織の目的追求に支障を来すようになった時、組織自体の存亡にかかわる危機となるのである。
外務省の場合、田中眞紀子外相の登場により、組織が弱体化したことで、それがこれまで潜在していた省内対立を顕在化させることになり、機能不全を起こした組織全体が危機的な状況へと陥った。その際、外務省は、そもそも危機の元凶となった田中眞紀子女史を放逐するために鈴木宗男氏の政治的影響力を最大限に活用した。そして、田中女史が放逐された後は、「用済み」となった鈴木氏を整理した。この過程で鈴木宗男氏と親しかった私も整理された――。
こう見ていくと、実にわかりやすい構図だと言えよう。
【解説】
外務省には、東大閥、京大閥、慶應閥といったいわゆる学閥は存在しない。
これについてはどうなんでしょう。
鈴木宗男氏の『闇権力の執行人』によると、外務省には学閥がないとされるが、例外がふたつだけあるという。
一つは「如水会」という一橋大学グループで、もう一つが創価大学閥だという。
みなさん御存知の「大鳳会」ですね。
佐藤氏はこのことを知っていたはずなのに、なぜか言及していません。
派閥があれば必ず抗争が生じ、それはまた必然的に人事と結びつく。しかし、派閥の存在が肥大化すると、往々にして抗争自体が自己目的化しはじめることになる。そうした動きを組織が抑えきれず、組織の目的追求に支障を来すようになった時、組織自体の存亡にかかわる危機となるのである。
外務省の場合、田中眞紀子外相の登場により、組織が弱体化したことで、それがこれまで潜在していた省内対立を顕在化させることになり、機能不全を起こした組織全体が危機的な状況へと陥った。その際、外務省は、そもそも危機の元凶となった田中眞紀子女史を放逐するために鈴木宗男氏の政治的影響力を最大限に活用した。そして、田中女史が放逐された後は、「用済み」となった鈴木氏を整理した。この過程で鈴木宗男氏と親しかった私も整理された――。
たしかに、わかりやすい構図ではあります。
獅子風蓮