2月上旬、仕事で被災地に足を運んだ。
仙台から沿岸部の名取地区へ行き、田んぼの除塩作業の進捗状況を取材して、そのまま北上して塩釜、東松島を通って、石巻、女川、南三陸町から気仙沼へ。
大震災から3カ月も経たない6月初めに、岩手県久慈港からやはり沿岸部を北上して八戸港を訪ねたが、そのときより今回のほうが衝撃が大きかったのは、被災から11カ月を経ようというのに、被災地が無残な姿のまま復興とは程遠い状況だったからだ。
石巻で沿岸部の木材加工工場を取材して、女川、気仙沼では漁業関係の方から話を聞いた。小雪がちらつく中、気仙沼から陸前高田、大船渡を経て釜石までひた走る(運転したのはカメラマンさんだったけど)。
津波に襲われた地域とそうでない地域の落差の大きさを地元の人は「天国と地獄」と言ったけど、まさにその通りだった。すべてを失った人たちといつもの日常を続けられる人たちが同じ地域に暮らす現実の重みがついて回る旅だった。
被災した様子は映像や写真で見てきたけれど、現場の空気感は報道からでは伝わらないということを実感した。やはり行かなければ肌身で感じることはできない。それくらいシビアな出来事だったのだと思い知らされた。
カメラマンとして画像を残す立場ではなかった私は、なおのこと行く先々の惨状をカメラに収めることができなかったし、私ごときがそれをしても伝えられるものではないと思った。カメラを構えることもはばかられる気がした。「心に刻む」、それしか私にできることはないと思った。
それなのに、現場の声は陳情と要求しかないと考えている、ある省の広報担当の役人は、カメラマンが撮影した被災地の写真を、震災後1年の特集を組む広報誌に掲載しようとしたら、「上(幹部)から『けしからん』と言われたから差し替えろ」と言う。「復興している写真が欲しい」と言う。「現地は一部復旧している所はあっても、がれきは山のように積まれたままで、主幹産業も『復興』などという言葉とは程遠い状況だった」と告げると「ええ~、そうなんだ」とぬかした。
そんな「小役人の鏡」のような人と対峙しながら悶々としていたので、ブログも更新できずに日が過ぎてしまったのであった。















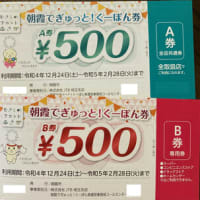










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます