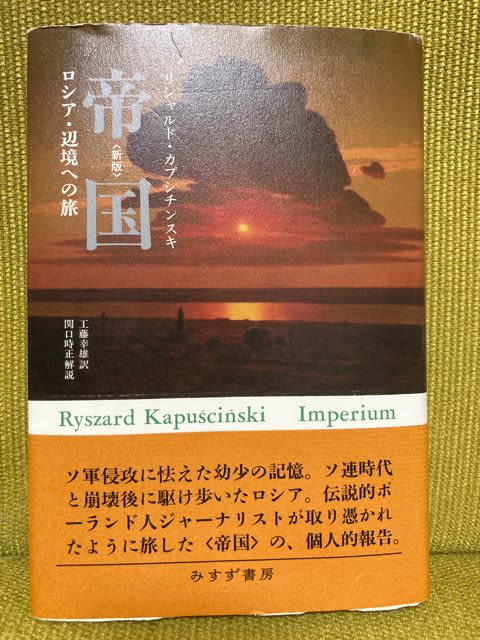長與進『チェコスロヴァキア軍団と日本1918-1920』(2023年、教育評論社)
チェコスロヴァキア、もはや存在しないこの国が誕生する最中の1918年から1920年の2年間、それはこの国と日本との関係が一番近かった2年間でもあった。本書は、建国過程にあった中欧の小国と当時の日本との関係を、一次史料に丹念にあたりながら、禁欲的でありながら丁寧な筆致で描き出した一冊である。
この時期、両国関係が非常に近しいものだった理由は本書のタイトルにある「チェコスロヴァキア軍団」の存在にある。後のチェコスロヴァキアとなる地域は長くオーストリア=ハンガリー帝国の支配下にあった。第一次世界大戦の勃発後、オーストリア=ハンガリーの兵士として徴兵されたこの地域の人々は、ハプスブルクのために戦うことを嫌いロシア軍に投降、この投降した兵士らによってつくられたのがチェコスロヴァキア軍団であった。ところがチェコスロヴァキア軍団の命運はロシア革命によって一変する。行き場を失ったチェコスロヴァキア軍団を極東経由で「救出」する構想が協商国側を中心に持ち上がる。そこに積極的に関与したのが日本であった。
日本史においてシベリア出兵と称されるこの出来事は、第一次世界大戦とロシア革命のどさくさにまぎれた日本による大陸進出の試みと言えるが、それが実質上はともかく、「チェコスロヴァキア軍団救出」を名目としていた以上、両国間、あるいはそこに住む人同士の間に様々な出来事を引き起こしている。
チェコスロヴァキア軍団の成り立ちや、その世界史の中の位置、各国のかかわりなどについては林忠行『チェコスロヴァキア軍団―ある義勇軍をめぐる世界史』(2021年、岩波書店)という良書がすでに存在するが、本書は同じくチェコスロヴァキア軍団を中心的テーマに置きつつも、そのような世界史的な議論ではなく、そうした日本との関係の中で生じた様々な出来事を積みかさねながら、歴史の一側面を描き出している。
本書のおもろしさはその「周辺性」とでもいうべきものにある。あるいは慎ましさとでもいうべきであろうか。日本史においてシベリア出兵は重要な出来事であるが、それは上述したような大陸進出(とその後の破局的なアジア=太平洋戦争)の流れの中に位置づいて理解されるからこそであって「名目上の理由」に過ぎなかった「チェコスロヴァキア軍団」との関係は周辺的なテーマとならざるを得ない。同様に、チェコスロヴァキアの歴史においてその独立過程のなかでのチェコスロヴァキア軍団は大きな位置を占めるのであろうが、独立プロセスのなかではむしろ欧米各国との関係が重視されるのであって、地理的にも離れた日本との関係が大きなテーマ性を持ち得るとは考えにくい。このように二重の意味で周辺的な位置づけとなるテーマを取り扱っているにもかかわらず、本書が描き出すこの時期の二国間関係(というより両国に住む人たちの関係といった方が正確であろう)は非常にヴィヴィッドであり、とても興味深い。それは、本書で行われているのが、一次史料から浮かび上がる歴史のひとコマひとコマを丁寧に追う作業であり、そこで描かれている一つひとつの小さなエピソード(それらは世界史的大事件のような耳目をひくようなものではない)について史料から語り得るものを語り得る範囲で語るという禁欲的な姿勢に著者が終始しているからであろう。
本書は序章と終章をのぞけば7つの章で構成されているが、主には6つのエピソード(チェコスロヴァキア建国の父であり初代大統領であるT・G・マサリクの日本訪問、東部シベリア、オロヴャンナヤ駅でのチェコスロヴァキア軍団と日本軍の邂逅、チェコスロヴァキア軍団の傷病兵と日本人看護婦との東京やウラジヴォストークでの医療面での交流、山ノ井愛太郎という日本最初のチェコ語学習者の一人、遭難したチェコスロヴァキア軍団の帰国船が日本近海で救助されたヘフロン号事件、両軍が衝突したハイラル事件)を取り上げている。一つひとつは上述したように大事件ではなく、良く知られている話ではない。それを史料から読み解いていく作業はさながらミステリーを読むような面白さがある。しかし、残念ながら歴史には作者がいないのであり、史料から語り得るものには限界がある。もう少しというところで迷宮入りしてしまい、真実がわからないエピソードも多いが、歴史家らしい著者の禁欲的姿勢は、むしろ読者の歴史理解を深めてくれているように思える。また、それぞれのエピソードが決してすべてが相互に関連しているわけでもない。しかし、それを通じて読むことによってこの時期の日本とチェコスロヴァキアの関係が浮かび上がってくるのが不思議である。
一つひとつの小さなエピソードを読み進めることによって、しかし通読してみると、全体として、歴史の流れが見えてくるというのはまさに歴史を読む面白さであり、恐らくは歴史を書く醍醐味でもあるのではないだろうか。本書はそんな歴史の楽しさを改めて教えてくれる一冊といえる。