衆議院選挙が「公示」された。
先日、この「公示」と「告示」の違いについて与太話をしたのでちょっと調べてみた。
産経新聞の記事【イチから分かる衆院選】どう違う?公示と告示(2009.8.18 09:16
)によると
--以下一部引用--
「最も大きな違いはだれが告知するかだ」ということで、公示は、憲法第7条にもとづく天皇の「国事行為」とされ、「また参院選も同じだ」とのこと。
「一方、告示を使う場合は、知事選や都道府県議選、市町村長選などの地方選挙。選挙管理委員会が告知するため、公示とは区別される。では、衆院補選の場合はどちらか。国会議員を選ぶ選挙だが、国事行為ではないので告示となる」ということだ。
--引用終わり--
というわけで、憲法を見てみると
--以下引用--
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一,二 (略)
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
--引用終わり--
という条項がある。
この憲法第7条第4号に基づき衆議院議員選挙は「公示」されるわけだ。
しかし気になるのは憲法では「総選挙」の施行を公示するとなっている点だ。
普通、総選挙といえば衆議院議員選挙のことをいうはず。参議院選挙は含まれないのではないか。
実際、wikipediaでは
--以下引用--
参議院議員通常選挙は全国規模の国政選挙ではあるが、総議員を一斉に選出するわけではなく半数改選であるから「総選挙」とは呼ばず、公職選挙法32条は3年ごとの参議院議員選挙を「通常選挙」と呼んでいる。
--引用終わり--
となっている。ではなぜ、参議院選挙までが「告示」ではなく「公示」となってしまうのか。
こちらのサイトにその答えが載っていた。
--以下引用--
そこで調べてみると、どうも、憲法でいうところの 「総選挙」 と、公職選挙法でいうところの 「総選挙」 とは、同じ字で同じ読みであるにも関わらず、意味が違うようなのである。
手っ取り早く言うと、憲法第7条でいう 「総選挙」 は、衆院選だろうが参院選だろうが構わず、全国で一斉に実施する国政選挙 を指すが、公職選挙法でいう 「総選挙」 は、議員全員を選び直す選挙 (つまり、いわゆる衆議院選挙のこと) のみ を指しているようなのである。
--引用終わり--
この点は、上述のwikipediaによると
--以下引用--
日本国憲法第7条4号の「総選挙」については、同条が「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と規定しており、衆参問わず各議院の国会議員を選出する基本的な選挙の公示を天皇の国事行為として定めた趣旨であると解されることから、憲法7条4号の「総選挙」には参議院議員通常選挙が含まれると解するのが通説である
--引用終わり--
となっている。
この点は実用的な理由もあるようで、上記サイトでは
--以下引用--
参院選を 「総選挙ではない」 と規定する限りは、憲法の条文を文字通り解釈すれば、参院選をまとめて 「公示」 することができなくなり、日本中の選挙管理委員会がそれぞれ別個に、あるいは連名で 「告示」 しなければならなくなる。
--引用終わり--
という点が指摘されている。
つまり、「地方単位の選挙管理委員会が一斉に行われる国政選挙をスタートさせることの違和感と、その煩雑さを解消するため」に、便宜的にスタートポイントだけは 「総選挙」 扱いにしているということではないだろうか、という指摘である。
とここまで書いたところで、件の憲法第7条第4号、英文だとどうなっているかなと思って調べていたら、新事実を発見。
ここのサイトによると
--以下引用--
憲法では『総選挙』という言葉はこの7条四号の他に、54条1項、70条、79条2号で2回、合わせて5回使われています。
しかし、7条四号以外は必ず、『衆議院議員の総選挙』と表現されています。
--引用終わり--
とのこと。つまり上述の解釈は少し違っていて、憲法と公職選挙法の間で「総選挙」という言葉の意味がずれているのではなく、「憲法第7条4号における『総選挙』」の意味のみが他とずれているようなのだ。つまりここだけが「国会議員」となっていて、参議院議員をも「総選挙」の対象とするような記述となっているわけだ。
実にややこしい。
ちなみに上記サイトによると、憲法の英文表記
--以下引用--
7条四号では『 general election of menbers of the Diet』
その他の条文はみな『general election of the menbers of the House of Representatives』となっています
--引用終わり--
ということです。
うーむ、ややこしい。
先日、この「公示」と「告示」の違いについて与太話をしたのでちょっと調べてみた。
産経新聞の記事【イチから分かる衆院選】どう違う?公示と告示(2009.8.18 09:16
)によると
--以下一部引用--
「最も大きな違いはだれが告知するかだ」ということで、公示は、憲法第7条にもとづく天皇の「国事行為」とされ、「また参院選も同じだ」とのこと。
「一方、告示を使う場合は、知事選や都道府県議選、市町村長選などの地方選挙。選挙管理委員会が告知するため、公示とは区別される。では、衆院補選の場合はどちらか。国会議員を選ぶ選挙だが、国事行為ではないので告示となる」ということだ。
--引用終わり--
というわけで、憲法を見てみると
--以下引用--
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一,二 (略)
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
--引用終わり--
という条項がある。
この憲法第7条第4号に基づき衆議院議員選挙は「公示」されるわけだ。
しかし気になるのは憲法では「総選挙」の施行を公示するとなっている点だ。
普通、総選挙といえば衆議院議員選挙のことをいうはず。参議院選挙は含まれないのではないか。
実際、wikipediaでは
--以下引用--
参議院議員通常選挙は全国規模の国政選挙ではあるが、総議員を一斉に選出するわけではなく半数改選であるから「総選挙」とは呼ばず、公職選挙法32条は3年ごとの参議院議員選挙を「通常選挙」と呼んでいる。
--引用終わり--
となっている。ではなぜ、参議院選挙までが「告示」ではなく「公示」となってしまうのか。
こちらのサイトにその答えが載っていた。
--以下引用--
そこで調べてみると、どうも、憲法でいうところの 「総選挙」 と、公職選挙法でいうところの 「総選挙」 とは、同じ字で同じ読みであるにも関わらず、意味が違うようなのである。
手っ取り早く言うと、憲法第7条でいう 「総選挙」 は、衆院選だろうが参院選だろうが構わず、全国で一斉に実施する国政選挙 を指すが、公職選挙法でいう 「総選挙」 は、議員全員を選び直す選挙 (つまり、いわゆる衆議院選挙のこと) のみ を指しているようなのである。
--引用終わり--
この点は、上述のwikipediaによると
--以下引用--
日本国憲法第7条4号の「総選挙」については、同条が「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と規定しており、衆参問わず各議院の国会議員を選出する基本的な選挙の公示を天皇の国事行為として定めた趣旨であると解されることから、憲法7条4号の「総選挙」には参議院議員通常選挙が含まれると解するのが通説である
--引用終わり--
となっている。
この点は実用的な理由もあるようで、上記サイトでは
--以下引用--
参院選を 「総選挙ではない」 と規定する限りは、憲法の条文を文字通り解釈すれば、参院選をまとめて 「公示」 することができなくなり、日本中の選挙管理委員会がそれぞれ別個に、あるいは連名で 「告示」 しなければならなくなる。
--引用終わり--
という点が指摘されている。
つまり、「地方単位の選挙管理委員会が一斉に行われる国政選挙をスタートさせることの違和感と、その煩雑さを解消するため」に、便宜的にスタートポイントだけは 「総選挙」 扱いにしているということではないだろうか、という指摘である。
とここまで書いたところで、件の憲法第7条第4号、英文だとどうなっているかなと思って調べていたら、新事実を発見。
ここのサイトによると
--以下引用--
憲法では『総選挙』という言葉はこの7条四号の他に、54条1項、70条、79条2号で2回、合わせて5回使われています。
しかし、7条四号以外は必ず、『衆議院議員の総選挙』と表現されています。
--引用終わり--
とのこと。つまり上述の解釈は少し違っていて、憲法と公職選挙法の間で「総選挙」という言葉の意味がずれているのではなく、「憲法第7条4号における『総選挙』」の意味のみが他とずれているようなのだ。つまりここだけが「国会議員」となっていて、参議院議員をも「総選挙」の対象とするような記述となっているわけだ。
実にややこしい。
ちなみに上記サイトによると、憲法の英文表記
--以下引用--
7条四号では『 general election of menbers of the Diet』
その他の条文はみな『general election of the menbers of the House of Representatives』となっています
--引用終わり--
ということです。
うーむ、ややこしい。











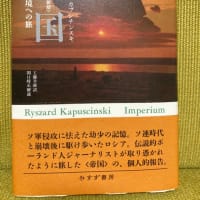
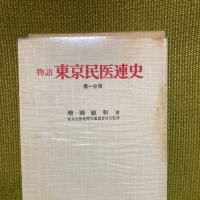







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます