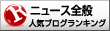上杉氏憲は各領主から人質を取っていたものの、その頃から、関東の情勢は次第に氏憲方に不利な様相を呈してきた。一つには、将軍・義持が氏憲らを“逆賊”と決めつけ、これを討伐する態度をはっきりと表明したからである。日頃は優柔不断な義持だが、断固として戦う姿勢を示したことが大きな要因だろう。
もう一つはこの戦乱から、公方の足利持氏と管領の上杉憲基が生き長らえたことである。前にも述べたように、持氏は駿河の今川範政のもとに逃れ、憲基は越後の上杉房方に庇護された。そして、範政と房方はこの2人を擁して逆襲に転じてきたのだ。やがて12月下旬になって、まず氏憲方の軍勢と今川勢が駿河国で戦うことになった。
この戦いの詳しいことは分からないが、持氏を擁した今川勢が氏憲軍に圧勝し、氏憲らはほうほうの体(てい)で鎌倉に逃げ帰ったという。これに呼応するかのように、武蔵国でも上杉勢が攻勢に出て氏憲方の豪族を次々に打ち破っていった。こうなると、態度を明らかにしていない“日和見”の領主らは、大部分が持氏・憲基の陣営に馳せ参じてきた。
石神井城の周辺でも、氏憲方の軍勢は浮き足立って自分の領地へ引き上げる者が出てきた。石神井城はおのずと安泰な状況になってきたのである。こうなると、居候のように身を寄せていた山口貞清は義父の豊島範泰に願い出たのだ。
「父上、もうこの地域は敵も少なくなり、安全な状況になってきました。それがしはそろそろ山口に戻り、あの一帯をわが陣営で治めたいと思います。よろしいでしょうか」
「うむ、それは結構なことだ。敵が少なくなったので、わしもこちらから打って出ようと考えていた。貞清殿、貴殿も領地の方が心配だろう。山口へ戻って、あの地を早く治められるのが得策だろう。わしにはまったく異存はない」
「ありがとうございます。山口の周辺からは敵も退散しているでしょう。情勢は日増しにわが陣営に有利になってきています。もし敵がいても、今度こそ追い払うだけです。本当にご厄介になりました」
「なんのなんの、わしが寂しく思うのは、お転婆なお牧がいなくなることだけだ。いや、騒々しい娘がいなくなれば、ここも静かで平穏になろう。はっはっはっはっは」
範泰が愉快そうに笑ったので、貞清も苦笑した。こうして2人が話を付けたため、山口勢は帰国することになったが、敵兵がまだあちこちに散在している危険性はあった。このため、尾高武弘の部隊が斥候を兼ねた先遣隊として出発したのである。
「庄太殿、怪我はだいぶ良くなったようですね」
武弘が先を行く庄太に声をかけると、彼は振り向いて明るく答えた。
「ええ、まだ少し痛みますが、ようやく治ってきました」
前にも述べたが、庄太は戦闘で右肩に重傷を負ったのだ。武弘も手足に相当の怪我をしたが、石神井城にいるうちにほとんど治っていた。
「お互いに無事で良かった・・・」
武弘がつぶやくように言ったが、戦いはこれからも続くだろう。山口へ帰る途中、2人の目には広々とした田園風景が映ったが、田畑や森の景色が彼らの心を癒やしたようだ。どんなに戦いが苛烈になろうと、敵も味方もこの豊かな自然を壊すことはできない、武弘はそう思った。
彼の部隊が山口の領地に着くと、案の定、敵兵の姿は見えなかった。氏憲方はそれほど重要ではないこの地を捨てて、他の場所に移ったのだろう。使いの者が味方の陣へすぐ報告に走った。やがて、武弘らは山口城の館に入ってゆく。
「殿、ずいぶん焼けましたな~」
「うむ、これでは当分使いものにならないか」
佐吉が嘆き声を上げる・・・半分ほど焼け落ちた館に、武弘も思わずため息をついた。
「すぐに館の応急措置、いや、建て直しに取りかかりましょう。しかし、怪我人も多いし、なんと言っても亡くなった人を弔わねばなりませんね」
「うむ、稲村幸正殿をはじめ12人が亡くなっている。その人たちの葬儀が先だ。佐吉、そちらの準備に取りかかってくれ」
「分かりました。さっそく葬儀の準備を始めます」
佐吉はそう答えたが、一呼吸置いて意外なことを言い出した。
「殿、実は一両日中に、藤沢の方から詩織が情報を伝えに来るようです」
「なに、あの詩織殿が・・・それはどういうことか?」
「貞清さまが藤沢の情勢を内密に知りたいというので、私が詩織と打ち合わせをしておいたのです」
「そうか、貞清さまもいろいろ手を打っているのだな。しかし・・・お主はいま“詩織”と呼び捨てにしたぞ。彼女とそんなに親しいのか?」
「いや、これはバレましたな、はっはっはっはっは。そのうち、殿に本当のことを言おうと思っていましたが、私は詩織と“関係”ができてしまいました。いつ言おうかと迷っていましたが、いま正直に打ち明けます」
「いや、これは驚いたな。さては小百合さまの件でいろいろあったのか?」
「まあ、そういうことです。小百合さまのことで長らく詩織と付き合っていましたからね」
「そうか、気が付かなんだ。それで、詩織殿とはいつ祝言をあげるのか?」
「殿、この話はもうやめましょう。今は戦いの真っ最中、祝言をあげるどころではありません。いずれ落ち着いたら、ご報告します」
「そうだな、楽しみにしているぞ。とにかく葬儀の準備が先だ。よろしく頼む」
「はい」
話が終わると、佐吉はさっそく葬儀の支度で領内に出かけていった。そうこうするうちに、山口貞清らの本隊が城に到着した。無残に焼け落ちた館を目(ま)の当たりにして、ほとんどの人が茫然とたたずんでいる。貞清が武弘たちに言った。
「ひどいものだ。一から出直す気持でやるしかない」
「殿、幸正殿らの葬儀を早くしなければなりません。いま、佐吉にその準備を命じたところです」
「うむ、ご苦労、そうしてくれ」
武弘はなおも貞清に聞いた。
「藤沢の方はどうなっているのでしょうか。小百合さまのことなどが心配です」
「一両日中に何か知らせがあると思う。それを待ってから考えよう」
貞清は落ち着いて答えたが、武弘は小百合のことがどうしても気になったのである。
山口勢がもとの領地に戻った頃、豊島範泰は兵を率いて逆襲に転じた。彼は味方の軍勢とともに相模国に入り、氏憲方と一戦を交えることになった。応永24年(西暦1417年)の元日、両軍は世谷原(せやはら)という所で激突したが、この戦闘は氏憲方が必死に戦ってなんとか勝利を収めた。
一方、太田城を攻めていた藤沢忠宗の軍勢は、太田勢の頑強な抵抗に遭いついに撤退を余儀なくされた。忠宗は兵を引き連れ藤沢城に戻ったが、この頃から形勢は足利持氏の方が明らかに有利な展開になったのである。
そうしたさなか、山口貞清は尾高武弘を呼んでこう述べた。
「亡くなった兵士らの葬儀も済み、われわれはいよいよ攻勢に転じようと思う。公方さまからの指令もあり、わが軍は相模国に出陣する。最終的に鎌倉を攻めるが、その前にわれわれは藤沢城を攻略しなければならない。ついては、どうしても聞いてもらいたいことがあるのだ」
「何なりとお申し付けください」
「うむ、実は妹から内密に知らせがあったが、藤沢家は志乃さまを鎌倉に人質として出し、小百合母子は城に残っているというのだ。そこで藤沢城を攻めるに当たり、なんとしても小百合たちを救出しなければならない。それは分かるな?」
武弘は重要な命令がついに来たなと思った。もとより、彼も小百合のことが気になっていたので、これは当然のことなのだ。
「小百合さまの救出をそれがしが受け持てということですね」
「そうだ、その方にぜひやってもらいたい」
「分かりました。命をかけてもやりとげます」
「そう思い詰めないでくれ。お主と小百合は子供の頃からの仲だ。それを知っているからこそ頼んでいる。しかし、無理はしないでくれ」
貞清はそう言ったが、武弘は無理をしてでもやり遂げなければならないと心に誓った。もし、小百合の救出に失敗すれば、貞清はなんと思うだろうか。彼の落胆ぶりは目に見えるようだ。ここは武士の意地にかけてもやり遂げなければならない。その決意を秘めて、武弘は帰路についた。
山口城が火災の被害を受けたため、武弘一家は昔 住んでいた農家風の一軒家を仮の宿にしていた。この家は城から300メートルほどの所にあるが、武弘が幼少の頃に居たことがある。もともとは尾高家の住まいだったが、父の武則が重臣に取り立てられてから城の館に移ったのだ。
だから、武弘にとっては懐かしい住まいだと言ってよい。彼は帰宅すると、さっそく小巻に貞清との話を説明した。彼女は心配そうな表情を浮かべて聞いてくる。
「あなたが小百合さまを救出しようというのは分かりますが、もしそれが果たせないとどうなるのですか?」
「そんなことは考えもしない。とにかく救出するのだ。佐吉にも十分に言い含めて、万全の態勢をとる。佐吉は詩織殿と連絡をとって、いろいろ手立てを講じるだろう。心配するな」
武弘は小巻に、なんの不安もないような様子を見せるのだった。
その年の冬は特に寒い感じがした。雪もよく降るし、風も冷たい。元気が良いのは4歳の太郎丸だけで、しきりに外で遊びたがる。武弘はチャンバラごっこなどにできるだけ付き合っていたが、迫りくる次の戦闘のことが気になって仕方がなかった。
そうした折、駿河国で圧勝した今川範政の軍勢が箱根峠を越え、一気に相模国の国府津(こうづ)へ進出したという知らせが届いた。これは上杉氏憲方にとって脅威そのものだ。今の東海道をまっすぐ東進すればじきに鎌倉に至る。このため、瀬谷原の戦いに勝った氏憲軍もあわてて鎌倉に戻ったのである。
(6)
1月上旬のある日、山口貞清は家臣たちにまもなく相模国へ出撃するとの指令を発した。いよいよ最後の戦いが始まろうとしている。武弘たちは緊張が高まるものの、闘志が湧いてくるのを感じた。佐吉はすでに藤沢城の方へ行っている。彼からの連絡を待ちながら、武弘は充実した時を過ごしていた。
山口の軍勢が出立する前に、小巻が喜ばしい話を彼に告げた。
「第3子を身ごもったようです。あなたが出発する前に言っておかねばと」
「おお、それはめでたい。いつごろ生まれるのだろうか・・・」
「たぶん、夏ごろでしょう」
武弘が嬉しそうに語ると、小巻も可憐な笑顔を浮かべて答えた。太郎丸と鈴の2人の子供に恵まれているから、彼はそれ以上のことは考えていなかった。ただ丈夫で元気な子が生まれれば良い。それ以上のことを望めば欲張りというものだ。武弘は小巻のことがただ無性に愛らしく思えた。
出陣の前日は雪が降った。父と母は別室で休んでいる。武弘と小巻は囲炉裏の端で横に並び、寝具に身を包んだ。傍らでは太郎丸と鈴がすやすやと眠っている。冷たい隙間風が土間(どま)を渡って板の間に流れてくる。武弘と小巻は自然に寄り添った。
「今夜はとても寒いね」
武弘が低い声で話しかけると、小巻は黙ってうなずいた。やがて2人はひしと抱き合い、愛の“交わり”に身をゆだねる・・・どのくらいの時がたっただろうか。静寂が辺りを支配し、聞こえるものといえば土間の薪(たきぎ)が燃える音だけだ。
2人の子供は相変わらすやすやと眠っている。武弘はやや身を起こし、傍らの小巻に目をやった。寝具がずれて彼女の裸体がほのかに見える。それは“人魚”のように美しく息づいている。まるで幻(まぼろし)の中から浮かび上がったようだ。
武弘はしばらく小巻の肢体に見とれていたが、彼女はそれに気づいただろうか。やがて、彼はまた小巻の体に身を任せた。なんだかこれが最後の交わりのように思える。武弘は心残りがないようにその夜を過ごした。
翌日、貞清らの山口勢が出陣することになった。武弘は両親と妻子らに別れの挨拶をすると、見送りに来た姉の忍(しのぶ)が声をかけてきた。
「これが最後の出陣になりますよう、ご武運を祈ります。十分に気をつけて行ってください」
「分かりました。皆さんもお元気で!」
武弘が答えると、太郎丸が母親に教わったのか真面目な顔をして言った。
「行ってらっしゃいませ。ご武運を祈ります」
これには武弘も笑いを堪えることができず、手を振りながら山口城を後にした。貞清の軍勢はせいぜい130人程度だが、みんな闘志がみなぎっており、降る雪もなんのそのという感じだった。一行は途中で豊島氏など味方の軍勢に合流した。
貞清は義父の豊島範泰に語りかけた。
「今度こそ氏憲勢を根こそぎ退治しようと思います」
「わしも瀬谷原(せやはら)では不覚を取ったが、今度は必ず勝ってみせるぞ」
範泰も雪辱の意気に燃えていた。こうして鎌倉公方・足利持氏方の軍勢およそ2500人が武蔵国から相模国へ進撃していった。そして、国境いまで来た時、佐吉ともう1人の“間者”が慌てふためいた様子で軍勢のもとに駆けつけて来たのである。佐吉が貞清と武弘らにご注進に及んだ。
「ご報告します。一昨日、鎌倉・雪ノ下で上杉氏憲公のほか足利満隆さま、持仲さまが今川勢などの攻撃を受け自害されました!」
「なにっ、それはまことか?」
驚いた貞清が問い返す。
「はい、ほかの氏憲方の兵も散り散りになって逃走したということです」
「う~む・・・」
貞清も武弘もしばらく二の句が継げなかった。あまりにも呆気ない結末ではないか。やがて、貞清が鎌倉周辺の情勢を尋ねると、佐吉が要領よく答えた。
「氏憲公に味方する軍勢はもういませんが、ただ藤沢城だけがかたくなに抵抗しています。このため、太田資正さまの兵が攻撃を仕かけるとのことです」
「そうか。ところで、鎌倉に人質となった志乃さまのことは何か聞いていないか?」
貞清はやはり藤沢志乃のことが気になるらしい。これには佐吉もすぐには答えられず、一呼吸置いてこう述べた。
「詩織殿の話によれば、志乃さまは近くの寺に避難したと聞いていますが、これはあくまでも未確認情報です」
「ふむ、命に別状がなければよいが・・・分かった、ご苦労であった」
貞清は佐吉の報告を聞いたあと、すぐに豊島範泰のもとへ行った。範泰と貞清が相談した結果、豊島・山口勢はただちに藤沢城を目指すことになったのである。
雪を踏みしめながらの行軍は楽ではなかった。それに冷たい北風が吹きすさび、豊島・山口勢はたびたび休みながら進んで行く。行軍の間、貞清も武弘も小百合救出の方法や対策をいろいろ考えていた。しかし、これといった妙案があるわけではない。とにかく藤沢へ行って、現地の状況を判断しながら行動するしかないのだ。
この一団は途中で味方の軍勢と合流し、公方方の兵力は次第に人数を増やしていった。そして数日後、約3000人の軍勢が藤沢城を包囲したのである。そこでは、太田資正の部隊がすでに城を攻撃していたが、城の防備が固いこともありまったく効果は上がっていなかった。
新たな軍勢が到着し、藤沢城の周辺はますます緊迫してくる。ちょうどそうした時、佐吉が詩織を連れて武弘のところに現われた。周りの人たちには、彼女は味方の“間者”だと言ってある。
「殿、藤沢城のだいたいの構造が分かりました。詩織殿が見取り図を持ってきてくれたので、ご覧ください」
佐吉はそう言うと大きな見取り図を武弘に差し出した。筆で書いたその図は分かりやすく、一目で城の有り様が把握できる。
「うむ、詩織殿、ありがとう。これは大いに参考になる」
武弘がそう答えると、詩織と佐吉が絵図の説明を始めた。城の内部のことはもちろんだが、3人が特に注目したのは“地下道”である。それは城から外部に通じる秘密の通路で、いざという時に脱出などができるように設けられたものだ。
「この地下道は、本当に役に立つのかな?」
武弘が少し疑うように質すと詩織が答えた。
「もちろん、役に立ちます。この地下道の在り処(ありか)を知っているのは城主さまらほんの数人で、家臣もまだほとんど知っていないと思います。私は小百合さまからこの絵図を渡されました。極秘の資料です」
「う~む、いざという時はこの地下道を通るのか・・・」
「はい」
詩織の説明に武弘はうなずき、見取り図を持って貞清のところに行った。
「貴重な資料だな。これをもとに佐吉や詩織殿と打ち合わせ、さっそく小百合たちの救出の手立てを講じて欲しい」
貞清も見取り図に納得したようだ。彼は藤沢城の攻略を第一としながらも、内心は妹やその家族の救出に全力を尽くす考えだった。城攻めはもう先が見えている。3000人の軍勢があれば、城の陥落は時間の問題だろう・・・このため、貞清は小百合たち救出の特別任務を武弘に命じたのである。
これは武弘にとってももちろん望むところで、彼はただちに佐吉と詩織を呼び寄せ“救出作戦”を練ることになった。
一方、豊島範泰を総大将とする軍勢は攻撃を開始したが、藤沢城は堅固な要塞に守られていたため、なかなか思うようにはいかなかった。この城は相模国でも有数の平山城(ひらやまじろ)で、地元の人たちも難攻不落と見ていたのだ。
しかし、城は堅固なものの藤沢勢は徐々に追い詰められる状況になった。それは上杉氏憲方の“敗残兵”を何百人も受け入れたため、兵糧、つまり食糧が欠乏してきたのだ。範泰は攻めあぐねていたものの、その点を見逃さなかった。城の包囲を厳重にして、食糧の持ち込みを遮断する“兵糧攻め”の策を取ったのである。
藤沢城の運命はもはや絶望的になり、藤沢忠則は父の忠道、弟の忠宗と最後の評議を行なった。
「城はもうこれまでです。打って出て討ち死にしますか?」
忠則が質すと忠道が答えた。
「降伏しても、われわれは首を斬られるだけだ。そんなことは分かっている。だからわしは討ち死にしようと思うが、お主は城の当主だ。最後まで戦って“死に花”を咲かせようぞ。それが武士(もののふ)の道だ」
「まことにその通りです。私は城を枕に死のうと思いますが、忠宗はどうか?」
「それがしは父上と同じように打って出て死のうと思います」
「うむ、降伏はせぬということだな。それでよい。ところで父上、小百合や子供たちはどうしますか?」
忠則の問いに忠道は少し考えていた。
「それはそなたに任せよう。できれば、生き長らえて欲しいが・・・」
「はい、私もそう思いますが、このことは小百合と相談します。せっかく母上(注・志乃のこと)が出家されたと聞きますので、なんとか3人には生きていて欲しい。ただ国松は男の子なので、敵がどう出てくるか分かりませんな。もう少し様子を見ましょう」
忠則たちはそういう話をしていたが、降伏しないとなれば小百合たちをどう逃がすのか、最も難しい問題である。秘密の地下道を通すことは簡単だが、もし敵に捕らえられればどうなるか分からない。地下道のことは詩織を通して、暗に山口貞清に伝わっているはずだ。しかし、敵側がどう判断してくるのか。
忠則は今はそれ以上考えても仕方がないので、父や弟と相談したあと、小百合を部屋に呼んだ。
「地下道の在り処は詩織に教えたな」
「はい、間もなく詩織から連絡があると思います」
「うむ、それで父上、忠宗と話し合ったが、われわれ3人は討ち死にや自害を覚悟している。問題は“そこもと”と子供たちのことだが、なんとか生き延びて欲しい。それは藤沢家の存続に関わることだ。それは分かっているな?」
「はい、よく承知しております。ただ子供たちのことは別として、私は殿に殉じたいと思います。そればかりはお許しください」
「なに・・・どうして私と行動を共にするのか?」
忠則は小百合の予想外の返事に少し驚いた。
「私は殿のお側にずっと仕えてきたのですから、それは当然でしょう。しかも、殿は何かと私をかばってくれました。その御恩は決して忘れません。妻が夫に殉じて何が悪いのでしょうか。幸(ゆき)と国松の安全を見定めた上で、私は殿と行動を共にする覚悟です」
小百合の決然とした言上(ごんじょう)に、忠則はしばらく返す言葉がなかった。やがて彼は吹っ切れた表情を浮かべ、優しく彼女に言葉をかけたのだ。
「分かった、そなたの心持はありがたいが、もう少し考えよう。子供たちのためにも、命は大切にな」
それだけ言うと忠則は部屋を出て、館の最上階から敵方の陣営を見渡した。敵はさらに軍勢を増やしたようだ。粉雪が舞う中、かがり火があちこちで揺らめくのが見える。この城の命運もあとわずかなのだろう。寒風を頬に感じながら、忠則は深い溜め息をついた。