転勤族の性でアパート住まいですのでちゃんとした固定シャックを持つことができず現在に至っており、無線を楽しむというと移動運用するかゲストオペででるかといういずれかの選択肢に頼ってきました。国内コンテストは前者、DXコンテストについては後者によることが多いです。この傾向は米国に来ても変わっていませんが、ビッグステーションで運用させて違いを感じるのアンテナシステムの構築方法です。いずれもフルサイズ八木を使う場合が多いですが、日本では多エレメント化するのに対して、当地ではスタック化する場合が多いです。
スタックしたアンテナへの給電にはいくつか方法がありますが、一般的なのはQマッチ、すなわち位相差をうまく活用してインピーダンス調整を行う方法です。より詳しい理論を知りたい方はこちらを参照ください。この方法では75オームの同軸を活用してあげれば比較的簡単に構築することがでいますが、バンド毎にケーブルを用意する必要があること、また偶数単位では比較的簡単に対応できるもののスタック数が奇数枚のアンテナになると構築が難しくなります。また、スタックの構成を自在に切り替えることもかなり難しくなります。Qマッチで2スタックの場合の単体およびスタックの切り替えについてはこちらの記事が参考になります。
実際、当地でスタック化が使われている理由はアンテナゲインを上げることよりも特に打ち上げ角を下げることを目的にされることの方が主目的であることが多く、かつコンテストではコンディションに応じて打ち上げ角に切り替えができるようにしていることが多いです。
この目的にあうデバイスがいわゆるスタックマッチと呼ばれるもので、現在Array Solutions傘下にあるWX0Bが製造しているブルーのケースのものが有名です。
さて、前書きが長くなりましたがこのデバイスどのようなものなのかということで以前WX0Bの商品を購入して中身をみてみましたが意外と構成は簡単です。
Balunに似たものでUNUNというものがありますが、これを使うとインピーダンス変換が可能です
変換比を2.25:1にすると、二つの50オームのアンテナをつなぐと56オーム、アンテナ3本だと37.6オームということで、SWRに直すと1.5以内に収まるとうことになります。
スタックマッチではこれにリレーでアンテナ切り替えを加えて色々な組み合わせで切り替えることができるようになっています。WX0Bの従来の商品はダイオードで作ったマトリックスをリモートスイッチで切り替えるというものですが、最近プッシュボタン式でそれぞれの組み合わせへクイック切り替えできるスイッチボックスもでてきています。K1TTTのところでは自作のものを商品化される前から使っていました。

エンジニア系ではない私には理論的解説はこの程度の説明が精一杯ですが、実際にこのデバイスの中身を見てみるとそれほど複雑ではないというの第一印象で自作ができないのかなと思いました。それで調べてみるといくつか参考になるサイトがありました。
まず、SM2WMVがStackerというスタックマッチ用のPCB基板を販売しています。円安になってしまった現在ではあまり妙味はありませんが、価格は40ユーロです。なお、キットではありませんのでコアやリレーなどの部品は別途調達する必要があります。
なお、SM2WMVはこの基板の他に6ポートのアンテナ切り替え器やSO2Rなどのコンテストで必需品のいわゆる6パック、4Qアンテナ用ボード、高出力向けコネクタ対応バージョンなども配布しています。
実際にこの基板を使った作成記事としてはDH1TWのものが写真など参考になります。You Tubeにもいくつかこの基板を使って作ったものをテストしているものがあります。
コアとしてはアミドンのFT240-61が推奨されており、巻き数が多いとローバンド向け、減らすとハイバンド向けとなるようで、また高出力の場合はコアを重ねることで対応できるようですがコア1つでもOM-3500クラスのリーガルパワー以上のクラスのリニアでも十分とのことです。
日本までの郵送料を考えるとどうなるかわかりませんが、当地ではここでコアを入手するのが一番安そうです。
この他に参考になるものとしてはコンテスト好きが高じてモロッコにスーパーステーションを構築したW7EJ がシャックの装置の回路図を公表しており、こちらに切り替え器の回路図もありますので参考になります。かれは基板を使わずに自作しており、写真を見ると基板無しでもいけそうでこれならコストを抑えて自作が可能そうです。
スタックしたアンテナへの給電にはいくつか方法がありますが、一般的なのはQマッチ、すなわち位相差をうまく活用してインピーダンス調整を行う方法です。より詳しい理論を知りたい方はこちらを参照ください。この方法では75オームの同軸を活用してあげれば比較的簡単に構築することがでいますが、バンド毎にケーブルを用意する必要があること、また偶数単位では比較的簡単に対応できるもののスタック数が奇数枚のアンテナになると構築が難しくなります。また、スタックの構成を自在に切り替えることもかなり難しくなります。Qマッチで2スタックの場合の単体およびスタックの切り替えについてはこちらの記事が参考になります。
実際、当地でスタック化が使われている理由はアンテナゲインを上げることよりも特に打ち上げ角を下げることを目的にされることの方が主目的であることが多く、かつコンテストではコンディションに応じて打ち上げ角に切り替えができるようにしていることが多いです。
この目的にあうデバイスがいわゆるスタックマッチと呼ばれるもので、現在Array Solutions傘下にあるWX0Bが製造しているブルーのケースのものが有名です。
さて、前書きが長くなりましたがこのデバイスどのようなものなのかということで以前WX0Bの商品を購入して中身をみてみましたが意外と構成は簡単です。
Balunに似たものでUNUNというものがありますが、これを使うとインピーダンス変換が可能です
変換比を2.25:1にすると、二つの50オームのアンテナをつなぐと56オーム、アンテナ3本だと37.6オームということで、SWRに直すと1.5以内に収まるとうことになります。
スタックマッチではこれにリレーでアンテナ切り替えを加えて色々な組み合わせで切り替えることができるようになっています。WX0Bの従来の商品はダイオードで作ったマトリックスをリモートスイッチで切り替えるというものですが、最近プッシュボタン式でそれぞれの組み合わせへクイック切り替えできるスイッチボックスもでてきています。K1TTTのところでは自作のものを商品化される前から使っていました。

エンジニア系ではない私には理論的解説はこの程度の説明が精一杯ですが、実際にこのデバイスの中身を見てみるとそれほど複雑ではないというの第一印象で自作ができないのかなと思いました。それで調べてみるといくつか参考になるサイトがありました。
まず、SM2WMVがStackerというスタックマッチ用のPCB基板を販売しています。円安になってしまった現在ではあまり妙味はありませんが、価格は40ユーロです。なお、キットではありませんのでコアやリレーなどの部品は別途調達する必要があります。
なお、SM2WMVはこの基板の他に6ポートのアンテナ切り替え器やSO2Rなどのコンテストで必需品のいわゆる6パック、4Qアンテナ用ボード、高出力向けコネクタ対応バージョンなども配布しています。
実際にこの基板を使った作成記事としてはDH1TWのものが写真など参考になります。You Tubeにもいくつかこの基板を使って作ったものをテストしているものがあります。
コアとしてはアミドンのFT240-61が推奨されており、巻き数が多いとローバンド向け、減らすとハイバンド向けとなるようで、また高出力の場合はコアを重ねることで対応できるようですがコア1つでもOM-3500クラスのリーガルパワー以上のクラスのリニアでも十分とのことです。
日本までの郵送料を考えるとどうなるかわかりませんが、当地ではここでコアを入手するのが一番安そうです。
この他に参考になるものとしてはコンテスト好きが高じてモロッコにスーパーステーションを構築したW7EJ がシャックの装置の回路図を公表しており、こちらに切り替え器の回路図もありますので参考になります。かれは基板を使わずに自作しており、写真を見ると基板無しでもいけそうでこれならコストを抑えて自作が可能そうです。












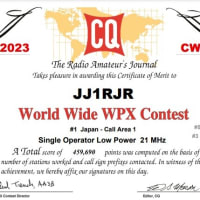












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます