河北新報より転載
仮設生活 心身とも限界/(3)避難長期化/福島知事選「復興の論点」

<「心折れたんだ」>
「散歩に行く」とうそをついた。玄関先で言い放った最後の声は、普段よりも大きかった。
「仮設はもう嫌だ」
福島第1原発事故で避難し、いわき市内の仮設住宅に住んでいた福島県楢葉町の女性(87)が9月2日、近くの森の崖の斜面で、首に蔓(つる)を巻き付けて自殺した。
2011年8月末に入居後、軽度のアルツハイマー病と診断された。ことし4月、夫(94)=当時=が仮設住宅で転倒し亡くなった後は物忘れの症状が悪化していた。
「みんなの名前が思い出せない」。8月30日、病院のリハビリから帰宅した際、同居する長男(64)にこぼした。
翌31日、突然友人や親戚に電話をかけ始めた。「今まで友だちでいてくれてありがとう」。別れのあいさつだった。
長男は「母は将来寝たきりになって、私に迷惑を掛けてはいけないと考えたのかもしれない。3年半は高齢の母には長すぎた。心が折れちまったんだ」と声を詰まらせた。
楢葉町は大半が避難指示区域。町は来春以降に帰町を目指す方針。除染は計画上終了したが、住民の放射能への不安は根強い。
仮設住宅の自治会長は「先が見通せない。福島には復興という道はあっても障害物が多すぎる」と厳しい認識を示す。
<遅れた整備計画>
仮設住宅の出口となる災害公営住宅の整備完了時期も、福島では見通しが定まらない。復興庁がまとめた被災3県の整備状況(14年6月末)によると、岩手では全戸の完成時期が確定、宮城も整備の見通しが立った。一方、福島は原発避難者向けの4890戸のうち、3466戸(70.8%)が決まっていない。
原発被災者向けの住宅を主体的に整備する福島県が、第1次整備計画を示したのは13年6月と遅かった。初めての県営住宅(計40戸)は来月、郡山市内に完成する。
整備の工程表が固まらない理由について県建築住宅課の担当者は「原発事故の避難区域に建設できないため、避難先の自治体内に大規模な土地が必要。用地は選定しているが、交渉に時間を要している」と説明する。
避難指示区域の同県富岡町から郡山市の仮設住宅に1人で暮らす村口和歌子さん(82)は同市内に来年1月完成する公営住宅に申し込んだが、7月に落選通知が届いた。
富岡町の帰還検討時期は17年4月以降。自宅は居住制限区域のため、戻れる時期の見通しは立たない。別の場所で自宅再建可能な年齢ではない。
長引く仮設住宅の暮らし。健康診断で身長が数センチ縮んだ。年を追うごとに腰の痛みが増す。人相が変わったと周囲から言われて、鏡を見る。この先の人生を考える。
村口さんが入居を望む公営住宅の完成は来年秋だ。「こんな仮住まいの暮らしは情けなくて仕方ない。死ぬ前に富岡の復興の姿を見たい。いつになったら出られるのか」
福島では、2万5000人以上の避難者が狭い室内で4年目の冬を越す。
[震災関連死]復興庁のまとめでは、14年3月末現在、岩手、宮城、福島の被災3県の震災関連死者数は計3034人。うち福島が1704人(56.1%)と過半数を占める。東日本大震災関連の自殺者数は内閣府自殺対策推進室の統計によると、8月現在、福島が56人と最多。岩手は31人、宮城は37人。
2014年10月06日月曜日










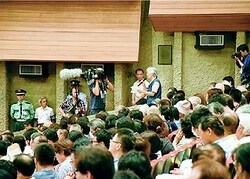


 不在者投票の請求書類を眺める三原さん。記入欄はまだ埋まっていない=5日、千葉県柏市
不在者投票の請求書類を眺める三原さん。記入欄はまだ埋まっていない=5日、千葉県柏市
