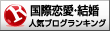Del Parson © Intellectual Reserve, Inc.
The End of the Worldと言う歌がある。1962年にアメリカのスキータ・デイヴィスがヒットさせた。邦題は、「世界の果てまで」。この曲は、作詞家のシルヴィア・デイヴィスが、かつての失恋の痛手を書いたものだが、14歳で父親を亡くした彼女はその悲しみをこの曲の基にしたとも言われる。この歌は、その後多くの歌手が歌っている。2004年にスキーター・デイヴィスが亡くなった時、葬儀で、彼女のこの歌が流された。「あなたの愛を失ってしまったというのに、何故日は昇り、波は打ち返し、鳥はさえずり、星は輝くのだろうか?朝目覚めると、何故何も変わっていないのだろう、私はあなたの愛を失ったというのに。」というような歌詞内容である。人を愛すると、世界はその人になるが、その人が去っても、世界は何ら変わらない。でも、本当に?
先日、詩人で編集者でもあるSomewhere on a Highwayと言う詩集を出版したマリサ・ドネリー(Marisa Donnelly)のエッセイを読んだ。そこには、人間は確かに小さな存在で、飛び立つ飛行機に乗って見える人間が、だんだん小さくなり、やがて消えてしまう小さな存在だが、しかし小さな存在だからと言って、決して重要ではないということではなく、一人一人の人間は無意味な存在ではない、というようなことが書かれている。これを読んでいて、ふとThe End of the World(実際には人間が小さいとは正反対の意図があるとしても)を思い出したあたり、私も古いものである。マリサ・ドネリーは、エッセイでこう言う。

goodreads.com
あなたが愛する人を失っても、あなたの心が壊れてしまっても、寂しくても、疲れていても、恐れていても、悲しくとも、そのために世界が止まるわけではありません。しかし、あなたは自分がちっぽけな存在だから、世界が止まるはずはないと確信しています。。。多分たった今そうした荒廃した気持ちを持っているかもしれません。あなたの周りのすべてが崩れ落ちたように見え、誰もあなたの言うことに耳を傾けない、と思うかもしれません。あなたは最初に覚えていなければならないのは、世界はあなたに何一つ貸しがなく、あなたが必要な愛や支持を常に提供してもいないのを知らなければなりません。けれど、それは、あなたの感情が重要ではないということはないのです。
。。。あなたが焦点を合わせるとき、あなたは一人一人が極めて重要であることに気付きますー母親(父親然り)、娘、息子、兄弟姉妹、いとこ、学校の先生、医者、ビジネスマン、郵便配達員、秘書など。 一人ひとりが直接自分の周りの人にどのように影響を与えるのか、一人ひとりが目的、役割、義務、重要性をどのように持っているかを見てください。
あなたが焦点を当てるとき、ひとりひとりが実際にはとても大きく、とても有能で、私たちの生活に、人生に、変化をもたらしさえできるのを見ます。 そして、ひとりひとりが小さな声で話しても、それは他の人々の声と混ざり合って、輝かしい統一された音を作り出します。
そしてそれはすべてたった一人から始まります。。。あなたは小さな存在かもしれませんが、小さな存在は弱いというわけではありません。小さな存在は非重要ではありません。小さな存在は無駄に等しいのではありません。だから、前進し、口を開き、声を上げ、真実を話し、感情を持つことです。。。たった一人でそうする必要はありません。あなたは大切で、そして愛されているのです。
たとえ人ひとり壮大な宇宙にあって点よりも小さな存在であるいはまったく目に見えないとしても、その存在は決して無意味ではなく、その大切は計り知れない。壮大な背景においても、人間を見ることのできる存在がある。私の脳裏に浮かんだのは、ルカ書第7章の話である。ナインという町で、ある寡婦(やもめ)のたった一人の息子が、亡くなり、その遺体を運んでいる葬列に通りがかったイエスが、その母親の寡婦に深い同情を表わし、彼女の状況がどれほどのものであるかを理解していた。その時代、その土地で、その文化で、女一人の経済状態や暮らしを考えると、頼りだった一人息子をも亡くしてその未亡人がどれほどの絶望を感じていたか想像がつく。やつれ果てた彼女がどれだけ神を乞い求め、祈り続けたか、涙の跡が残る頬を目にしたら、その苦しみはわかる。その苦しみから彼女を救うために、イエスはそこで出会ったばかりの彼女の息子を甦らせた。その奇跡もさながら、私が驚くのは、イエスが見ず知らず(しかも只の点に過ぎなかったろう存在)だった彼女を誰よりも深く理解していたことである。社会の中でおそらく最も小さき存在であったろう寡婦にさえ、イエスは深く同情し、躊躇することなく手を差し伸べられ、窮地にあった彼女を救ったのだ。
力がなく、すべての面において、自分は劣ると思う小さき存在を、イエスはお見過ごしにはならず、手を差し伸べるというその確信をここで見る。

ブリガム・ヤング大学古代聖典学准教授のケイス・J・ウィルソン氏は、次のようにこの聖書の話について語る:「この話を思うと,わたしたちは主にとって大切な存在であり,主がわたしたちをお忘れになることは決してないということが,改めて分かります。このことを忘れることはできません。」(Ensign, April 2019)
意気消沈し、悲しみや絶望に打ちひしがれようとも、助けを求めるならば、イエスはすぐそこにいらっしゃり、往々にしてその助けは他の人を通してやってくるものである。そのことを忘れたくない。