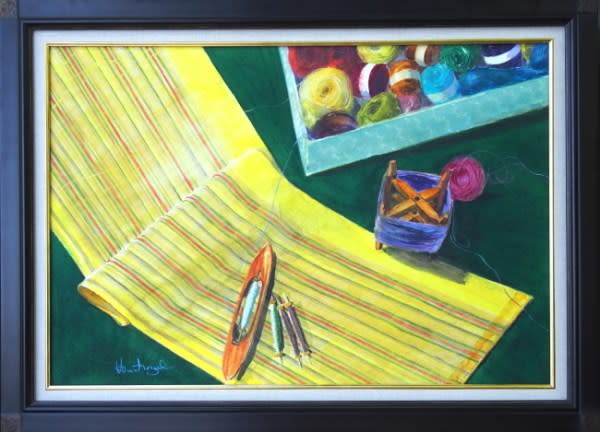ときどき通っている教会は、クリスマスの唄が聞こえ始めるこの頃になると、毎年「もなかバザー」を行う。バザーという単語はummage sale(米国)、jumble bazaar(英国)と言って、(家の不要物の)かき回しセールや、寄せ集め市場のイメージであるが、この「もなかバザー」は教会員らが実際に材料を仕入れて餡(あん)を作り、皮づめまでの手間をかけて売り、資金集めの一助にするという結構大変な苦労である。この教会は創立127年の小さな教会だが、「もなかバザー」は50年前から続けているとのこと。私は、この「もなか」を我が家で採れる橙(だいだい)と合わせて、年末の元気便り・プレゼントにしている。

2017.11.27撮影 「橙」
今年はしっかり実を付けてくれて、この籠に二杯採れた。酢醤油には適しており、酸っぱさはもちろんだが少しの苦味が良い味を造ってくれる。横に写っている倒れた黄色の葉は「ギボウシ」だ。多年草で夏の花、それに日陰を好むので、ずぼらな私向きの手のかからない花である。近寄って見下ろすと、ちょっとした抽象画だ。

2017.11.27撮影 「ギボウシ」
面白くなって、手入れをしない我が家の庭を歩いてみると、次々と目に留まるものがある。

2017.11.27撮影 「ミツバ」
まだ小さな葉(3~4cm)をしているが、見事に群生している。お吸い物に浮かせたり、サラダに混ぜたり。

2017.11.27撮影 「ツワブキ」
半分は花の見ごろを過ぎていたが、まだまだ艶のある葉をしていて、花びらの黄色が映える。

2017.11.27撮影 「ツタ」
詳細な名前は分からないが、緑と赤紫の補色が綺麗だ。ベースの石の色もいい。

2017.11.27撮影 「ジネンジョ」
自然薯のことは、子供の頃、山を持った農家に居候していたのでよく知っている。自然薯の根は栄養豊富で美味しい。細長くハート型をした葉は秋の終わりには黄色になって枯れ落ち、冬には蔓も朽ち果てる。土中の根は、新たな芽を出すためにエネルギーを消耗してしぼんで痩せるが、夏には新たな栄養接種が勝って肥大する。それを繰り返して5年も経つと1mくらいになり、旬の食料になる。ムガゴは実、鼻にくっつけて遊ぶ三つの陵は種子を内包している。この5年も待つところがポイントで、素人は蔓があると根を掘り出してしまい、山を荒らす奴だとさげすまされる。
あるがままの我が家の植物たちは、こうして季節に従った暮らしをしている。