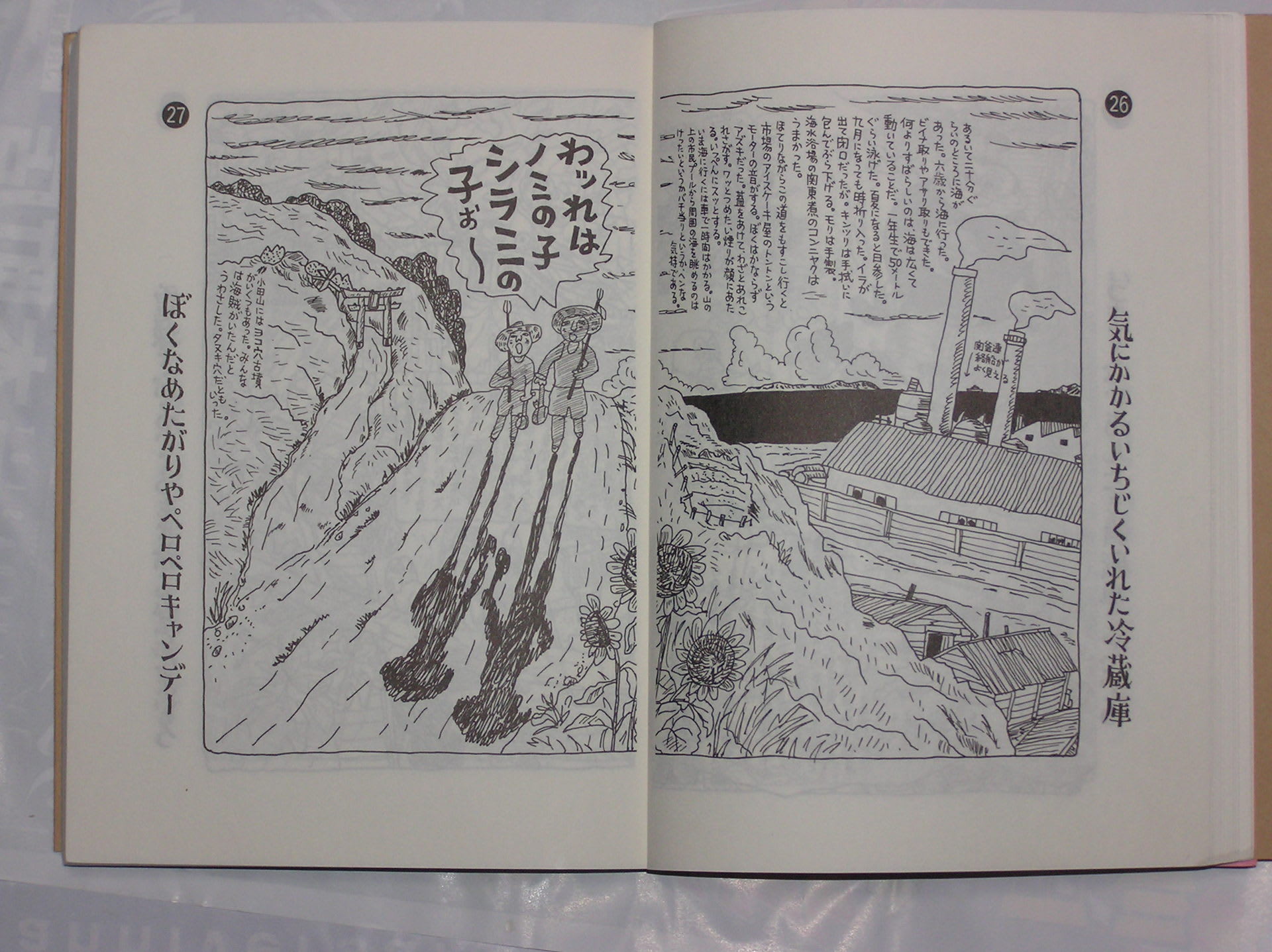若松高校同窓会総合文化展については(その35・36)に載せましたが、落としていたことがありましたので追補します。
「若松高校同窓会の隆盛は彼の手腕に負うところが大きい」と光安鐵男に言わしめるその人は、喜連川修さんです。酸素溶材会社を経営している喜連川さんは、取引先で懇意な谷川義和さん(げってんその9に登場)に絵の手ほどきを受けており、光安鐵男とは絵で接点ありました。また、若松高校同窓会総会の世話役が持ち回りで光安鐵男に回ってきたときに、書記役をしている喜連川さんの采配や飛躍的な発案にはしばしば感心させられていました。若松高校同窓会総合文化展の発案も実は喜連川さんでした。寄付金を集める仕掛けやその成果は喜連川さんのアイデアが満載です。OBでプロの画家の作品を集めてチャリティーを企画したのもそうです。しかし、喜連川さんは1985年の同窓会館完成と同時期に同窓会の書記を辞め、その年の第7回を以って総合文化展も宙に浮いてしまいました。同窓会館の竣工式では「寂稜」と銘々したお酒を蔵元に造らせ、その売上げから大パーティーの費用を捻出しました。喜連川さんのご家族の方はお酒の箱詰めに夜を徹した想い出があると話して居られました。
喜連川さんは地域を活性化させる名人でした。
・ 料亭「金鍋」で開かれる「若松異業種情報交流会」では「若松酒肴の会」をつくり、当時脚光を浴びていた吟醸酒をたしなむため西日本の蔵元を巡るツアー、遂には「若松忠臣蔵」に発展
・地ビール造りを発想したは水が大事と水探し、とうとう屋久島の水にたどり着く
・市の後押しもあって、冬の風祭りを発案。子供達に凧作りを教え、凧あげ大会。場所は響灘の埋立地で、グリーンパークで、広島で、遂には中国は万里の長城で河童の凧を揚げる
・自治会長時代は地域の祭りを盛り立て、五平太ばやしを推進。市の後押しする「わっしょい百万夏祭り」には地域独特の祭りを集合させ、五平太ばやしもこれに参戦させる。地元若松では「あじさい祭り」や、「まつり深町」を推進。町内の盆踊りでは地元に伝承されている伝統踊りとコラボレイトさせる。
・地元出身のバイオリニスト・川口エリサを後押しして後援会事務局の看板をあげ、大いに盛り立てた。川口エリサさんも感謝の意を表して、喜連川さんの可愛がっている地元の子供五平太ばやしの一団をご自分がコンサートマスターを務めておられるベルギー王立オーケストラの演奏会へ招待することに。喜連川さんは考えました。ベルギーで五平太ばやしを演奏しようと。
残念なことに、このベルギー五平太が実現する2000年に仕掛け人喜連川は体調の異変を感じ、ご本人のベルギー行きは実現せず、突如人生を閉じることになりました。
祭りといえば一致団結して自分の持ち場をこなす若松12区は今も健在です。奥様は行列のできる「男の料理」を主宰し、娘さんは近隣での働く人たちの胃袋を満たし、娘婿は喜連川さんが飛び歩いている間に酸素溶材会社を営むことを鍛えられていました。げってんさんも喜連川修さんとは波長の合うところが少なからずあったにちがいありません。
「若松高校同窓会の隆盛は彼の手腕に負うところが大きい」と光安鐵男に言わしめるその人は、喜連川修さんです。酸素溶材会社を経営している喜連川さんは、取引先で懇意な谷川義和さん(げってんその9に登場)に絵の手ほどきを受けており、光安鐵男とは絵で接点ありました。また、若松高校同窓会総会の世話役が持ち回りで光安鐵男に回ってきたときに、書記役をしている喜連川さんの采配や飛躍的な発案にはしばしば感心させられていました。若松高校同窓会総合文化展の発案も実は喜連川さんでした。寄付金を集める仕掛けやその成果は喜連川さんのアイデアが満載です。OBでプロの画家の作品を集めてチャリティーを企画したのもそうです。しかし、喜連川さんは1985年の同窓会館完成と同時期に同窓会の書記を辞め、その年の第7回を以って総合文化展も宙に浮いてしまいました。同窓会館の竣工式では「寂稜」と銘々したお酒を蔵元に造らせ、その売上げから大パーティーの費用を捻出しました。喜連川さんのご家族の方はお酒の箱詰めに夜を徹した想い出があると話して居られました。
喜連川さんは地域を活性化させる名人でした。
・ 料亭「金鍋」で開かれる「若松異業種情報交流会」では「若松酒肴の会」をつくり、当時脚光を浴びていた吟醸酒をたしなむため西日本の蔵元を巡るツアー、遂には「若松忠臣蔵」に発展
・地ビール造りを発想したは水が大事と水探し、とうとう屋久島の水にたどり着く
・市の後押しもあって、冬の風祭りを発案。子供達に凧作りを教え、凧あげ大会。場所は響灘の埋立地で、グリーンパークで、広島で、遂には中国は万里の長城で河童の凧を揚げる
・自治会長時代は地域の祭りを盛り立て、五平太ばやしを推進。市の後押しする「わっしょい百万夏祭り」には地域独特の祭りを集合させ、五平太ばやしもこれに参戦させる。地元若松では「あじさい祭り」や、「まつり深町」を推進。町内の盆踊りでは地元に伝承されている伝統踊りとコラボレイトさせる。
・地元出身のバイオリニスト・川口エリサを後押しして後援会事務局の看板をあげ、大いに盛り立てた。川口エリサさんも感謝の意を表して、喜連川さんの可愛がっている地元の子供五平太ばやしの一団をご自分がコンサートマスターを務めておられるベルギー王立オーケストラの演奏会へ招待することに。喜連川さんは考えました。ベルギーで五平太ばやしを演奏しようと。
残念なことに、このベルギー五平太が実現する2000年に仕掛け人喜連川は体調の異変を感じ、ご本人のベルギー行きは実現せず、突如人生を閉じることになりました。
祭りといえば一致団結して自分の持ち場をこなす若松12区は今も健在です。奥様は行列のできる「男の料理」を主宰し、娘さんは近隣での働く人たちの胃袋を満たし、娘婿は喜連川さんが飛び歩いている間に酸素溶材会社を営むことを鍛えられていました。げってんさんも喜連川修さんとは波長の合うところが少なからずあったにちがいありません。