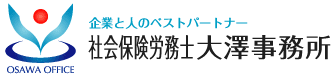人事パーソンのための産前産後休暇の与え方
従業員さんから、「産前産後休暇」を取りたいと申出があった場合、
会社は、どのように産前産後休暇を与えたらいいのでしょうか。
●産前産後休暇の与え方
産前産後休暇は、労働基準法で次のように定められています。
「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に
出産する予定の女性が請求した場合においては、その者を就業させては
ならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、
その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、
差支えない。・・・」(労働基準法65条第1項・第2項)
「産前6週間は自然の分娩予定日を基準として計算し、産後8週間の期間は
現実の出産日(又は人工流産を行った日)を基準として計算する。」
(S26.4.2婦発113号)
●産前休暇とは
産前休暇は、労働者が「請求した場合には」与えなければなりません。
産前休暇はいつから与えなければならないのでしょうか。上記によれば、
出産予定日の6週間(42日)前からです。この場合、出産予定日は産前休暇に含まれます。
例えば、出産予定日が5月12日の場合、産前休暇の開始日は4月1日となります。
●「出産」とは
労働基準法で「出産」とは、妊娠4か月(4×28日=85日)以上の分娩とし、
生産のみならず、死産(人工妊娠中絶は含まれる。)も含みます(S23.12.23基発1885号)。
●実務上の産前休暇の与え方
実務上は、「出産予定日」から起算して42日前から休み始め、
「出産日」までが産前休暇です。
ところで、出産が予定日より早まったり遅れたりする場合があります。
その場合、労基法上の産前休暇はどうなるのでしょうか。
産前休暇の原則は、出産日以前42日間ですが、
「出産日」が出産予定日より早まったら、その分産前休暇は短くなり、
反対に「出産日」が遅れたら、その分、産前休暇は長くなります。
例をみてみましょう。
・出産予定日:5月12日 出産日:5月12日 産前休暇:4月1日~5月12日(42日間)
・出産予定日:5月12日 出産日:5月10日 産前休暇:4月1日~5月10日(40日間)
・出産予定日:5月12日 出産日:5月14日 産前休暇:4月1日~5月14日(44日間)
●産後休暇
産後休暇は、原則として出産日後8週間(56日間)です。
こちらは、出産日を含まず、その翌日から起算します。
・出産予定日:5月12日 出産日:5月12日 産後休暇:5月13日~7月7日(56日間)
・出産予定日:5月12日 出産日:5月10日 産後休暇:5月11日~7月5日(56日間)
・出産予定日:5月12日 出産日:5月14日 産後休暇:5月15日~7月9日(56日間)
ただし、労働者が希望し、医師が支障がないと認める業務に就かせる場合は、
産後6週間(42日)後から就労させても差し支えありません。こういう事例は滅多に
ないと思いますが。
●注意点
・女性の場合は、労基法の産前産後休暇が終わった翌日から育児休業が始まることになります。
・産前産後休暇中の賃金の支払いにつては、労使の自由です。
・産前産後休暇期間中とその後30日間は解雇できません(労基法19条1項)。
・産前産後休暇期間は、平成26年4月1日より申出により労使共に社会保険料が免除となります。
・健康保険法の「出産手当金」の支給対象期間は、「出産日」以前42日間となります。
労働基準法65条の産前産後休暇の期間は、他の制度にも影響を与える
大切な期間といえましょう。
次回は、妊産婦の健康保持について述べてみましょう。
続く。
 にほんブログ村
にほんブログ村
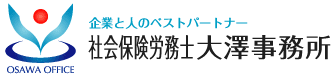
従業員さんから、「産前産後休暇」を取りたいと申出があった場合、
会社は、どのように産前産後休暇を与えたらいいのでしょうか。
●産前産後休暇の与え方
産前産後休暇は、労働基準法で次のように定められています。
「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に
出産する予定の女性が請求した場合においては、その者を就業させては
ならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、
その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、
差支えない。・・・」(労働基準法65条第1項・第2項)
「産前6週間は自然の分娩予定日を基準として計算し、産後8週間の期間は
現実の出産日(又は人工流産を行った日)を基準として計算する。」
(S26.4.2婦発113号)
●産前休暇とは
産前休暇は、労働者が「請求した場合には」与えなければなりません。
産前休暇はいつから与えなければならないのでしょうか。上記によれば、
出産予定日の6週間(42日)前からです。この場合、出産予定日は産前休暇に含まれます。
例えば、出産予定日が5月12日の場合、産前休暇の開始日は4月1日となります。
●「出産」とは
労働基準法で「出産」とは、妊娠4か月(4×28日=85日)以上の分娩とし、
生産のみならず、死産(人工妊娠中絶は含まれる。)も含みます(S23.12.23基発1885号)。
●実務上の産前休暇の与え方
実務上は、「出産予定日」から起算して42日前から休み始め、
「出産日」までが産前休暇です。
ところで、出産が予定日より早まったり遅れたりする場合があります。
その場合、労基法上の産前休暇はどうなるのでしょうか。
産前休暇の原則は、出産日以前42日間ですが、
「出産日」が出産予定日より早まったら、その分産前休暇は短くなり、
反対に「出産日」が遅れたら、その分、産前休暇は長くなります。
例をみてみましょう。
・出産予定日:5月12日 出産日:5月12日 産前休暇:4月1日~5月12日(42日間)
・出産予定日:5月12日 出産日:5月10日 産前休暇:4月1日~5月10日(40日間)
・出産予定日:5月12日 出産日:5月14日 産前休暇:4月1日~5月14日(44日間)
●産後休暇
産後休暇は、原則として出産日後8週間(56日間)です。
こちらは、出産日を含まず、その翌日から起算します。
・出産予定日:5月12日 出産日:5月12日 産後休暇:5月13日~7月7日(56日間)
・出産予定日:5月12日 出産日:5月10日 産後休暇:5月11日~7月5日(56日間)
・出産予定日:5月12日 出産日:5月14日 産後休暇:5月15日~7月9日(56日間)
ただし、労働者が希望し、医師が支障がないと認める業務に就かせる場合は、
産後6週間(42日)後から就労させても差し支えありません。こういう事例は滅多に
ないと思いますが。
●注意点
・女性の場合は、労基法の産前産後休暇が終わった翌日から育児休業が始まることになります。
・産前産後休暇中の賃金の支払いにつては、労使の自由です。
・産前産後休暇期間中とその後30日間は解雇できません(労基法19条1項)。
・産前産後休暇期間は、平成26年4月1日より申出により労使共に社会保険料が免除となります。
・健康保険法の「出産手当金」の支給対象期間は、「出産日」以前42日間となります。
労働基準法65条の産前産後休暇の期間は、他の制度にも影響を与える
大切な期間といえましょう。
次回は、妊産婦の健康保持について述べてみましょう。
続く。