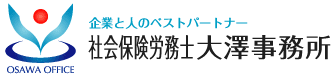またも育児休業給付が引き上げられる可能性とか……。
制度が出来た当初の支給率は休業前賃金の25%、次に40%に上がり、現在は50%。
休んでて50%もらえるというのは、かなりいい率です。
今度の支給率の案は、育休最初の6か月間を67%にするというもの。
(厚生労働省 第93回雇用保険部会)
この67%というのは、健康保険から支給される「出産手当金」の支給率を
踏襲したものといいます。
育児休業給付は、他の雇用保険の手当(失業給付等)から比べても
ダントツの多さです。
厚生労働省の発表によれば、平成24年の育児休業給付の平均月額は111,932円。
これを原則として6か月分もらえるのですから、大盤振る舞いです。
仕事をしないで家でゆっくりしていて、11万からのお金がもらえるのですから、
へたなパートに出るよりもずっといいですね。
その上、社会保険料はタダ。子ども手当ももらえる。非課税。
気持ちは分かりますが、雇用する側の企業はどうでしょう。
子供を産んでない人はどうでしょう。
企業には、せいぜい、育休期間中の社会保険料が免除になるくらい。
一定の期間欠員が生じたら、それを何らかの手段で穴埋めしなければなりません。
或いは他の従業員にしわ寄せがいくかもしれません。
更に、会社は、2か月に1回、職安に育児休業給付の申請に行っています。
出産・子育てと縁のない方もいらしゃいます。
雇用保険料は、被保険者と事業主とで折半で負担していますので、
そういう方たちや企業も育児休業給付の一部を負担していることになります。
もらえる人ともらえない人の「格差」が広がるわけですね、
保護されるのは、育休取得者のみ。
企業などにも奨励金などの何らかの手当をすべきではないでしょうか。
中小企業では、公務員や大企業のように
「はい。どうぞ、どんどん育休取ってください」
とまでは言い難い面もあります。
当事務所で手続きした育休取得者の方々は、かなりの率で、育休が
終わると辞めてしまいます。厚生労働省がその数字を発表しないので
そのような離職者がどのくらいいるか分かりませんが。
受給要件の面では、疾病、他の子の出産や育休などで、欠勤が多い人の
賃金登録の場合もありますので、結構、最初の書類作成が複雑な場合があります。
当事務所では、受給要件をとことん追求し、もらえるかもらえないか
微妙な事例でも、最大限の努力をして職安に主張して手続しているつもりです。
そんな私でも、今以上の給付率アップが必要性があるのか、とても疑問に
思うのです。
 にほんブログ村
にほんブログ村
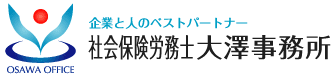
制度が出来た当初の支給率は休業前賃金の25%、次に40%に上がり、現在は50%。
休んでて50%もらえるというのは、かなりいい率です。
今度の支給率の案は、育休最初の6か月間を67%にするというもの。
(厚生労働省 第93回雇用保険部会)
この67%というのは、健康保険から支給される「出産手当金」の支給率を
踏襲したものといいます。
育児休業給付は、他の雇用保険の手当(失業給付等)から比べても
ダントツの多さです。
厚生労働省の発表によれば、平成24年の育児休業給付の平均月額は111,932円。
これを原則として6か月分もらえるのですから、大盤振る舞いです。
仕事をしないで家でゆっくりしていて、11万からのお金がもらえるのですから、
へたなパートに出るよりもずっといいですね。
その上、社会保険料はタダ。子ども手当ももらえる。非課税。
気持ちは分かりますが、雇用する側の企業はどうでしょう。
子供を産んでない人はどうでしょう。
企業には、せいぜい、育休期間中の社会保険料が免除になるくらい。
一定の期間欠員が生じたら、それを何らかの手段で穴埋めしなければなりません。
或いは他の従業員にしわ寄せがいくかもしれません。
更に、会社は、2か月に1回、職安に育児休業給付の申請に行っています。
出産・子育てと縁のない方もいらしゃいます。
雇用保険料は、被保険者と事業主とで折半で負担していますので、
そういう方たちや企業も育児休業給付の一部を負担していることになります。
もらえる人ともらえない人の「格差」が広がるわけですね、
保護されるのは、育休取得者のみ。
企業などにも奨励金などの何らかの手当をすべきではないでしょうか。
中小企業では、公務員や大企業のように
「はい。どうぞ、どんどん育休取ってください」
とまでは言い難い面もあります。
当事務所で手続きした育休取得者の方々は、かなりの率で、育休が
終わると辞めてしまいます。厚生労働省がその数字を発表しないので
そのような離職者がどのくらいいるか分かりませんが。
受給要件の面では、疾病、他の子の出産や育休などで、欠勤が多い人の
賃金登録の場合もありますので、結構、最初の書類作成が複雑な場合があります。
当事務所では、受給要件をとことん追求し、もらえるかもらえないか
微妙な事例でも、最大限の努力をして職安に主張して手続しているつもりです。
そんな私でも、今以上の給付率アップが必要性があるのか、とても疑問に
思うのです。