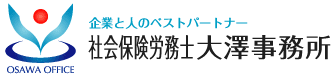今の日本では、労使紛争の解決手段は多種多様にあります。
どれにしようか……迷うくらいです。
少し前までは、せいぜい労基署へ駆け込む、民事調停、裁判くらいでしたが、
現在は、加えて、労働局のあっせん、ADR、労働審判と、
その種類も増えてきました。
使用者側も枕を高くしていられません。
労使紛争が起きないよう身構える風潮が強くなっているように感じます。
さて、労働基準法違反関係の駆け込み寺は労働基準監督署等といえますが、
労基法違反事案ではない解雇、出向、賃下げ、降格、配置転換などは、
民事上の紛争になりますので、
民事調停、労働局あっせん、ADR、労働審判、裁判などの諸制度を
利用することになります。
大抵は労働者側からの「訴え」が多いわけですから、労働者側が
上記のどの制度を使って訴えてくるかで、使用者側の対応も変わってきます。
使用者側ももちろん上記制度を利用できますが、費用、簡便性などを
考えれば、労働局のあっせん、民事調停がお薦めといえましょうか。
本日は、上記の中から「労働局のあっせん」に焦点を絞ってご説明しましょう。
平成13年に「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」ができまして、
都道府県労働局で、いろいろ指導・助言をしても労使紛争が解決しなかった場合、
紛争当事者の一方又は双方の申し立てにより、労働局内に設置した
「紛争調整委員会」の「あっせん」により解決するという制度が設けられました。
「あっせん」は、大抵の場合、労働者からの申し立てが多いのですが、
申し立てがありますと、労働局から使用者側に
どうですか、このあっせんを「受けますか?」との通知が出されます。
この紛争調整委員会のあっせんを使用者が受けるかどうかは、自由です。
断っても何らの問題がありません。
これは、労働審判、民事調停、裁判などと大きく異なる点です。
あっせんは、いわば公的な和解交渉になります。
実際には、紛争調停委員1名が、労働者、使用者双方から話をきいて、
和解案等を提示していくことになります。「金銭解決」です。
双方の話し合いがまとまれば、あっせんは終了し、合意内容に基づく
文書が作成されます。
双方の話し合いがまとまらず、あっせんが打ち切られる場合もあります。
その場合は、申し立てた側がその他の手段を検討することになります。
労働審判か、民事調停か、裁判か……。
あっせんで和解が成立し、使用者側がいくばくかの金銭を支払うことで
合意した場合は、定められた期日までに支払うことになりますが、
労働局のあっせんにおいては、その債務は、
裁判などの判決のように、「債務名義」にはなりません。
「かくかくしかじか支払うことで合意した」という文書があっても、
もし使用者側が支払わなかった場合に、裁判の判決のように、
労働者側は、「強制執行」の申し立てをすることができない、という
欠点を持っています。
あっせんでは、「債務名義」が取れないのです。
裁判、民事調停、労働審判では、当然ですが「債務名義」になります。
ただし、あっせんの長所は、
・無料であること
・手間暇がかからないことなど
・自分でできること(代理人を選ばなくてもできる)
など、たとえ資力のない労働者でも申し立てをしやすいことにあります。
当事務所では、顧問先でそのような事案があった発生した場合には、
あっせんに出席するかどうか、金銭解決になるが支払う意志があるのか
などを確認し、アドバイスしています。
なお、申し立てた側の方ですが、
労働局でのあっせんの話し合いがまとまらず、打ち切られたときは、
時効の中断に関しては、あっせんの打ち切りの通知を受けた日
から30日以内に訴えを提起すれば、
あっせんの申請時に訴えの提起があったとものとみなされます。
一定の条件で、時効の中断があるのですね。
 にほんブログ村
にほんブログ村
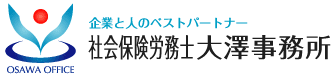
どれにしようか……迷うくらいです。
少し前までは、せいぜい労基署へ駆け込む、民事調停、裁判くらいでしたが、
現在は、加えて、労働局のあっせん、ADR、労働審判と、
その種類も増えてきました。
使用者側も枕を高くしていられません。
労使紛争が起きないよう身構える風潮が強くなっているように感じます。
さて、労働基準法違反関係の駆け込み寺は労働基準監督署等といえますが、
労基法違反事案ではない解雇、出向、賃下げ、降格、配置転換などは、
民事上の紛争になりますので、
民事調停、労働局あっせん、ADR、労働審判、裁判などの諸制度を
利用することになります。
大抵は労働者側からの「訴え」が多いわけですから、労働者側が
上記のどの制度を使って訴えてくるかで、使用者側の対応も変わってきます。
使用者側ももちろん上記制度を利用できますが、費用、簡便性などを
考えれば、労働局のあっせん、民事調停がお薦めといえましょうか。
本日は、上記の中から「労働局のあっせん」に焦点を絞ってご説明しましょう。
平成13年に「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」ができまして、
都道府県労働局で、いろいろ指導・助言をしても労使紛争が解決しなかった場合、
紛争当事者の一方又は双方の申し立てにより、労働局内に設置した
「紛争調整委員会」の「あっせん」により解決するという制度が設けられました。
「あっせん」は、大抵の場合、労働者からの申し立てが多いのですが、
申し立てがありますと、労働局から使用者側に
どうですか、このあっせんを「受けますか?」との通知が出されます。
この紛争調整委員会のあっせんを使用者が受けるかどうかは、自由です。
断っても何らの問題がありません。
これは、労働審判、民事調停、裁判などと大きく異なる点です。
あっせんは、いわば公的な和解交渉になります。
実際には、紛争調停委員1名が、労働者、使用者双方から話をきいて、
和解案等を提示していくことになります。「金銭解決」です。
双方の話し合いがまとまれば、あっせんは終了し、合意内容に基づく
文書が作成されます。
双方の話し合いがまとまらず、あっせんが打ち切られる場合もあります。
その場合は、申し立てた側がその他の手段を検討することになります。
労働審判か、民事調停か、裁判か……。
あっせんで和解が成立し、使用者側がいくばくかの金銭を支払うことで
合意した場合は、定められた期日までに支払うことになりますが、
労働局のあっせんにおいては、その債務は、
裁判などの判決のように、「債務名義」にはなりません。
「かくかくしかじか支払うことで合意した」という文書があっても、
もし使用者側が支払わなかった場合に、裁判の判決のように、
労働者側は、「強制執行」の申し立てをすることができない、という
欠点を持っています。
あっせんでは、「債務名義」が取れないのです。
裁判、民事調停、労働審判では、当然ですが「債務名義」になります。
ただし、あっせんの長所は、
・無料であること
・手間暇がかからないことなど
・自分でできること(代理人を選ばなくてもできる)
など、たとえ資力のない労働者でも申し立てをしやすいことにあります。
当事務所では、顧問先でそのような事案があった発生した場合には、
あっせんに出席するかどうか、金銭解決になるが支払う意志があるのか
などを確認し、アドバイスしています。
なお、申し立てた側の方ですが、
労働局でのあっせんの話し合いがまとまらず、打ち切られたときは、
時効の中断に関しては、あっせんの打ち切りの通知を受けた日
から30日以内に訴えを提起すれば、
あっせんの申請時に訴えの提起があったとものとみなされます。
一定の条件で、時効の中断があるのですね。