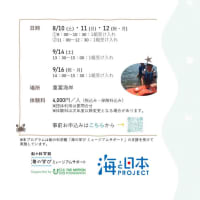昨夜は再びの大雨で、今朝もその延長の雨でした。

でも、朝の仕事をしている間にピタリとやみました。このまま梅雨にあけて欲しいなぁ。

なおちゅん先生のブログに惹かれて、エアーズの『子どもの発達と感覚統合』を読み始めました。
私にとって、初めて知った感覚統合の本は
岩永竜一郎さんの『もっと笑顔が見たいから』でした。
たしか、灰谷さんのブレインジムの講座を受けている頃で、その中で子どもが机にだらーっともたれかかって字を書くことや不器用な動きについて得た脳の知見とこの本で扱っている「固有受容覚」や「前庭覚」という内容が私の中で結びつき、読んだのを覚えています。
また、灰谷さんがブレインジム系列のその他の講座で紹介されていたので読んだ『感覚統合Q &A』という本も読んで、支援員として関わっていたお子さんたちができないことには、それぞれのお子さんが持つ体の不器用さを埋めることが必要なのだなぁと思った気がします。
これらの2冊の本やブレインジムでやったことを参考にしながら、当時の私は子どもの体や気持ちをその場凌ぎ的に表面上整えることをしていたように思います。
さて、そして感覚統合を体系化されたエアーズさんの本に今、初めて触れています。
まだまだ途中ではありますが、私が教室の親御さんからお聞きして構築された「療育」のイメージや上記二冊の本から得た体を使っての遊びより、思っている以上に細やかな感じです。
感覚統合も人類の進化の成り立ちや重力、内臓など細部を想像しながら成立しているのだなぁと感じました。
『感覚統合Q &A』でエアーズのこの本を「障害分類など古くなっているが、アメリカでは今でも再販されて読み継がれている」と紹介されていますが、それはこの本がハウツー本ではなく、原理原則を記しているからではないかなぁと途中ながら思いました。
世の東西を問わず、ハウツー本は流行り廃りがあり、原理原則の基本を押さえ、読み手に想像力を働かせてくれる本は、読み継がれるのだなぁと思うことです。
本の内容については、言葉を補いながら読み進めないと、思考がぐるぐるしてしまうような訳なので、読み込めたら紹介したいと思います。
がんばりまーす!