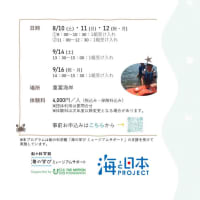本を読んでいたら、「スモールワールド」という言葉が出てきました。
なんでも、例えばですが、私が知人を通して奥田民生氏に手紙を送りたいと臨むなら、
間におおよそ6名の人を介せば、奥田民生氏に手紙が届くというもの。
こういう実験を1967年に社会心理学者のミルグラムという方が行ったそうで、
それをスモールワールドというそうです。
知りませんでした。
ネットなんぞがある今は、もっと直接で近い感じですが、
これが鬱陶しさにつながることもあります。
個人的には6人くらい介してくれたほうが、距離的には良い感じがしますねぇ。
ふと、以前受講した講座のノートを見ていたら、
「子どもの知能ー問題点~別」と書いてありました。
あ、忘れていたな、と思いノートをめくっていきました。
これは、IQが高いけれどミスが多い子は、
まぁ、IQ高いしやればできるよとうるさいことを言われずに放置されたり、
逆に、IQ高いのになにやってんだ!と叱るとかではなく、
何が、この子にミスをさせるのか、という問題点を観察して、
そこを改善していくことを教える側はしなくちゃいけないよ、ということでした。
だから、IQが低くくてミスが多い子も、
この子の力はこういう感じだね、まぁ、がんばってるよ、と放置するのでなく、
かといって、努力が足りないんだ!もっと努力をしなさい!と叱るのでもなく、
やはり、子どもの何がミスをさせるのかを見つけていくのが教える側の仕事になる訳です。
教える側に立つと、どうしても、ただただ子どもに努力を強いて、
できない責任を子どもに押し付けてしまいがちです。
自分の問題は、なかなか自分では気がつくことができません。
ましてや、生きている年数の浅い子どもたちは、自分のできる精一杯のことをしていても
それが周りの大人には評価されなかったり、同じ年くらいの子ども同士でも違和感があって避けられたりします。
子どもの精一杯は、精一杯として認めながらも。
「よしよし。がんばってるね。」で立ち止まるのではなく、
冷静に分析して、本質の問題点を見つけて解きほぐし、改善していくことが
教える側には求められている、と講座を受講したときに思ったことでした。
枝葉末節に目がいきがちです。
気をつけなくては、と思いを新たにした日でした。
なんでも、例えばですが、私が知人を通して奥田民生氏に手紙を送りたいと臨むなら、
間におおよそ6名の人を介せば、奥田民生氏に手紙が届くというもの。
こういう実験を1967年に社会心理学者のミルグラムという方が行ったそうで、
それをスモールワールドというそうです。
知りませんでした。
ネットなんぞがある今は、もっと直接で近い感じですが、
これが鬱陶しさにつながることもあります。
個人的には6人くらい介してくれたほうが、距離的には良い感じがしますねぇ。
ふと、以前受講した講座のノートを見ていたら、
「子どもの知能ー問題点~別」と書いてありました。
あ、忘れていたな、と思いノートをめくっていきました。
これは、IQが高いけれどミスが多い子は、
まぁ、IQ高いしやればできるよとうるさいことを言われずに放置されたり、
逆に、IQ高いのになにやってんだ!と叱るとかではなく、
何が、この子にミスをさせるのか、という問題点を観察して、
そこを改善していくことを教える側はしなくちゃいけないよ、ということでした。
だから、IQが低くくてミスが多い子も、
この子の力はこういう感じだね、まぁ、がんばってるよ、と放置するのでなく、
かといって、努力が足りないんだ!もっと努力をしなさい!と叱るのでもなく、
やはり、子どもの何がミスをさせるのかを見つけていくのが教える側の仕事になる訳です。
教える側に立つと、どうしても、ただただ子どもに努力を強いて、
できない責任を子どもに押し付けてしまいがちです。
自分の問題は、なかなか自分では気がつくことができません。
ましてや、生きている年数の浅い子どもたちは、自分のできる精一杯のことをしていても
それが周りの大人には評価されなかったり、同じ年くらいの子ども同士でも違和感があって避けられたりします。
子どもの精一杯は、精一杯として認めながらも。
「よしよし。がんばってるね。」で立ち止まるのではなく、
冷静に分析して、本質の問題点を見つけて解きほぐし、改善していくことが
教える側には求められている、と講座を受講したときに思ったことでした。
枝葉末節に目がいきがちです。
気をつけなくては、と思いを新たにした日でした。