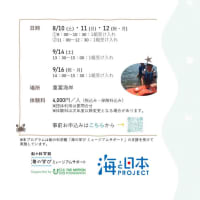今朝は満月に見送られながらの出勤。
早朝の月なのですが、まるで秋の夜更けの月の晩のようでした。
日中は暑いですが、秋の足音を感じる早朝です。
自分はどうやって漢字が書けるようになったのだろう、読めるようになったのだろう。
そんなことを考えることがあります。
高校生のときは、学校で配られる試験や入試対策の漢字については、
読みについては、ほとんど何もしなくても読めたし、
書く方も知らない漢字だけ覚えるだけで楽勝でした。
これは、本を読むことが好きだったことと、
年相応よりも自由に何でも本を読める環境に育ったことが大きかったと思います。
もう少し、学年を下げて中学生のとき。
ここでも、ほとんど、苦労したことはありませんでした。
私が漢字に苦労した記憶があるのは、
「帰る」という漢字や「必ず」という漢字などが出てきた頃で、
漢字を覚えられず、聞かれるとイライラしていたのを思い出します。
このふたつの漢字は「帰る」の方は、「ヨ」と「冖」と「巾」の組合わせが頭に入らず、
「ヨ」の部分の真ん中の棒を貫いたり、「冖」が「宀」になったりしていて、
父に何度も注意され、
「私には、そう見えるの!」とわからんちんなことを言っていた記憶があります。
「必ず」の方は、字のバランスの悪さを何度も言われて、
パーツは同じなのにどうして出来上がりが違うのか、
自分でも途方に暮れる思いでした。
子どもの頃の私は、よくある、
「絵を見て7つの間違いを探しましょう」という間違い探しが苦手でした。
どこから手をつければいいのか、何を手がかりにすればいいのかわからず、
本当に途方に暮れる気持ちでした。
そんな風だったので、正しい字と間違いの字の違いに気がつけず、
バランスのある漢字の書き方もできなかったのだと思います。
7つの間違い探しが苦もなくできるようになり、
漢字も描けるようになっていったと思います。
形を覚えるためには、どこに注目するか、何に注目するか。
そんな基準を自分の頭の中に入れることができると、
漢字の学習もうまくいくかもしれないですね。
早朝の月なのですが、まるで秋の夜更けの月の晩のようでした。
日中は暑いですが、秋の足音を感じる早朝です。
自分はどうやって漢字が書けるようになったのだろう、読めるようになったのだろう。
そんなことを考えることがあります。
高校生のときは、学校で配られる試験や入試対策の漢字については、
読みについては、ほとんど何もしなくても読めたし、
書く方も知らない漢字だけ覚えるだけで楽勝でした。
これは、本を読むことが好きだったことと、
年相応よりも自由に何でも本を読める環境に育ったことが大きかったと思います。
もう少し、学年を下げて中学生のとき。
ここでも、ほとんど、苦労したことはありませんでした。
私が漢字に苦労した記憶があるのは、
「帰る」という漢字や「必ず」という漢字などが出てきた頃で、
漢字を覚えられず、聞かれるとイライラしていたのを思い出します。
このふたつの漢字は「帰る」の方は、「ヨ」と「冖」と「巾」の組合わせが頭に入らず、
「ヨ」の部分の真ん中の棒を貫いたり、「冖」が「宀」になったりしていて、
父に何度も注意され、
「私には、そう見えるの!」とわからんちんなことを言っていた記憶があります。
「必ず」の方は、字のバランスの悪さを何度も言われて、
パーツは同じなのにどうして出来上がりが違うのか、
自分でも途方に暮れる思いでした。
子どもの頃の私は、よくある、
「絵を見て7つの間違いを探しましょう」という間違い探しが苦手でした。
どこから手をつければいいのか、何を手がかりにすればいいのかわからず、
本当に途方に暮れる気持ちでした。
そんな風だったので、正しい字と間違いの字の違いに気がつけず、
バランスのある漢字の書き方もできなかったのだと思います。
7つの間違い探しが苦もなくできるようになり、
漢字も描けるようになっていったと思います。
形を覚えるためには、どこに注目するか、何に注目するか。
そんな基準を自分の頭の中に入れることができると、
漢字の学習もうまくいくかもしれないですね。