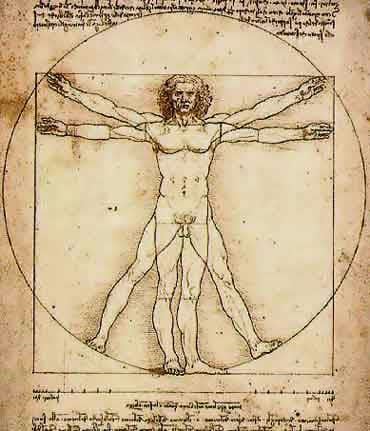ジェームズ・デューイ・ワトソン(James Dewey Watson, 1928年)は1953年にフランシス・クリック(1916年- 2004年)とともに遺伝子DNAの二重螺旋の構造を解明し、1962年にノーベル賞を受賞した。
ワトソンは、15歳で大学に入学し、20歳で遺伝学のPh.Dの学位をとり、シカゴの神童といわれていた。22歳で英国ケンブリッジに留学し、ここで知り合ったクリックと共同で遺伝子DNAの化学構造を明らかにした。
彼は科学者の伝記によく登場するような自制的なジェントルマンでは決してない。ノーベル賞受賞後に出版した『二重らせん』はベストセラーとなり、いまでも読み継がれているが、この本の中で、ロザリンド・フランクリンの撮ったX線回折写真を本人の承諾もなく見ることによって、DNAの構造を思いついた事をあからさまに述べている。
ウィキペディア(Wikipedia)の記事をみても、人種差別発言を繰り返すなど問題の多い人物である。当年92歳で存命中。
マックス・ペルツ (Max・F・Perutz)は英国でX線解析法によるヘモグロビンの研究に従事し、1962年にノーベル化学賞を受賞した有名な生化学者である。ペルツは、ワトソンが英国に留学していた1950年ごろ、キャベンディシュ研究所で分子生物の研究グループの主任をしていた。クリックは、そのペルツのグループの一員であった。ある日、ペルツの部屋にクールカットの頭で目玉の飛び出た変わった男が、挨拶もせずに入ってきて、「ここで仕事をさせてもらえませんか?」と言った。その男こそジム・ワトソンであった。
ペルツの評によると、ワトソンとクリックに共通しているのは、自分と知的に同程度の人物はめったにいないという、途方もない尊大さであったとしている。ワトソンが『二重らせん』で、ロザリンド・フランクリンを攻撃的で視野の狭いインテリ女性として描いたことに、ペルツは「才能ある女性を侮蔑したことに猛烈に腹をたてた」と述べている。

フランクリン・ポルトガルはその著、The Least Likely Man-Marshall Nirenberg and the discovery of the genetic code(「あり得ないほどすごい男・ニーレンバーグと遺伝子暗号」)で、ワトソンの異常な性向について、次のようなエピソードを伝えている。
ニーレンバーグは後で述べるが、DNAの遺伝子コードを解明し、1968年にノーベル生理学・医学賞を受賞したアメリカ人である。
『1961年10月にワトソンはニーレンバーグをマサチューセッツ工科大学での講演に招待した。それを聞きに来た聴衆で大講堂はあふれかえり、後から来た人は建物に入れなかった。
ニーレンバーグは、遺伝暗号を解明する自分の研究結果を話し始めた。ワトソンは、いつものように、傍らにニューヨークタイムズを置いて最前列に陣取っていた。ニーレンバーグの講演の半ばになると、ワトソンは急に新聞をバサバサと広げて読み出した。ニーレンバーグは、ワトソンが気に入らない話しや同意できない話しを聞いた時には、必ずこのような大人げない行動をとることを人から聞いていた。。ニーレンバーグは、この情け容赦のない無礼にたじろいで一瞬講演を中止しようかと考えたが、結局、最後までやり通した。科学者は、話しの内容が不満でも講演が終わるまで静かに聴き、その後で批判や反対の発言をするのが普通である。このワトソンのように、途中で話しの妨害を決してしないものである』(以上庵主訳)
気に入らない講演の話しを聞くと、これ見よがしに新聞を読みはじめるのが、ワトソン定番の嫌がらせであった。どうして、ワトソンはニーレンバーグの講演が気に入らなかったのだろうか。それには、遺伝子暗号の解明にかかわる当時の激しい先陣争いが背景にあった。
1953年のワトソン・クリックによるDNAの二重螺旋モデルが明らかにされて、ただちに遺伝子暗号を解読する研究が始まった。ワトソン、クリックとガモフは、この研究目的のためにRANタイクラブ(RNA Tie Club)という国際的な組織を作った。これは定員20名で、ワトソン、クリック、ガモフをはじめ、ブレナー、カルビン、シャルガフ、ステントなど錚々たる核酸の研究者が含まれていた。メンバーの一人づつに1個のアミノ酸が割当てられ、それを支配する遺伝子コードを明らかにすることが義務付けられていた。クラブ会員のネクタイには二重らせんがデザインされていたそうである。
だれもが、このRANタイクラブの一人が遺伝子コード解明の先駆けをするものと信じていた。ところがそれを行ったのは、当時、NIHの研究員の一人に過ぎなかったマーシャル・ニーレンバーグ (1927-2010)であった。かれはドイツから来たポスドクのヨハネス・マッシー (Johannes Mathaei)と協力し、無細胞タンパク質合成系を使って実験をすすめた。そして人工的RNA(UUUUUUUUUUUUUU)を用い、UUUがフェニルアラニンに対応していることを明らかにした。この実験結果は1961年8月のモスクワでの国際生化学会議で発表された。ニーレンバーグは結局、64個のアミノ酸コドンのうち54個を明らかにしている。
先を越されたRNAタイクラブは、このニーレンバーグの発表に驚き、かつ不快であった。ニーレンバーグの講演で、ワトソンが嫌がらせをしたのは、まさにその態度表明であったのだ。
ワトソンの相棒であったイギリス人のクリックも、人の講演中に同じように嫌がらせをしたことを、庵主は前のブログで述べた (「悪口の解剖学 IV フランシス・クリック、おまえもか!」19/06/24)。ペルツの言うように、二人とも尊大で二重螺旋のように屈折したところがあった。
追記 (2020/03/12)
ジェームズ・ワトソンは、分類学者の間でも評判が悪い。スティーブン・B・ハードはその著『学名の秘密』(上京恵訳)(原書房 2021)でインドネシアのゾウムシにTrigonopterus watsoniの学名が付けられたことに憤慨している。著者はワトソンを強固な人種差別主義者、女性差別主義者として知られており、長らく彼に献名された種の学名がないことを吉としていた。
参考図書
Franklin H. Portugal. The Least Likely Man-Marshall Nirenberg and the discovery of the genetic code. The MIT Press、2015
Max・F・Perutz. Is Science Necessary? Essays on Science and Scientists. E.P.Dutton,
1989(『科学はいま』中馬一郎訳 1991、共立出版)