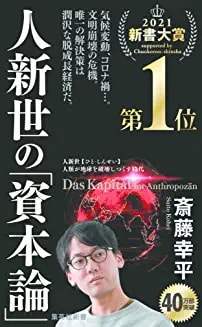医師シーボルトの功績
江戸時代に長崎・出島のオランダ商館にやってきた外国人の医師としてはシーボルトが最も有名である。フィリップ・フランツ・フォン・バルタザル・シーボルトは1796年、神聖ローマ帝国・バイエル州のヴュルツブルクに生まれた。シーボルト家は代々、医者の名門で父親はヴュルツブルク大学医学部教授であったが、シーボルトが2歳の頃に若死にしてしまった。そのため叔父のもとで母親に育てられた。人は幼児期に父と死別すると、後になって困難な状況での強い意志力と決断力、自分自身や家族のための成功への強い欲求心をしばしば引き起こす。シーボルトも、その人生の軌跡をみるとこの例外ではなかった。
ヴュルツブルクの高校卒業後、1815年にヴュルツブルク大学医学部に入学している。ナポレオン戦争後のことで、ドイツの医学は急速に進展期に入っており、各地に多くの医学校が設立され、医学教育が充実し、医学生は解剖学や生理学などの基礎的な科目を学びながら臨床的な経験を積んでいた。さらに細菌や感染症の研究が進み、パストゥールやコッホらによる細菌理論の確立はまだ少し先のことだが、感染症の伝播や予防に関する研究も盛んであった。ヴュルツブルク大学医学部のレベルは高く、臨床関係の多くの研究所を備えていた。シーボルトが履修した科目の記録は存在しないが、外科、内科、眼科を中心に勃興しつつあるドイツ近代医学を習得したものと思える。

このような時代の雰囲気を背景にシーボルトは青年期を過ごしたが、彼は医学の他にも植物・動物・地理・人類学をひろく履修したと言われる。シーボルトは亡父の友人で解剖学のイグナーツ・デルリンゲル教授の家に下宿していたが、そこで様々な分野の学者や研究者者と交流し自然博物学の関心を高めた。もっともこの頃は、かなりの荒くれ学生であったようで郷土のメナーニア学生団に属して何度も決闘し、顔に消えない傷跡を残した。
1820年大学卒業後、国家医師免許を取得しハイディングスフェルトでしばらく開業していた。この頃は内科医とか外科医といった区別はなく、医者は「なんでも屋」の時代であった。そして1822年オランダ政府に就職し、東インド陸軍病院の軍医少佐となってバタヴィア(現在のジャカルタ)に派遣された。前から熱望していた東洋の自然研究を行なう絶好の機会と考えたのである。しばらく、そこに滞在していたが、1823年(文政六)ファン・デル・カペレン総督により日本に派遣される事になる。帆船「三人姉妹号」に乗り込んだシーボルトは8月12日に長崎・出島に到着した。このとき役人による人別改めにおいて、シーボルトのオランダ語発音が疑われたが、日本人通詞が「彼は高地オランダ人である」と機転を利かせてくれたので虎口を逃れることができた。そして来日した翌月には、早々と長崎・丸山の遊女であった楠本滝(基扇)と結婚している(遊女ではなかったという説もある)。後にシーボルトとツッカリーが『ファウナヤポニカ(日本植物誌)』でアジサイの種小名をotaksaとしたのは、この「お滝さん」の名を採ったことは有名な逸話だ。しばらくして、お滝さんとの間に娘(いね)をもうけた。
第1回の訪日時(1823年8月1日~1829年12月30日)シーボルトは、出島でオランダ商館の館員の病気や怪我を診る医官としての役割を果たすとともに、日本の動物・植物などの自然物を収集し、そのコレクションをオランダ政府に送った。シーボルトは出島に来て1年3ケ月ほど経ってバタビアのオランダ政庁総督に宛てた報告書のなかで、「博物学やその他諸学の研究と医療活動を自分が並行して行なうのは困難なので、別に医師1名を日本に派遣して、自分が自然調査に専念できるようにしてほしい」と要求している。この頃は、医師としての任務よりも博物学研究を一義的に考えるようになっていた事を示している(あるいは最初からそのように考えていたかもしれない)。
1826年には館長のスチュルレルに随伴して約5カ月かけ江戸参府旅行に出かけた。このとき江戸滞在中に幕府天文方・書物奉行の高橋景保と接触し、伊能忠敬が作成した『大日本沿海輿地全図』(日本全土の実測地図)の写しを手に入れた。景保はかわりにクルーゼンシュテインの著『世界周航記』をシーボルトから受け取ったとされる。後に、これが幕府に発覚しシーボルト事件を引き起こすことになる。シーボルトは1829年(文政12年)に国外追放の上、再渡航禁止の処分を受け、12月に多数の収集品とともにオランダに向け出航した。オランダに帰着してからはライデンに居を構え、コレクションの整理と『日本』『日本動物誌』『日本植物誌』の著作・編纂に努めた。48歳にあたる1845年には、ドイツ貴族出身の女性、ヘレーネ・フォン・ガーゲルンと結婚し、3男2女をもうけている。
1859年、63歳になったシーボルトは13歳の息子アレキサンダーを伴って、オランダ貿易会社顧問として再来日した。その5年前に日本は開国し、さらに前年には日蘭修好通商条約が結ばれ、シーボルトに対する追放令も解除されていたのである。彼は鳴滝に居を定め、オランダ政府の為に外交にかんする献策をしながら日本研究を続けた。午前は日本人訪問客の応接に務め、午後は植物研究のために遠出した。白髭をたくわえたシーボルトが町や村に現れると、名主や町医者に歓待されて病人を診断した。そこでは患者には欧州の薬を処方するように乞われる事が多かったそうである。1861年には貿易会社との、契約が切れたため、幕府の外交顧問・学術教授となり江戸に向かった。江戸・横浜に滞在し、今度は幕府のために助言を行い、赤羽根の接待所で日本人に様々な教科を講義した。並行して博物収集や自然観察なども続け、風俗習慣や政治など日本関連の記述を残している。1862年に幕府により職を解かれ、5月長崎から帰国した。故郷のヴュルツブルクで「日本博物館」を開設するなどの活動をしていたが、1866年12月21日に70歳で没した。
シーボルトの日本における活動は、多面的なもので、自然博物学者、医師、情報収集官、外交官(2回目の訪日時)に分類できる。その中で自然博物学者としての活躍がもっとも顕著で有名であるが、医師としての実績や評価についてはどのようなものであったろうか。シーボルト関係の書にあるように本当に名医だったのであろうか?
それまでの商館医ケンペルやツュンベリーなども日本人の患者を診たが、出島に出入りする者や長崎の要人に限られていた。一方、シーボルトは身分の上下に関係なく広範な日本人患者の治療にあたった。一切、金銭を受け取らなかったので、患者達は感謝の意をこめて諸国の物産、美術品、工芸品、薬草、珍しい自然物などを置いていくようになった。シーボルトが、こういった物品をコレクションしているのを知っていたからである。診療活動の範囲は、最初は出島と長崎市内に限られていたが、郊外の鳴滝塾で患者を診るようになる。商館医へのこのような優遇は、それまで考えられなかった事であった。江戸参府中の日記には、シーボルトの噂を聞いて、道中いたるところで蘭方医や患者が宿屋に押しかけてきた様子が記録されている。
シーボルトが来日していた頃、日本では天然痘が流行していた。種痘は1796年に英国人エドワード・ジェンナーによって発明されたものであるが、西洋ではようやく汎用されるようになっていた。記録によると、牛痘ワクチンをオランダから持参したシーボルトは出島に着いた直後に、男の子3人に種痘を施している。さらに江戸滞在中にも子供5人にこれをおこない、そのやり方を幕府の医師に教えている。ただ、ワクチンが失活していたために、うまくいかなかった。種痘が本邦に根を下ろしたのは、約20年後の緒方洪庵が除痘館を設立した頃の事である。シーボルトは叔父宛てに「私が初めて日本に牛痘種を導入しました」と報告しているが、彼の前任者の商館医テュリングがすでにそれを行なっており、長崎の蘭方医吉雄幸載がこれに立ち会っている。
シーボルトは江戸滞在中、眼科の侍医の訪問を受け、豚の眼の解剖実習を行ない、ベラドンナで人の瞳孔を開く実験を見せている。この時の様子をシーボルトは『江戸参府紀行』の中で「私は眼科についての書物と眼科関係の器具をいっしょに見せた。さらに瞳孔をベラドンナによって拡げる実験を行なう。その著しい効能に人々は驚き喝采した」と記している。ベラドンナとは、ナス科植物で外国産のAtropa bella-donnaの根から調整した薬剤であった。このとき見学していた侍医の中に土生玄碩(はぶげんせき)がいた。彼はシーボルトからベラドンナを分譲してもらうかわりに、将軍から拝領した葵の紋服を贈った。後に、これが露見して処罰されることになるが、この奇跡のような薬をどうしても手に入れたかったのである。玄碩は、シーボルトから、日本にもベラドンナが自生していると聞き、その植物を取り寄せ、白内障治療の虹彩切開手術に成功している。ただ、この植物はベラドンナでなくハシリドコロ(Scopolia japonica)であった。これらは属の違うよく似たナス科の毒草で、水谷助六(豊文)の描いた写生図に出てくるハシリドコロをシーボルトがベラドンナと見間違っていたのである。
この頃の西洋の内科治療は、漢方と同じく薬草に頼る薬物療法であった。シーボルトが植物学に蘊蓄が深かったのは、自然博物学的な興味があっただけでなく、このような実用的な関心があったからである。シーボルトは欧州で使われている薬草を持参して治療に利用した。また長崎郊外に出かけて薬草探しも行なっている(実際は薬草収集を名目にした植物採集といったほうが当たっている)。また出島の植物園でも多くの薬草を育てた。当時の日本人医師の中には、漢方とさほど変わらないオランダ内科に批判をくわえる者もいた。たとえば建部清庵は「オランダ人医者は年々、出島にやって来るが、まともな内科というものがない。オランダ流といっても膏薬と油薬を使うだけだ」と杉田玄白への手紙で悪口をいっている。
シーボルトの最大の功績は治療活動そのものよりも、日本人医師(蘭方医)に対する医学教育であったといえる。それまでのオランダ商館医は出島の通訳や周りの限られた日本人に西洋医術を個別的に伝授していたが、シーボルトは長崎郊外に「鳴滝塾」を開設し、全国から若い優秀な医師を集め、授業と臨床講義を行なった。美馬順三、岡研介、伊藤玄朴、石井宗謙、伊藤圭介、二宮敬作、高良齋、湊長安、小関三英、鈴木周一、本間玄調、高野長英などの蘭方医が集まった。多くは後に日本の近代医学の発展に貢献した。先ほど述べた種痘にしても、シーボルトに方法を伝授された多くの弟子がそれを広めた。
シーボルトの書いた医学的論文としては、大著『日本』の付録に載せた「日本の鍼術知見補遺(烙針法)」と「艾(もぐさ)の効用」がある。いずれも短いものだが、門人が提出したオランダ語論文をシーボルトが細かく添削してドイツ語に翻訳したものである。鍼についてはシーボルトが自ら試し「まったく痛みを起さず炎症もない」と感想を述べている。また美馬順三が加川流の産科教科書(『産論』」)をオランダ語にまとめて提出したレポートを、これも添削後、自分の名前でドイツの産科雑誌で発表した。シーボルト自身が医学的関心や興味でまとめた論文は見当たらない。
シーボルトは1829年に帰蘭後、コレクションの整理と日本研究に集中し、医師としての活動はほとんど行なっていない。息子のアレキサンダーはそれを見て、「父は医学の才能を先祖から受けついでいたのに、自然科学を偏愛して医学の分野をなおざりにしたことは、まことに残念な事である」と述べている。もっとも再来日時には、30年間診断から遠ざかっていたにもかかわらず、日本人患者を診ており医師とも交流している。たとえば長崎町年寄の後藤惣佐衛門の陰嚢潰瘍手術の記録と処方箋が残されている(注1)。1861年7月6日、浪人が横浜のイギリス公使館を襲撃した東禅寺事件に際しては、シーボルトは現場に駆けつけて負傷者を手当した。シーボルトの再来日した頃、松本良順の奔走により長崎医学伝習所が幕府により開設されており、ヨハネス・ポンぺが招聘され教授をしていた。シーボルトとポンぺが直接、接触した形跡はないが、シーボルトが斬首された囚人の遺体を検分し、それをポンぺが解剖実習に用いたという記録が残っている。良順とは1986年9月1日に長崎で会って情報交換している。
高野長英は医師シーボルトを高く評価し、父にあてた手紙で「この度の医者は格別秀いでている」とベタ褒めしている。一方、弟子の一人、本間玄調は「とかく評判は高いが、これといって特段の技術を持っているわけではなく、外国人というだけで初学者のようである」と手厳く批評をした手紙を知人に送った。玄調は全身麻酔を行った華岡青洲の弟子でもあった。弟子の間でも、このように評価は分かれていた。
後に呉秀三はその圧巻の著「シーボルト先生ー其生涯及功業」においてつぎのように述べている。
「シーボルト先生が出島を出でて、鳴滝塾に臨むはたいてい一週間に一回を例とし、その合間に楢林・吉雄氏は険悪なる症状にして診断治療に困難なるものを集め置き、シーボルト先生の来らるるを待ちて居り、先生はその病人を診て、いちいち症状を説明し、診断の仕方・治療の方法をうけるときは、鳴滝校舎にておこなえり。腹水穿刺を最初の手術として、腫瘍切除・その他外科・眼科・婦人科の諸手術並びに内科的処置は容易ならぬ難病を平癒せしめ、幾多の人命をいと危うき瀬戸際に救ひたり」
呉秀三は、もともとシーボルト教の教祖のような人だったので、この評価はだいぶ割り引いて聞く必要があるが、他にもシーボルトは名医であったという説を唱える人は多い。しかし、シーボルトがどれほど有能だったとしても、開業医経験がわずか2年で「名医」といわれるレベルに達していたとは思えない。ただ、彼が学んだ西洋医学のレベルと当時の日本のそれとの落差や、持ち前の積極性、実行力、人間的魅力が人々を惹きつけたことは確かである。それまでの商館医には見られなかった活躍を行なったことは間違いない。

(注釈)長崎のシーボルト記念館に残されている記録文書では、その処方箋は次のようになっている。「タンポポの根(4オンス)、忍冬(2オンス)、山帰来(2オンス)、キナ皮(1オンス)、大黄(2ドラム)1.5フラスコの水を1フラスコになるまで煮る。毎日、朝晩にそれぞれ小さい湯呑茶碗一杯分宛」ドイツ語でシーボルトが記したメモを蘭方医になった娘のいねが日本語に訳したものである。