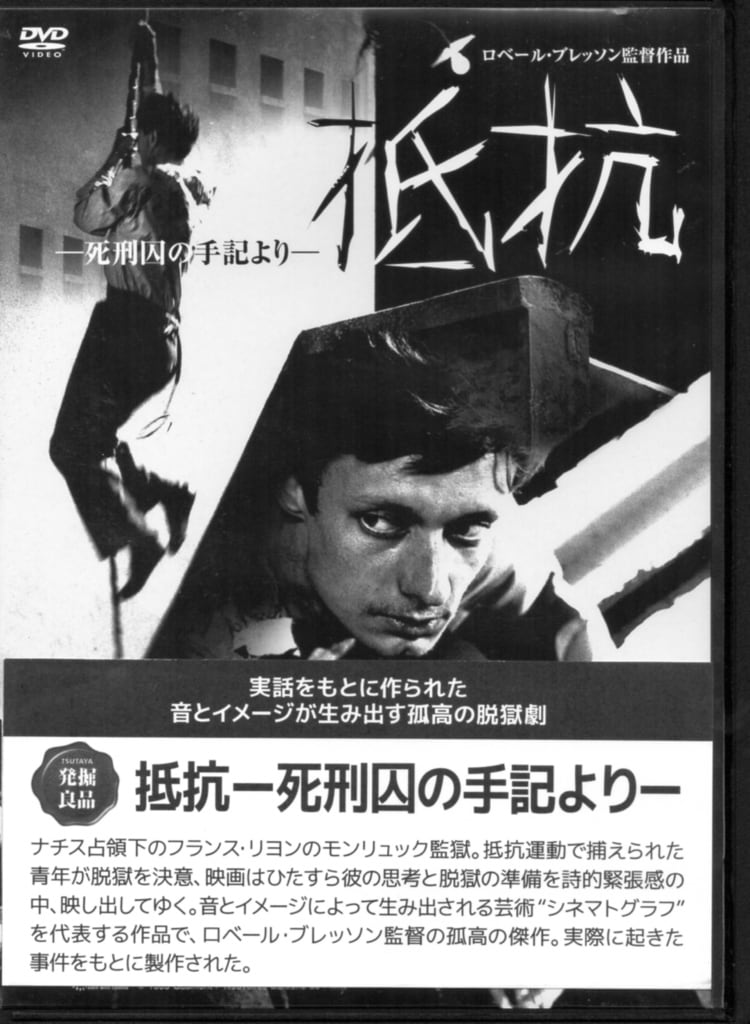
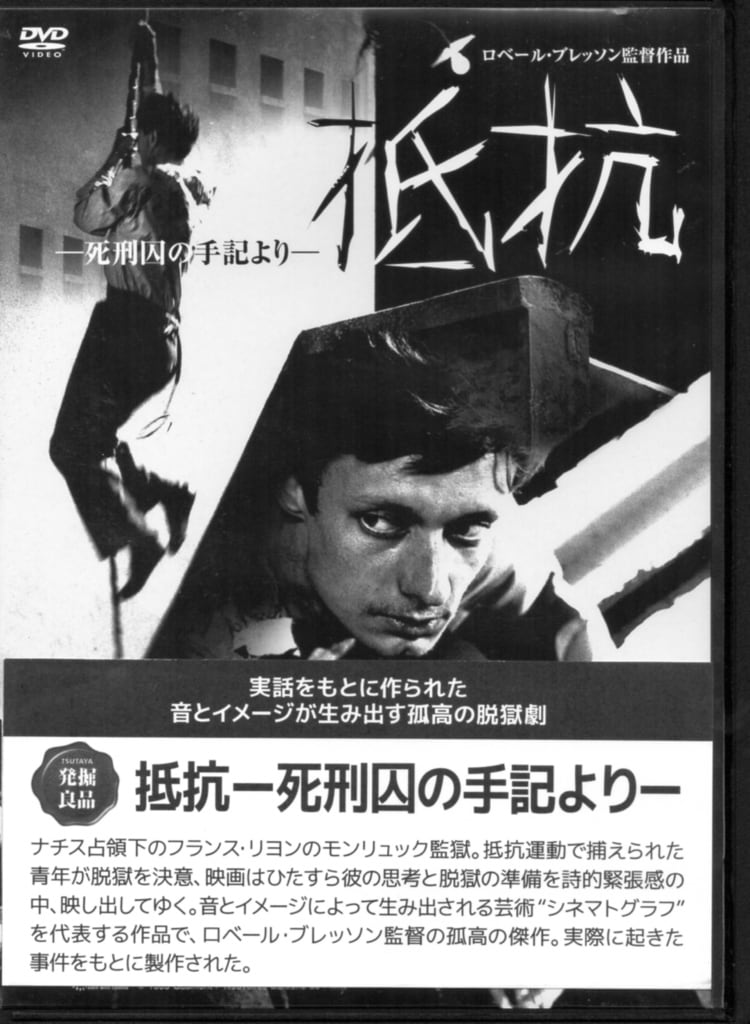

英国は第二次大戦中、チャーチル首相に率いられた民主国家で、何事もジェントルマンで合理的かつ理性的にふるまっていたかというと、決してそうではなかった。戦争が勃発するや、国内に居住するすべてのドイツ人を無理やり拘束した。1940年にイタリアが参戦すると、やはり「国内のイタリア人全員に首輪を付けよ」というチャーチルの号令がだされた。これらのドイツ人やイタリア人の大部分は、反ナチ、反ファシズムの善良な市民であったのにもかかわらずである。要するに、太平洋戦争でアメリカ合衆国に居住する日系アメリカ人が、強制キャンプ場に収容されたのと同じような理不尽なことがおこなわれていた。
収容されたイタリア人は、アマンド・スターという客船にのせられてリバプールからマン島に運ばれることになった。マン島は、グレートブリテン島とアイルランド島に囲まれたアイリッシュ海の中央に位置している辺鄙な島である。船に乗り込む前に、彼らの所持品はほとんど没収され、ごく少しのものしか携行を許されなかった。山積みされた没収品を、警官を含んだ雑多な人間がよってたかって横領した。この哀れなイタリア人の中に、BBCで働いていたダンテ研究家のウベルト・リメターンが含まれていた。
船には護衛の軍艦はついていなかったので、出航してまもなく、ドイツのUボートの魚雷によって沈没することになるが、そのときリメターンは「生きんとする強烈な意志力」で九死に一生を得ることになる。
爆発がおこって船内は停電した。リメターンは決断を下す前に、必ずしばらく熟考した。同室の3名の乗客はパニックになってたちまち部屋を飛び出したが、リメターンは、冷静にも暗闇の中で壁にかかっている救命具をみつけて身につけた。甲板に上がると、ここでも人々はパニックになって動きまわっていた。彼は縄梯子をみつけて傾いた下甲板に降り、タイミングをはかって海に飛び込んだ。最初にしたことは、浮かんでいる漂流物を見つけてそこに泳ぎつくことであった。そして沈没する船に巻き込まれないように、いそいで離れた。船は急速に沈みはじめボイラーが爆発して、まわりの物も人も吹っ飛んだ。いたるところに漂流物と死体がただよっていた。約1時間半ほどして、2Kmも先に救命ボートの影をみつけたので、木片にすがりついてそれに向って泳いだ。「難破せし船の舳先を波が押し沈めるがごと」というアレサンドロ・マンゾーニの詩を何度も暗唱しながら、必死に泳ぎつづけた。そして、力尽きる寸前にリメターンは救命ボートにたどり着き助け上げられた。このエピソードは、マックス・ペルツというノーベル化学賞受賞者の著『科学はいま』(共立出版 1991)に載せられている。
危機のときは瞬間の判断が生死を左右するというが、むしろしばらく熟考したほうが、生き残る確率は高いという教訓である。
佐野三治著『たった一人の生還-「たか号」漂流二十七日間の闘い』新潮社 1992年
(1995年に新潮社から、2013年に「山と渓谷社」からそれぞれ文庫本がでている)。

前掲のスティーヴン・キャラハン『大西洋漂流76日』もヨットによる海難漂流の手記であるが、これは最初からキャラハン一人の物語りであった。この手記は6人のクルーで遭難、最後まで生き残ったのは佐野一人というさらに過酷な実話である。
1991年12月26日「トヨタカップ ジャパングアムヨットレース」に参加した「たか号」(全長14メートル)は、クルー6名をのせて小網代(三浦市)を出帆した。艇長はベテランの水川秀三。31歳の佐野は飛び入りでクルーとして参加していた。出発の直前まで艇の改修に時間が取られ、なすべき事故対策の準備が不十分であった。この事が後におこる悲惨な遭難の遠因となった。
27日になって強風が吹き荒れ、メインセールに穴が開きリタイアを検討するが、レースを続行する。そして、29日の夜になって突然ヨットは転覆する。巨大な崩れ波をかぶったのではないかと著者は言う。水川(船内で水死)を除く5名はヨットから抜け出し、海面で逆さまになったふな底にとりついていた。そのうち急にヨットが起き上がったので、デッキに這い上がり固縛してあったライフラフト(ゴム製の丸い救命ボート)を海面に浮かべて乗り移った。備品、食料品、水などはほとんど流されてしまった。ここから太平洋の真中で6人の過酷な漂流が始まる。
漂流が始まってしばらは誰も比較的元気だったが、渇水と餓えで次第に弱り始める。1月9日に2機の飛行機を上空に認める。一機はYS11であったという。10日になってリーダー格の武市俊が死ぬ。翌日さらに鍋島博之と橋本定文、緒方稔の三名がたて続けに衰弱死する。13日の朝方になって、ラフトの天辺にとまったカツオドリを捕らえれて高瀬恒夫と二人で食べる。生のままであったがどの組織も美味しかったそうだ。さらにスコールが来て真水が補給できたのは幸運であった。しかし1月16日に心臓マヒで高瀬が逝く。19日に二匹目のカツオドリを捕獲して一人で食べる。おそらくこれらの食糧と水が手に入らなければ、著者の生命は発見されるまでに持たなかったのではないか。以下本文を一部編集して引用。
「その時は鳥が吐き出した飛魚だけを食べた。二十センチぐらいはある、かなり大きな飛魚だった。目玉や脳味噌は水分があったので食べやすかったが、身の方は、水分をとったいなかったので、咀嚼するのだが、飲み込めない。しかし生きるために食おうと思い、また一呼吸おいて、なんとか飲み込んだ。死を覚悟したなどと言いながら、やはりどこか生きようという本能は残っていた。残した一匹は、その日の夜中に食べている。食いたいと思わなかったが、食うのが生きるための行動だと思い。食おうと決意した」
最後に残った佐野は、25日イギリス船籍の貨物船に奇跡的に救助されたのである。溺れる者はワラをも掴むというが、生存の可能性があれば人はそれにトライするべきという例である。
ヴィクトール•フランクル (Viktor Emil Frankl 1905-1997)『夜と霧』霜山徳爾訳(みすず書房)1956年

庵主が小学生5-6年の頃、父親の本棚に並んでいた「夜と霧」(初版本)を読んだ。本を開くや、ナチスドイツの強制収容所で写した何枚もの無惨な写真が出てきて、恐れおののいた記憶がある。虐殺場面などの残虐なシーンが続くので、新版ではこれらは収録されてないはずである。その時の写真の印象が強烈で、本の内容について、どのように思ったかについては全くおぼえていない。しかし、読み直してみて、評判どおり読むべき20世紀の一冊であると思った。
初版は本文の前に「解説」があり、ナチスの強制収容所であるアウシュビッツ、ベルゼン、ブッシェンワルト、ダッハにおいて、どのような残虐で非道な事が行われていたかが、細かく書かれている。第三帝国のあらゆる悲惨な道が、強制収容所での死へと続いていた。ユダヤ人、ロシアの戦争捕虜、パルチザン、連合国捕虜、夜と霧の囚人、ジプシー、障害者、侵略に協力する事を拒否したり、あるいは侵略者に抵抗した市民は、いずれもゲシュタポによって、その家庭から引きずり出された。これら無辜の人々を待ち受けていたのは死であり、たとえ運よくここを出れたとしても、身体は痛めつけられ、心にはすっかりひびが入れられていた。この「解説」では、ナチスの強制収容所の状況が詳しく報告されている。「ホロコーストは捏造だと」いう主張を一蹴できる資料である。
「劣等」民族や人種に対する「最終的解決」はナチズム哲学の具体的な実践であり、強制収容所における集団虐殺であった。一方において、これは戦時における労働奴隷の確保を前提に、使えない弱者や病者を順次、ガス室で抹殺していくといった合理的、能率的な計算にもとずくものであったとされる。この悪魔的な非人間性は、ナチス思想とドイツ人独特の合理主義とベルトコンベアー式近代工業をミックスして発揮されたものだ。アウシュビッツの正門ゲートには、Arbeit macht Frei (労働は自由への道)という象徴的標語が掲げられていた。
著者フランクルは1905年にウィーンで生まれる。フロイド、アドラーに師事し、ウィーン学派の精神分析医であった。1938年ドイツによるオーストリア併合後、この国のユダヤ人に苦難が始まる。そして1942年に家族とともに強制収容所に送り込まれる。単に一家がユダヤ人だという理由だけで。両親、妻、二人の子供はガス室で、あるいは餓死あるいはチブスで病死した。フランクだけが奇跡的に生き延びたのである。日常が死と隣り合わせの状況で、心理学者の眼で強制収容所を見つめ、生きると言う意味を考え続けた。ここで生き残った人とそうでなかった人の差は、運以外になんであったのか? そのヒントを本文からいくつか引いて紹介する(文章は一部改変)。
• どんなときにも自然を見つめる。
『労働の最中に一人二人の人間が、自分の傍で苦役に服している仲間に、丁度彼の目に談った素晴しい光景に注意させることもあった。たとえばバイエルンの森の中で、高い樹々の幹の間を、まるでデューラーの有名な水彩画のように、丁度沈み行く太陽の光りが射し込んでくる場合の如きである。あるいは一度などは、われわれが労働で死んだように疲れ、スープ匙を手に持ったまま土間に横たわっていた時、一人の仲間が飛び込んできて、極度の疲労や寒さにも拘わらず日没の光景を見逃させまいと、急いで外の点呼場まで来るようにと求めるのであった。そして、われわれはそれから外で、酉方の暗く撚え上る雲を眺め、また幻想的な形と青銅色から真紅の色までのこの世ならぬ色彩とをもった様々な変化をする雲を見た。そしてその下にそれと対照的に収容所の荒涼とした灰色の損立小屋と泥だらけの点呼揚があり、その水溜りはまだ撚える空が映っていた。感動の沈黙が数分続いた後に、誰かが他の人に「世界ってどうしてこう綺髭なんだろう」と尋ねる声が聞えた』
地球の自然にやすらぎを求めるのは、おそらく虫をはじめとする全ての動物の習性であろうと思う。習性への回帰が命を延ばす。
• 希望を失う事が免疫を低下させる
『勇気と落胆、希望と失望というような人間の心情の状態と、他方ではその抵抗力との間にどんなに緊密な連関があるかを知っている人は、失望と落胆へ急激に沈むことがどんなに致命的な効果を持ち得るかということを知っている。私の仲間のFは期待していた解放の時が当らなかったことについての深刻な失望が、すでに潜伏していた発疹チブスに対する身体の抵抗力を急激に低下せしめたことによって死んだ。彼の未来への信仰と意志は弛緩し、彼の肉体は疾患におちいったのである。このI例の観察とそれから出てくる結論とは、かつてわれわれの収容所の医長が私に注意してくれた次の事実と合致する。すなわち1944年のクリスマスと1945年の新年との間に、われわれは収容所では未だかつてなかった程の大量の死亡者が出ているのである。彼の見解によれば、それは過酷な労働条件によって、また悪化した栄養状態によって、また悪天候や新たに現われた伝染炊患によっても説明されえるものではなく、むしろこの大量死亡の原因は、単に囚人の多数が、クリスマには帰れるだろうという素朴な希望に身を委せた事実の中に求められるのである』
安易な希望的な観測は、予想がはずれるとかえってダメージが大きい。しかし、楽天的であることと精神のタフネスの維持が二律背反とは思えない。
• ユーモアーと遊びを忘れずにいる
『もし収容所にはユーモアがあったと言ったならば、驚くであろう。もちろんそれはユーモアの芽のごときものに過ぎず、また数秒あるいは数分間だけのものであった。ユーモアもまた自己維持のための闘いにおける心の武器である。周知のようにユーモアは通常の人間の生活と同じに、数秒でも距離をとり、環境の上に自らを置くのに役立つのである。私は数週間も工事場で私と一緒に働いていた一人の同僚の友人に、少しずつユーモアを言うようにすすめた。すなわち私は彼に提案して、これからは少くとも一日に一つ愉快な話をみつけることをお互いの義務にしようではないかと言った。彼は外科医で、ある病院の助手であった。私は彼に、たとえば彼が後に家に帰って以前の生活に戻った時、収容所生活の癖がどんなにとれないかを面白く描いて、彼を笑わせようと試みた。このことを語る前に先ず説明しておかなければならないのが、労働場では、労働監督が巡視にやってくる時には、看視兵は労働のテンポをその時早めさせようとして、いつも「動け、動け」と言ってわれわれをせきたてるのが常だった。だから私は友に語った。もし君が手術室に立って、そして長く統く胃の手術をしていたとする。すると突然手術室係りが飛び込んできて「動け、動け」と知らせる、それは「外科部長がやってきた」ということなのさ』
ユーモアと遊びはどんな時にも必要である。これは人をパニックから救ってくれる。
• 人生(世界や社会や他人)に何を求めるかではなく、それが私に何を求めているかを問う。
『既述の如く、強制収容所における人間を内的に緊張せしめようとするには、先ず未来のある目的に向って、緊張せしめることを前提とするのである。囚人に対するあらゆる心理治療的あるいは精神衛生的努力が従うべき標語としては、おそらくニーチエの「何故生きるかを知っている者は、殆んどあらゆる如何に生きるかに耐えるのだ。」という言葉が最も適切であろう。すなわち囚人が現在の生活の恐しろい「如何に」(状態)に、つまり収容所生活のすさまじさに、内的に抵抗に身を維持するためには、何らかの機会がある限り囚人にその生きるための「何故」をすなわち生きる目的を意識せしめねばならないのである』
et lux in tenebris lucet (光は闇を照らしき)
闇に光を探すのではなく、自ら闇に灯りをともすべし。「一隅を照らす」と天台の教えにもある。言い換えると、人生にはそれぞれ納得できるストリーの創造が必要であるということである。
• 精神的愛の確信
『その時私は或ることに気がついた。すなわち私は妻がまだ生きているかどうか知らないのだ!そして私は次のことを知り、学んだのである。すなわち愛は、1人の人間の身体的存在とは関係が薄く、愛する人間の精神的存在と深く関係しているかということである。愛する妻がまだ生きているかどうかということを私は知らなかったし、また知ることができなかった(妻はこの時にはすでに殺されていた)もし私が当時、私の妻がすでに死んでいることを知っていたとしても、私はそれにかまわずに今と全く同様に、この愛する直視に心から身を捧げ得たであろう』
付記:今日の京都新聞 (2019/07/23・ 30面)に、たまたま『ナチスの「安楽死」政策』というコラム記事がでていた。ナチスドイツの障害者「安楽死」政策で、約20万人もの人が犠牲になった。この背景には「経済性、効率性、生産性といった社会にとっての価値基準」があるとしている。
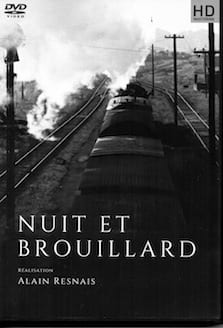
スティーヴン•キャラハン 『大西洋漂流76日』長辻象平訳 早川書房 1988.
キャラハンは全長21フィートの愛艇「ナポレオン•ソロ」号で、カナリア諸島のイエロ島からカリブ海のアンティグア島に向かった。1982年1月29日のことである。ところが出航して1週間ほど経った日の真夜中にクジラと衝突し、「ソロ」号は転覆してしまう。救命用ゴムボートに乗り移ったキャラハンの信じられないサバイバルゲームが、ここから始まる。結局、キャラハンは76日間の漂流後、カリブ・グアドルプ島の漁船に救助される。この奇跡の生還劇の背景には、キャラバンの知識、技術、幸運の他に、なによりもその意志力をあげることができる。しかし、それは何度も挫折しかけたものであった。

『わたしの周りにはソロ号からの回収品がある。装備はしっかり固定され、命に関わるシステムは機能している。日々の仕事の優先順位は決まっていて、異論の余地はない。耐え難い心細さと恐れ、苦痛をなんとか抑えている。わたしは危険な海に浮かぶ、ちっぽけな船の船長なのだ。ソロ号を失った後の動揺を乗り越え、とうとう食糧と飲み水を手に入れた。ほぽ確実と思われた死を免れた。そしていまや私は選ぶことができる。新しい人生を探して進むか、あきらめて死を受け入れるかだ。わたしは可能な限り、死に抵抗する道を選ぶ』(以上本文より引用)
つぎの母との回想場面も感動的である。
母はにこりともせずに、反論した。
「わたしは苦労をしてあなたを産んだんだから、そんなに簡単にあきらめてはだめよ」
そのときの母の言葉が耳から離れない。
「できるだけ長くがんばると、約束してね」
約束はしなかったが、今も変わらぬ響きをともなって、わたしの記憶に残っている。
絶望ー希望ー絶望ー希望...の繰り返しの中で、精神の錯乱をいかに防ぐかの心理劇が展開する。「安っぽい興奮でもまったくないよりましだ」と思うこともあれば、「まやかしの希望を抱かずに、生還のために知恵をしぼれ」、と思う事もあった。それとこの書は海での遭難時になすべきガイドともなっている(例えば太陽熱蒸留器など)。それとボートについてくる回遊性のシイラの生態が興味ふかい(どこまで科学的かは検証が必要だが)。 サバイバルノンフィクションの一級作品の一つである。
J.シンプソン『死のクレバス』-アンデス氷壁の遭難。中村輝子訳 岩波現代文庫 2000年11月
これは有名な山岳遭難ノンフィクションである。映画化もされた(「運命を分けたザイル」2005)。1985年、英国の二人の若きクライマーのジョー•シンプソンとサイモン•イエーツは、ペルーのアンデス山脈のシウラ•グランデ(6600m)に挑んだ。この峰の西側は前人未踏で、ほぼ垂直に立ち上がり、頂上は雲が暗くたれこめていた。登頂は困難を極めるが二人は登りつづけ、3日目についに頂上を極めた。頂上で心の底から湧いてくる笑いを抑えきれない二人は写真を撮る。しかし、下山で悲劇が起こる。ルートを見失い、突然、足場が崩れてジョーは急斜面を数十メートルほど落下し、足を骨折してしまう。負傷したジョーとサイモンは互いの身体をザイルで結び、下降を繰り返すが、ジョーはクレパスに滑落し、垂直な氷壁で宙吊りになってしまう。イエーツにはジョーの姿がみえず、声もきこえない。彼は今やジョーの全体重を支えなければならない。しばらくして、もはや選択の余地がないと考えたイエーツは、友人に死刑を執行していることを意識しながら、ザイルを切断する。しかし、落下したジョーはクレパスの氷棚にひっかかり、一命を取り留める。これからジョーの超人的な生きるための努力がはじまる。おそるべき意志力でジョーは数日をかけて、氷河を10kmもはい進み、まさにイエーツが下山しようとしていたその時に、ベースキャンプにたどりついたのである。
以下本書より抜粋
『アプザイレン〔ザイルを伝って岩壁を懸垂降下すること〕をやめたいという欲求は、ほとんど耐え難いほどだった。下に何かあるのかまったくわからなかったが、二つのことだけは確かだったIサイモンは行ってしまい、もう戻ってはこない。つまり、このまま氷橋にとどまっていれば、一巻の終わりだということだ。上に抜けることは不可能だったし、逆側の急斜面は、すべてを早く終わらせよとわたしを招いていた。ついその気になったが、絶望のさなかにあっても、自殺する勇気は持てなかった。氷の橋の上で、寒さと疲労で死ぬまでには、まだまだかかるだろう。しかし、長い時間をかけて、一人ぼっちで死を待ちながら、狂っていくのだ。この考えが、わたしに決断を迫った。脱出法を見つけるまでアプザイレンするか、その過程で死ぬかだ。死が来るのをただ待っているより、自分から死を迎えに行った方がいい。もう後戻りはできない。』
この意思堅固な男にとって、生存は自ら選び取るものだった。そして特にジョー・シンプソンが身をもって示したように、生存は至上命令だった。不運で機会を逸することはあっても、生きている限り至上命令に抗うことはできない。前回のアーネスト・シャクルトンといい、世界を一度制覇しただけあって、英国人(ジョン ブル)のど根性は並ではない。このドキュメントはプロの登山家が書いただけあって、臨場感がある。登山家の鮮烈な行動と心理がリアルに描けている。例えば回想場面だが、二人の日本人クライマーが目の前で滑落死する描写は凄い。「死のクレパス」はボードマン・タスカー賞、NCR賞を受賞している。

アルフレッド•ランシング 『エンデュアランス』(山本光伸訳) パンローリング社刊、2014
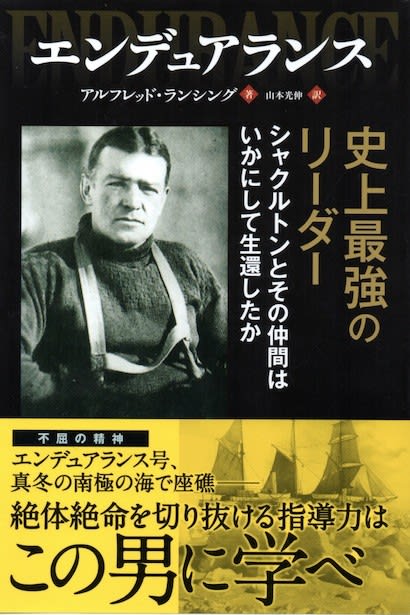
アーネスト•ヘンリー•シャクルトン (1873-1922)はアイルランド生まれの探検家である。1914年、シャクルトンは27名の隊員とともに南極大陸横断を目指して木造帆船で出発する。だが航海の途中で氷に阻まれて難破し、舟を捨てて漂流生活が始まる。母国とも連絡は取れず、苦難の生活が続く。シャクルトンは並外れた勇気と剛胆さを持って隊員を導き、17ケ月後に一人の犠牲者も出さずチームは帰還をはたすことができた。寒さと嵐、食料不足、病気、隊員どうしの不和といった極限状況の中でシャクルトンが、どのようにリーダーシップを発揮し、人々がそれに応じたかを迫真の筆致でえがく。
集団が極限の苦難に直面した場合は民主的な協議よりも、一人の強いリーダーが必要であることをこの書は教えてくれる。たまにリーダーが過ちをおかすにしても、その方が生き残る確率は高いのだ。そして、日常の中で人々が苦痛を精神的に軽減するために、いかに「遊び」が大事かも教えてくれている。彼らは遭難中にも次のようなパーティーを開いて不安や苦痛を消去する努力をした。
グリーンストリートはこの日の日記に次のように書いている。〈一番笑ったのは、カーが浮浪者の格好で『闘牛士スパゴニ』を歌ったときだ。カーは高すぎる音程で歌いだして、伴奏のハッセーが『もっと低く、低く』と言って、低い音で演奏しているのに構わずそのまま続けて、とうとうまるきり調子がはずれてしまった。闘牛士スパゴニの歌詞も忘れてしまって、闘牛士スチュバスキと言ってみたり、コーラスの部分なんてひどいもので、ただ『死んでしまえ、死んでしまえ、死んでしまえ』と怒鳴っていた。これがとにかくおかしくて、皆、涙をこぼして笑い転げた。マッキルロイはスペインの女の子に扮したが、これもひどいものだった。襟ぐりの深いイブニングドレスにスリットスカートをはいて、靴下の上に生の脚をのぞかせたマッキルロイが……スペイン・ダンスを踊ったのだ〉。マーストンは歌を歌い、ワイルドはロングフェローの詩『ヘスペラス号の難破』を朗唱し、ハドソンは混血の少女に、グリーンストリートは赤鼻の酔っぱらいに、リッキンソンはロンドンの街娼に扮した(以上引用)。
マーゴ•モレル、著『史上最強のリーダー シャクルトン ― 絶望の淵に立っても決してあきらめない 』(高橋裕子訳)PHP研究所、2001
この書も同じ事件のドキュメントであるが、ランシングの著が冒険小説的なの対して、シャクルトンにスポットを当てた心理ドラマの要素が強い。















