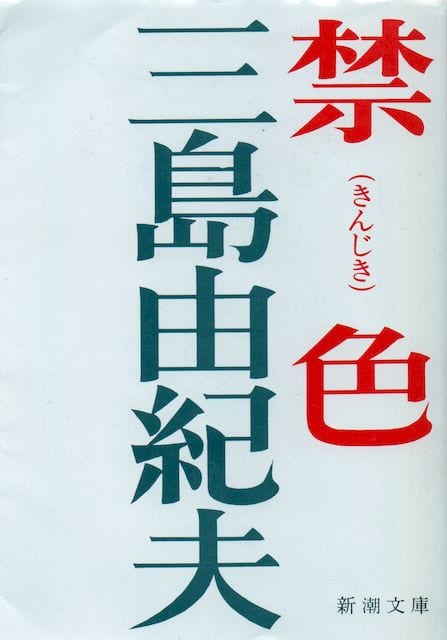
平野啓一郎の三島由紀夫論の中で、金閣寺と対をなす作品として鏡子の家、仮面の告白と対をなす作品としてこちらの禁色、が挙げられていました。禁色の内容はほぼ忘れているので、あらためて読んでみようと古本を購入。昔ながらの表紙で懐かしい。

で、読み始めたのはいいのですが、えらく時間が掛かってしまいました。こんなに難解な一冊だったっけ?2か月くらい掛かりましたよ。老作家が鬱積した青春の怨念を同性愛者の美少年を使って果すという話です。現代ではLGBTなどセクシャルマイノリティの理解が進んでいますが、発表当時としてはまさに禁色の事柄だったのでしょう。
ストーリーよりもその中にふんだんに散らばめられている様々な主張、思想の理解が難解なため、読むのがしばしばストップしてしまいます。たとえば、上の内容紹介にある「ルネッサンス的ヘレニズム思想」と言われても、それがなんのことか、そして具体的にこの作品のどこに表れているかを理解することも困難です。
前に呼んだのは40年ほど前で、当時はそれほど苦労して読んだという覚えはないのですが、若いせいで読解力が高かったのか、それともわかったつもりで読んでいて実はわかっていなかったのか、おそらく後者でしょう。若いっておそろしい^^;
三島がこの作品を書いたのは26歳から28歳のとき、群像と文學界への連載でした。単行本化に際し、ストーリーを変えています(鏑木夫人が自殺するのを止めた)。
本書は三島文学の理解を深めるためには、読んでおくべき一冊ではないかと思います。

作者プロファイル。

書誌事項。
初出は1951年からの連載、単行本化は1951年(上巻)と1953年(下巻)。
文庫化は1954年に新潮文庫から上下巻で、1964年に一冊にまとまっています。
p.s. 健康診断のあと昼飲み。

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます