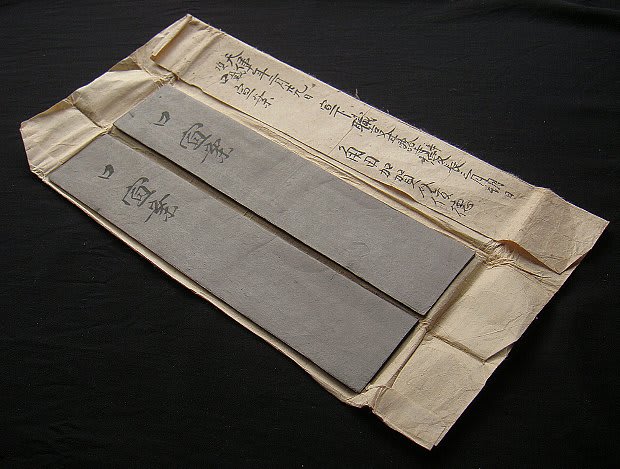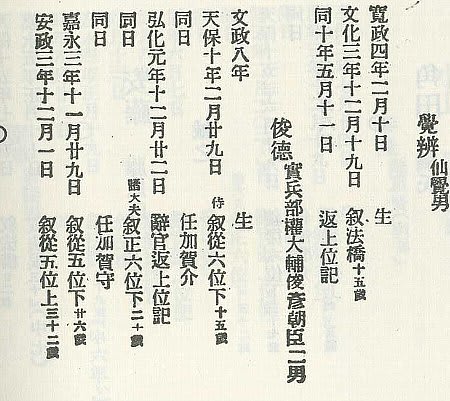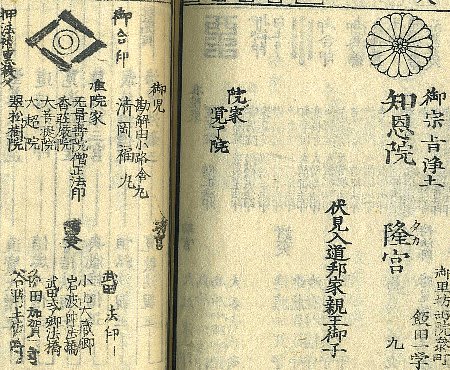密教の世界観が見事に具現化された佛尊たち。
眼光鋭い大日大聖不動明王を中心にそれぞれの印を結んだ
大威徳明王・降三世明王・軍茶利明王・金剛夜叉明王が鎮座し、その四方を
四天王と金剛力士が守護する。普段は四天王に踏みつけられる邪鬼も灯篭を持った
天燈鬼・竜燈鬼として表情豊かにその存在をアピールしている。

極彩色が大変美しい愛染明王・大日如来・孔雀明王と優美な像形の阿修羅・韋駄天

大変気高い面持ちの文殊菩薩・如意輪観音・毘沙門天・聖徳太子

まあ・・・シャレですから・・・w
「黒駒思いのままの記」←こちらも見てやってください。
 ←ポチッとお願いします。
←ポチッとお願いします。
眼光鋭い大日大聖不動明王を中心にそれぞれの印を結んだ
大威徳明王・降三世明王・軍茶利明王・金剛夜叉明王が鎮座し、その四方を
四天王と金剛力士が守護する。普段は四天王に踏みつけられる邪鬼も灯篭を持った
天燈鬼・竜燈鬼として表情豊かにその存在をアピールしている。

極彩色が大変美しい愛染明王・大日如来・孔雀明王と優美な像形の阿修羅・韋駄天

大変気高い面持ちの文殊菩薩・如意輪観音・毘沙門天・聖徳太子

まあ・・・シャレですから・・・w
「黒駒思いのままの記」←こちらも見てやってください。