松森俊尚さんの存在を初めて知ったのは、生活クラブ生協が発行している月刊『生活と自治』の教育コラム「魂のバトンリレー」の松森連載を読んだことからでした。2013年7月号から十数回続いたと思います。出会った子どもたちとの出来事を柔らかなタッチでドラマチックに描いているような印象を受けました。彼の子ども観や子どもとの付き合い方に自分と似たような匂いを感じたものです。
松森俊尚さんってどんな人かなと思ってそのままになっていたのですが、先日、ブックオフに行った時、偶然『けっこう面白い授業をつくるための本――状況をつくりだす子どもたち』を見つけ、早速購入しました。
感想を書く前にこの本の概略を紹介しましょう。
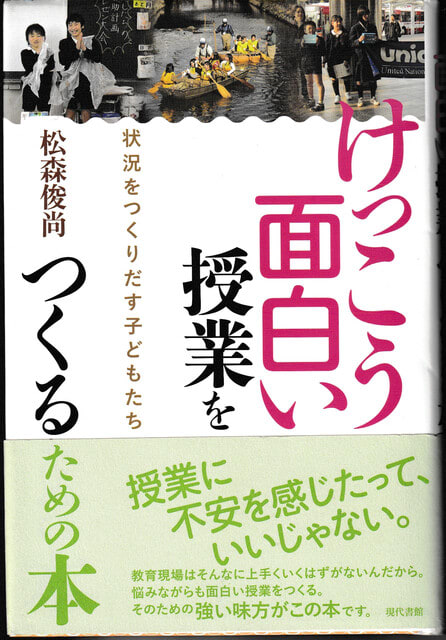
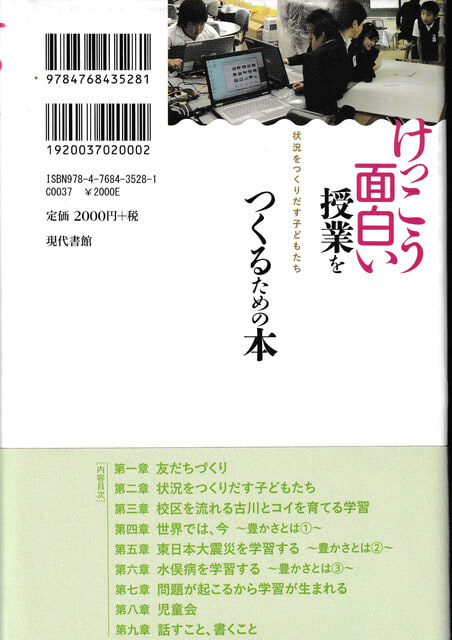
◆『けっこう面白い授業をつくるための本――状況をつくりだす子どもたち』松森俊尚、現代書館、264ページ、2000円+税(現代書館HPより)
学校教育に対する公権力の締め付け、それに乗じたと思われる過度の親からの干渉等により、自信を失い教育に情熱を感じられなくなった教師が増えている。そのような教師が自信を持って教育現場で子どもたちと社会をつくるための本。
〔オビ〕教育現場はそんなに上手くいくはずがないんだから。悩みながらも面白い授業をつくる。そのための強い味方がこの本です。
第1章 友だちづくり
第2章 状況をつくりだす子どもたち
第3章 校区を流れる古川とコイを育てる学習
第4章 世界では、今―豊かさとは1
第5章 東日本大震災を学習する―豊かさとは2
第6章 水俣病を学習する―豊かさとは3
第7章 問題が起こるから学習が生まれる―子どもたちがイジメと向かい合う
第8章 児童会―The government of the Children,by the Children,for the Children
第9章 話すこと、書くこと
●松森俊尚[マツモリトシヒサ]1951年大阪に生まれる。1976年大阪教育大学卒業後、寝屋川市内の小学校に勤務。2012年3月退職。
書名やオビだけ見て手に取る人とそうでない人に分かれる本のような気がします。ハウツーものの教育書と思ったら大間違い、本書は教育の本質に迫る渾身の実践記録です。率直に書いて、もう少し内容に相応しい書名やオビがあった方が良かったと思うのです。
「第1章 友だちづくり」では最初はハウツー本の雰囲気を漂わせながら、リアルな子どもが登場して期待を持たせました。第2章から6章までの授業づくりは圧巻です。学級や学年での図工、総合学習、社会の授業展開は目を見張るものがあります。しっかり学年も巻き込みながら「教えから学びの地平を拓く」(リーデフ'98のスローガン)ものになっています。
こんな実践記録を読みたかったというのが第7章のいじめ問題です。キリキリするような子どもたちの議論に松森センセも割って入りますが、自分なら学級通信にそうは書かないなとおもわず感情移入させられます。(拙著『いちねんせい-ドラマの教室』『ぎゃんぐえいじ-ドラマの教室』晩成書房、参照)
第8章の児童会づくりの実践は著者の並々ならぬ力量を物語っています。民主的で創造的な教師集団がなければこれだけの実践はできなかったでしょう。
第9章の「ヒロシマ修学旅行で」「識字学級で」も読み応え充分です。
●最後に余談をいくつか。
現代書館からの本書の出版を勧められたのが北村小夜さんとのことでした。ブログにも登場いただいている、私もよく知る大先輩との繋がりが知れて嬉しかったです。
気になったこと2点。
*「ぼくらの村」の作者は大関松三郎ではなく寒川道夫というのが今は定説になっています。『「山芋」の真実』(太郎良信、教育史料出版会)、拙著『地域演劇教育論-ラボ教育センターのテーマ活動』「寒川道夫の光と影」などを参照願います。
*「卒業式のシナリオ」は「卒業式の台本」が相応しいでしょう。シナリオは映画の脚本の場合に用いられることが多いようです。
ネットでもう1冊、松森さんの本が出版されていることを知りました。『街角の共育学- 無関心でいない、あきらめない、他人まかせにしないために』(現代書館 2020/8/20)またブックオフを探してみます。
松森俊尚さんってどんな人かなと思ってそのままになっていたのですが、先日、ブックオフに行った時、偶然『けっこう面白い授業をつくるための本――状況をつくりだす子どもたち』を見つけ、早速購入しました。
感想を書く前にこの本の概略を紹介しましょう。
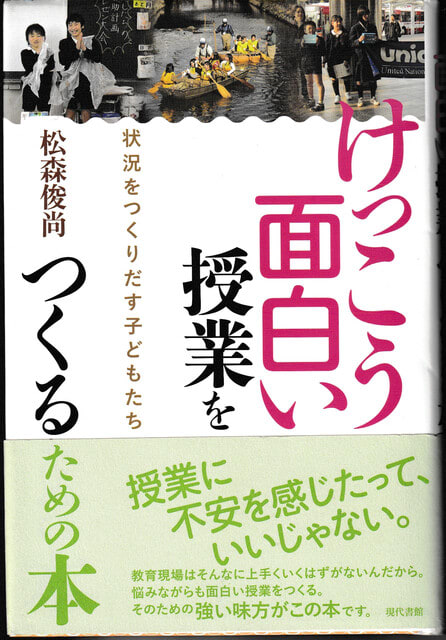
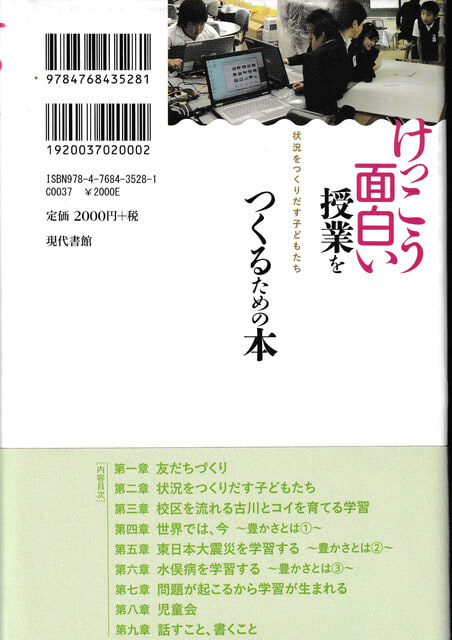
◆『けっこう面白い授業をつくるための本――状況をつくりだす子どもたち』松森俊尚、現代書館、264ページ、2000円+税(現代書館HPより)
学校教育に対する公権力の締め付け、それに乗じたと思われる過度の親からの干渉等により、自信を失い教育に情熱を感じられなくなった教師が増えている。そのような教師が自信を持って教育現場で子どもたちと社会をつくるための本。
〔オビ〕教育現場はそんなに上手くいくはずがないんだから。悩みながらも面白い授業をつくる。そのための強い味方がこの本です。
第1章 友だちづくり
第2章 状況をつくりだす子どもたち
第3章 校区を流れる古川とコイを育てる学習
第4章 世界では、今―豊かさとは1
第5章 東日本大震災を学習する―豊かさとは2
第6章 水俣病を学習する―豊かさとは3
第7章 問題が起こるから学習が生まれる―子どもたちがイジメと向かい合う
第8章 児童会―The government of the Children,by the Children,for the Children
第9章 話すこと、書くこと
●松森俊尚[マツモリトシヒサ]1951年大阪に生まれる。1976年大阪教育大学卒業後、寝屋川市内の小学校に勤務。2012年3月退職。
書名やオビだけ見て手に取る人とそうでない人に分かれる本のような気がします。ハウツーものの教育書と思ったら大間違い、本書は教育の本質に迫る渾身の実践記録です。率直に書いて、もう少し内容に相応しい書名やオビがあった方が良かったと思うのです。
「第1章 友だちづくり」では最初はハウツー本の雰囲気を漂わせながら、リアルな子どもが登場して期待を持たせました。第2章から6章までの授業づくりは圧巻です。学級や学年での図工、総合学習、社会の授業展開は目を見張るものがあります。しっかり学年も巻き込みながら「教えから学びの地平を拓く」(リーデフ'98のスローガン)ものになっています。
こんな実践記録を読みたかったというのが第7章のいじめ問題です。キリキリするような子どもたちの議論に松森センセも割って入りますが、自分なら学級通信にそうは書かないなとおもわず感情移入させられます。(拙著『いちねんせい-ドラマの教室』『ぎゃんぐえいじ-ドラマの教室』晩成書房、参照)
第8章の児童会づくりの実践は著者の並々ならぬ力量を物語っています。民主的で創造的な教師集団がなければこれだけの実践はできなかったでしょう。
第9章の「ヒロシマ修学旅行で」「識字学級で」も読み応え充分です。
●最後に余談をいくつか。
現代書館からの本書の出版を勧められたのが北村小夜さんとのことでした。ブログにも登場いただいている、私もよく知る大先輩との繋がりが知れて嬉しかったです。
気になったこと2点。
*「ぼくらの村」の作者は大関松三郎ではなく寒川道夫というのが今は定説になっています。『「山芋」の真実』(太郎良信、教育史料出版会)、拙著『地域演劇教育論-ラボ教育センターのテーマ活動』「寒川道夫の光と影」などを参照願います。
*「卒業式のシナリオ」は「卒業式の台本」が相応しいでしょう。シナリオは映画の脚本の場合に用いられることが多いようです。
ネットでもう1冊、松森さんの本が出版されていることを知りました。『街角の共育学- 無関心でいない、あきらめない、他人まかせにしないために』(現代書館 2020/8/20)またブックオフを探してみます。









