白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんの、ビルコック(Billecocq)神父様による哲学の講話をご紹介します。
※この公教要理は、 白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんのご協力とご了承を得て、多くの皆様の利益のために書き起こしをアップしております
Billecocq神父に哲学の講話を聴きましょう
ルソーは「地理学」ならちょっとでもやるといいといっています。というのも、地理学だと、周りの世界に基づいているからやっても良い学問だといっています。ただ、非常に手軽に限定的にやるべきだと。遊べる近くの川と芝生ぐらいを教えるだけでよい、まあ、ちょっと大げさに言ってみましたが、原文を見るとほとんど大げさに言っているわけでもありません。
というのも、ルソーが問題にしているのは、近くだけの地理学ではないのなら、地球模型を差し出す必要が出てしまい、そしてそれは「人工的な」段ボールの模型だからけしからんというのがルソーのスタンスです。本物の地球ではないから、地理学を習ってはいけないというロジックです。
歴史はダメ。言語学はダメ。死語ならなおさらのことだと言いますが、いつもラテン語で引用しているルソーなのになあ。これは、ルソーの多くの矛盾の一つなのです。
読書なら、一冊しか許されていないと言います。これは『ロビンソン・クルーソー』です。象徴的でしょう。「善き未開人」の再登場です。ここではその良き未開人はエミールですね。
しかし、続いて、エミールは職業を習うべきだと言います。それは、「独立に生計を立てる」ことができるためです。
「わたしはどうしてもエミールに何か職業を学ばせることにしたい。少なくとも何か品のいい職業を(…)えらぶことによう。それにしても、有用性のないところには品もないということをいつも忘れないでおくことにしよう。」
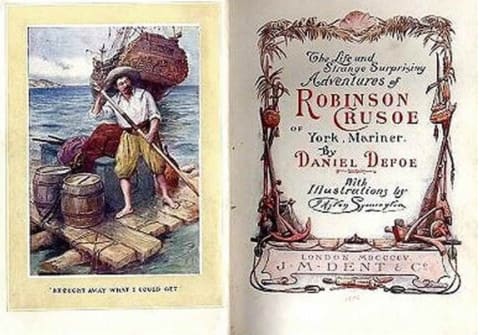
また、いつも同じ繰り返しになります。ルソー論において、「知る」のは有用でなければなりません。そういえば、現代社会では全くその空気です。何かを学ぶときに、「何のために」、「何の役に立てる」とすぐに聞かれるでしょう。例えば、「哲学を学んでいます」、すぐに「何のため?」と。「いや、哲学は何の役に立たない学問だ」。はい、哲学は具体的には何の役にも立たないが、「良く生きるために」役に立ちます。
「何のために?」「何の役立つ?」。近代的な質問です。しいて言えば、他人に奉仕するためとかは論外となっていて、自分の何かの利益がなければやらないといった雰囲気があります。有用性がなければならないということが常識になりつつあります。
現代社会では、役に立たない職業は、好まれていないようです。修道士や一生独身の神父などは何の役に立つでしょうか。具体的に、物質的にいうと、何も役立たないのです。結果、観想系の修道会をつぶそうとする動きが強くなっています。フランシスコ教皇は例えば、近代主義に染まって、観想系の修道会を迫害しています。理由は「社会上、何の役に立たないから」というだけです。
「天主に栄光を捧げる」修道会ですが、それは「役立たない」らしいのです。悲惨なことですが、ルソーらしく有用性を重んじるあまり、とんでもなくなります。
「彼には島にいるロビンソンの役に立ちうるような職業が必要だ。」と言います。

「すべてをよく考えてみると、わたしがいちばん好ましく思う職業で、私の生徒の好みに合っていると思われるのは、指物師の職業だ。それは清潔で、有益で、家の中で仕事をすることができる。それは十分に体をはたらかせ、職人の器用さと工夫を必要とし、用途によって決定される作品の形には、優美さと趣味も排除されてはいない。」
「こうして私たち自身のところに帰ってきた。私たちの子供は、自分という個人を認めて、もう子供ではなくなろうとしている。いま彼は、これまで感じていたよりもずっと痛切に、彼を事物に結び付けている必然を感じている。(12歳から14歳まで)まず彼の体と感官を訓練したあとで、わたしたちは彼の精神と判断力を訓練した。」
なんてね。「精神と判断力」の訓練なんて、何も習っていないのに。それでも、判断力と精神があるようになったとされています。歴史も、言語も、何も習っていないのに、知性は訓練されているみたいです。
「そして彼の手足を用いることを彼の能力を用いることにむすびつけていた。」
これは教育の第二段階と第三段階の関係です。第二段階は体の教育でした。第三段階は精神と判断力だと言います。
「彼を行動し思考する存在につくりあげた。」
つまり、15歳になる前、行動していたかもしれないが何も思考していなかったという意味ですね。ルソーの理想教育です。
「人間として完成させるには、人を愛する感じやすい存在にすること、つまり感情によって理性を完成することだけが残されている。」
要するに、「14歳になる前に、理性などはなかったかのように、まともな感情がなかったかのように」ルソーがいわんばかりです。あり得ないでしょう。
「人間は知れば知るほど誤りをおかすことになるのだから、誤りを避けるただ一つの方法は何も知らないでいることだ。」
これは、最後の方にある引用です。
第三編の最後の部分には、ルソーが若きエミールを描写しています。
「エミールは純粋に物体的な自然についての知識しかもたない。彼は歴史という名詞さえ知らないし、形而上学とか倫理学とかいうものがどういうものがどういうものかも知らない。」
つまり、15歳にもなって、また道徳などは何も知らないということです。
「事物に対する人間の基本的な関係は知っているが、人間対人間の倫理的な関係については何も知らない。」
しいて言えば、エミールは「自然(状態)の人」だということです。
「観念を一般化することはほとんどできないし、抽象化することもほとんどできない。」
ルソーは明白に明かしますね。エミールはほとんど何も知らないって。つまり、エミールはまさに「幸せな馬鹿」です。
「ある種の物体に共通の性質はわかっているが、その性質自体について考えることはしない。」
ちょっと飛ばします。
「エミールはよく働き、節制を守り、忍耐心に富み、健気で、勇気にみちている。けっして燃え上がることのない彼の想像力は、危険を大きくして見せるようなことはない。」
ちょっと飛ばしていたところですが、ルソーはエミールに「一人で闇に行かせたりして」とかありますよ。なんかコツみたいな、完全に無知でありながら、無知ではないかのようにね。まあ。
「死ということについては、それはどういうことかまだよく知らない。」15歳なのに、滑稽ですな。
「しかし、(自然状態に生きているから)反抗せずに必然の掟をうけいれることになれているから、死ななければならないときには、うめき声をあげたり、悶えたりすることもなく、死んでいくだろう。」どうでしょう。
「それがすべての人に恐れられているこの瞬間において自然が許していることのすべてだ。自由に死、人間的なものにあまり執着しないこと、それが死ぬことを学ぶ一番いい方法だ。」
「一言でいえば、エミールは彼自身に関係のある徳はすべてもっている。」
自明でしょう。「彼自身に関係のある」と。いつもこういった個人主義です。
「社会的な徳ももつためには、そういう徳を必要としている関係を知ることだけが残されている。」
それでは、第四編になります。今日は第四編に深く入らないことにしています。なぜかというと、まず第四編は15歳から20歳までですから、成長上の非常に大事な時期です。ルソーは「青春時代」だといっています。で、ルソー論において、その15歳から20歳まで、「人生の物事を教える」ほかに、「心と感情を持つように」教えると言います。
第四編の最初あたり、次の描写があります。
「ところが、私のエミールを見るがいい。私が彼を導いてきた時期には、彼は感じたこともなければ、嘘をついたこともない。」
なんて素直な教育者でしょう。
「彼は、愛することはどういうことか知らないうちに、だれかに「わたしはあなたを本当に愛します」といったことはない。」
つまり、15歳になっても、感情などはまだないという。不思議でしょう。まあ、エミールは孤児だから、愛している親もない当然か。まあ、ルソーの教育を施すために、生徒を厳格に選ばないとできないのですね。
「父親の部屋、母親の部屋、あるいは病気で寝ている教師の部屋にはいるときにはこういうふうにしなさい、などと彼は言いつけられたことはない。感じてもいない悲しみをよそおう技巧を教えられていないからだ。」
感情はないということです。悲しみでさえ感じていないエミール。
「誰が死んでも、それ涙を流したことはない。死ぬとはどういうことか知らないからだ。」
エミールには感情が一切ないのです。なんて理想的な!
「心情が無関心なら、態度も同じように無関心だ。ほかの子供もすべてそうであるように、自分のことのほかには一切関心を持たない彼は、誰にも興味を感じない。」
つまり、ルソーの教育によって、頑固なる「わがまま」を作ったのです。ただ、ルソーに言わせると、その「エゴイストの者」は一応道徳的に振る舞うといっています。15歳ですよ。しかも、何も知識がありません。無知です。
それでも、エミールには15歳から「愛することを教える」ことになると。それでは、ルソー教育論の最後の段階ですが、愛の仕方を教えるということで、他人との関係の持ち方を教えることとされています。
しかしながら、第四編において、エミールは他人と触れ合うことは一度もないのです。第五編になっていよいよ少女ソフィーと出会うことになりますが、いきなり登場する者です。そして、そのソフィーには何の養成・教養・教育はないと。「女性のゆえに当然だ」とルソーがしています。「母になる最低限の知識でよい」としています。
そして、いきなり、ルソーはエミールとソフィーと結婚させます。理由は?ありません。決まったことですから、と。

第四編において、もう一つ指摘しましょう。エミールはいよいよ歴史を習うことになります。15歳になってから。しかしながら、歴史といっても限られた歴史ですよ。ちょっと引用を探してみます。配布していないかと思います。
「青年にとって一番悪い歴史家は判断を下している歴史家だ。」(中・64頁)
繰り返します。「青年にとって一番悪い歴史家は判断を下している歴史家だ。事実を!事実を!そして生徒自身に判断させるのだ。」
つまり、ルソーにとって良い歴史家は、事実だけを取り上げて、判断を下すことは一度もないということです。で、プルタルコスはいいとルソーが判断しますから、エミールはプルタルコスを読むことになります。
また、一応、個人の人生についての本を読んでも良いと。まあ、もちろん、聖人の人生ではないのですが、一般人の人生ならいいと。 ・・・続く
※この公教要理は、 白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんのご協力とご了承を得て、多くの皆様の利益のために書き起こしをアップしております
Billecocq神父に哲学の講話を聴きましょう
ルソーは「地理学」ならちょっとでもやるといいといっています。というのも、地理学だと、周りの世界に基づいているからやっても良い学問だといっています。ただ、非常に手軽に限定的にやるべきだと。遊べる近くの川と芝生ぐらいを教えるだけでよい、まあ、ちょっと大げさに言ってみましたが、原文を見るとほとんど大げさに言っているわけでもありません。
というのも、ルソーが問題にしているのは、近くだけの地理学ではないのなら、地球模型を差し出す必要が出てしまい、そしてそれは「人工的な」段ボールの模型だからけしからんというのがルソーのスタンスです。本物の地球ではないから、地理学を習ってはいけないというロジックです。
歴史はダメ。言語学はダメ。死語ならなおさらのことだと言いますが、いつもラテン語で引用しているルソーなのになあ。これは、ルソーの多くの矛盾の一つなのです。
読書なら、一冊しか許されていないと言います。これは『ロビンソン・クルーソー』です。象徴的でしょう。「善き未開人」の再登場です。ここではその良き未開人はエミールですね。
しかし、続いて、エミールは職業を習うべきだと言います。それは、「独立に生計を立てる」ことができるためです。
「わたしはどうしてもエミールに何か職業を学ばせることにしたい。少なくとも何か品のいい職業を(…)えらぶことによう。それにしても、有用性のないところには品もないということをいつも忘れないでおくことにしよう。」
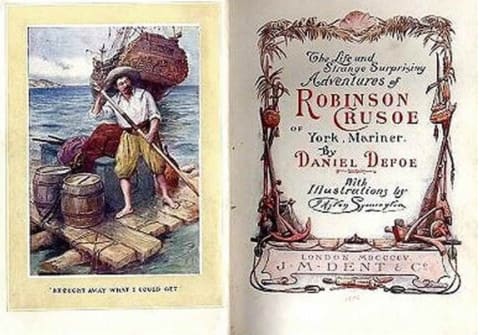
また、いつも同じ繰り返しになります。ルソー論において、「知る」のは有用でなければなりません。そういえば、現代社会では全くその空気です。何かを学ぶときに、「何のために」、「何の役に立てる」とすぐに聞かれるでしょう。例えば、「哲学を学んでいます」、すぐに「何のため?」と。「いや、哲学は何の役に立たない学問だ」。はい、哲学は具体的には何の役にも立たないが、「良く生きるために」役に立ちます。
「何のために?」「何の役立つ?」。近代的な質問です。しいて言えば、他人に奉仕するためとかは論外となっていて、自分の何かの利益がなければやらないといった雰囲気があります。有用性がなければならないということが常識になりつつあります。
現代社会では、役に立たない職業は、好まれていないようです。修道士や一生独身の神父などは何の役に立つでしょうか。具体的に、物質的にいうと、何も役立たないのです。結果、観想系の修道会をつぶそうとする動きが強くなっています。フランシスコ教皇は例えば、近代主義に染まって、観想系の修道会を迫害しています。理由は「社会上、何の役に立たないから」というだけです。
「天主に栄光を捧げる」修道会ですが、それは「役立たない」らしいのです。悲惨なことですが、ルソーらしく有用性を重んじるあまり、とんでもなくなります。
「彼には島にいるロビンソンの役に立ちうるような職業が必要だ。」と言います。

「すべてをよく考えてみると、わたしがいちばん好ましく思う職業で、私の生徒の好みに合っていると思われるのは、指物師の職業だ。それは清潔で、有益で、家の中で仕事をすることができる。それは十分に体をはたらかせ、職人の器用さと工夫を必要とし、用途によって決定される作品の形には、優美さと趣味も排除されてはいない。」
「こうして私たち自身のところに帰ってきた。私たちの子供は、自分という個人を認めて、もう子供ではなくなろうとしている。いま彼は、これまで感じていたよりもずっと痛切に、彼を事物に結び付けている必然を感じている。(12歳から14歳まで)まず彼の体と感官を訓練したあとで、わたしたちは彼の精神と判断力を訓練した。」
なんてね。「精神と判断力」の訓練なんて、何も習っていないのに。それでも、判断力と精神があるようになったとされています。歴史も、言語も、何も習っていないのに、知性は訓練されているみたいです。
「そして彼の手足を用いることを彼の能力を用いることにむすびつけていた。」
これは教育の第二段階と第三段階の関係です。第二段階は体の教育でした。第三段階は精神と判断力だと言います。
「彼を行動し思考する存在につくりあげた。」
つまり、15歳になる前、行動していたかもしれないが何も思考していなかったという意味ですね。ルソーの理想教育です。
「人間として完成させるには、人を愛する感じやすい存在にすること、つまり感情によって理性を完成することだけが残されている。」
要するに、「14歳になる前に、理性などはなかったかのように、まともな感情がなかったかのように」ルソーがいわんばかりです。あり得ないでしょう。
「人間は知れば知るほど誤りをおかすことになるのだから、誤りを避けるただ一つの方法は何も知らないでいることだ。」
これは、最後の方にある引用です。
第三編の最後の部分には、ルソーが若きエミールを描写しています。
「エミールは純粋に物体的な自然についての知識しかもたない。彼は歴史という名詞さえ知らないし、形而上学とか倫理学とかいうものがどういうものがどういうものかも知らない。」
つまり、15歳にもなって、また道徳などは何も知らないということです。
「事物に対する人間の基本的な関係は知っているが、人間対人間の倫理的な関係については何も知らない。」
しいて言えば、エミールは「自然(状態)の人」だということです。
「観念を一般化することはほとんどできないし、抽象化することもほとんどできない。」
ルソーは明白に明かしますね。エミールはほとんど何も知らないって。つまり、エミールはまさに「幸せな馬鹿」です。
「ある種の物体に共通の性質はわかっているが、その性質自体について考えることはしない。」
ちょっと飛ばします。
「エミールはよく働き、節制を守り、忍耐心に富み、健気で、勇気にみちている。けっして燃え上がることのない彼の想像力は、危険を大きくして見せるようなことはない。」
ちょっと飛ばしていたところですが、ルソーはエミールに「一人で闇に行かせたりして」とかありますよ。なんかコツみたいな、完全に無知でありながら、無知ではないかのようにね。まあ。
「死ということについては、それはどういうことかまだよく知らない。」15歳なのに、滑稽ですな。
「しかし、(自然状態に生きているから)反抗せずに必然の掟をうけいれることになれているから、死ななければならないときには、うめき声をあげたり、悶えたりすることもなく、死んでいくだろう。」どうでしょう。
「それがすべての人に恐れられているこの瞬間において自然が許していることのすべてだ。自由に死、人間的なものにあまり執着しないこと、それが死ぬことを学ぶ一番いい方法だ。」
「一言でいえば、エミールは彼自身に関係のある徳はすべてもっている。」
自明でしょう。「彼自身に関係のある」と。いつもこういった個人主義です。
「社会的な徳ももつためには、そういう徳を必要としている関係を知ることだけが残されている。」
それでは、第四編になります。今日は第四編に深く入らないことにしています。なぜかというと、まず第四編は15歳から20歳までですから、成長上の非常に大事な時期です。ルソーは「青春時代」だといっています。で、ルソー論において、その15歳から20歳まで、「人生の物事を教える」ほかに、「心と感情を持つように」教えると言います。
第四編の最初あたり、次の描写があります。
「ところが、私のエミールを見るがいい。私が彼を導いてきた時期には、彼は感じたこともなければ、嘘をついたこともない。」
なんて素直な教育者でしょう。
「彼は、愛することはどういうことか知らないうちに、だれかに「わたしはあなたを本当に愛します」といったことはない。」
つまり、15歳になっても、感情などはまだないという。不思議でしょう。まあ、エミールは孤児だから、愛している親もない当然か。まあ、ルソーの教育を施すために、生徒を厳格に選ばないとできないのですね。
「父親の部屋、母親の部屋、あるいは病気で寝ている教師の部屋にはいるときにはこういうふうにしなさい、などと彼は言いつけられたことはない。感じてもいない悲しみをよそおう技巧を教えられていないからだ。」
感情はないということです。悲しみでさえ感じていないエミール。
「誰が死んでも、それ涙を流したことはない。死ぬとはどういうことか知らないからだ。」
エミールには感情が一切ないのです。なんて理想的な!
「心情が無関心なら、態度も同じように無関心だ。ほかの子供もすべてそうであるように、自分のことのほかには一切関心を持たない彼は、誰にも興味を感じない。」
つまり、ルソーの教育によって、頑固なる「わがまま」を作ったのです。ただ、ルソーに言わせると、その「エゴイストの者」は一応道徳的に振る舞うといっています。15歳ですよ。しかも、何も知識がありません。無知です。
それでも、エミールには15歳から「愛することを教える」ことになると。それでは、ルソー教育論の最後の段階ですが、愛の仕方を教えるということで、他人との関係の持ち方を教えることとされています。
しかしながら、第四編において、エミールは他人と触れ合うことは一度もないのです。第五編になっていよいよ少女ソフィーと出会うことになりますが、いきなり登場する者です。そして、そのソフィーには何の養成・教養・教育はないと。「女性のゆえに当然だ」とルソーがしています。「母になる最低限の知識でよい」としています。
そして、いきなり、ルソーはエミールとソフィーと結婚させます。理由は?ありません。決まったことですから、と。

第四編において、もう一つ指摘しましょう。エミールはいよいよ歴史を習うことになります。15歳になってから。しかしながら、歴史といっても限られた歴史ですよ。ちょっと引用を探してみます。配布していないかと思います。
「青年にとって一番悪い歴史家は判断を下している歴史家だ。」(中・64頁)
繰り返します。「青年にとって一番悪い歴史家は判断を下している歴史家だ。事実を!事実を!そして生徒自身に判断させるのだ。」
つまり、ルソーにとって良い歴史家は、事実だけを取り上げて、判断を下すことは一度もないということです。で、プルタルコスはいいとルソーが判断しますから、エミールはプルタルコスを読むことになります。
また、一応、個人の人生についての本を読んでも良いと。まあ、もちろん、聖人の人生ではないのですが、一般人の人生ならいいと。 ・・・続く









