対面朗読のスキルアップ講座で、二人の先生に教わりましたが
このお二方が全く違うタイプだったので、
なかなか、興味深いものがありました。
技術的なことはともかく、誰かに何かを「教える」とき
どういうことを念頭においているかということですが
大抵の先生は「教わる」側の気持ちには立てず
「教える」ことばかりに気がいっているのではないでしょうか。
具体的にいうと、何か実習したときの指導で
「こういうところが良かった」とまず認め
受講者が安心して注意を受け入れる気持ちになったところで
「でも、こことここに気をつけていくともっと良い」
というような方法を意識する先生は少ないのではないでしょうか。
どちらかというと、悪いところだけ指摘して、ここを直しましょう!
という指導法が多いように思います。
(べつに受講者に媚びることはありませんが)
いろいろ自分の子育ては反省することばかりですが
(ときに懺悔もあり
 )
)
子どもは常にこの「教わる」立場にいるのだと思うと
もっともっと良いところを見つけて、口に出して褒め、
充分に認められていることが
子ども自身にわかるようにしてあげないとなぁ

などと、思ったのでした。

このお二方が全く違うタイプだったので、
なかなか、興味深いものがありました。
技術的なことはともかく、誰かに何かを「教える」とき
どういうことを念頭においているかということですが
大抵の先生は「教わる」側の気持ちには立てず
「教える」ことばかりに気がいっているのではないでしょうか。
具体的にいうと、何か実習したときの指導で
「こういうところが良かった」とまず認め
受講者が安心して注意を受け入れる気持ちになったところで
「でも、こことここに気をつけていくともっと良い」
というような方法を意識する先生は少ないのではないでしょうか。
どちらかというと、悪いところだけ指摘して、ここを直しましょう!
という指導法が多いように思います。
(べつに受講者に媚びることはありませんが)
いろいろ自分の子育ては反省することばかりですが
(ときに懺悔もあり

 )
)子どもは常にこの「教わる」立場にいるのだと思うと
もっともっと良いところを見つけて、口に出して褒め、
充分に認められていることが
子ども自身にわかるようにしてあげないとなぁ


などと、思ったのでした。












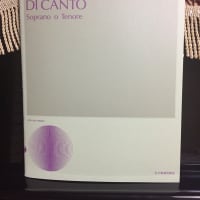
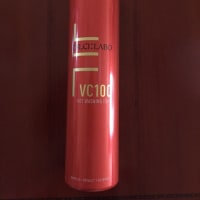

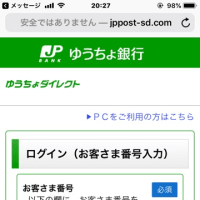
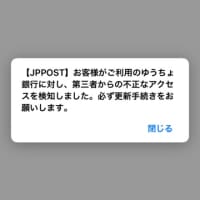





ついつい短絡的に悪いところのみを指摘しがちです(反省)。
親サイドが、こどもの良い部分を発見・理解はしていても、
それを「親はわかっているのよ」とこどもに伝える努力はしてなかったです。
やはり、(良い)思いは口に出さないとねぇ~。
それが結構苦手です
口に出しては言っていないと思います。
そのこのいいところも、「言わなくてもわかってるでしょ」と
思っていますよね。
でも子どもは、子どものきもちはどうなのかな?
意外に、伝わっていないかも?
とわたしは思うことがあります。