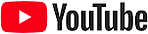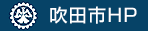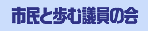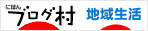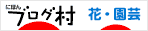未来にまっすぐ、市政にまっすぐ。まっすぐな人、池渕佐知子。無党派、市民派の前吹田市議会議員です。
未来にまっすぐ(池渕 佐知子のブログ)
政務調査費の会計
お昼前から市役所に行き、年末から溜まっていた政務調査費の会計処理を行いました。
政務調査費や応援団の会計や議員報酬の会計、また家計簿、いろいろ会計をつけているのですが、まとまった時間でじっくり、没頭して計算したり、帳簿をつけたり、伝票を作成したりしないと、わけがわからなくなってしまいます。
それでも、ようやく会計処理がまとまったので、やれやれです。
次は、応援団会計をまとめなきゃ。
政務調査費や応援団の会計や議員報酬の会計、また家計簿、いろいろ会計をつけているのですが、まとまった時間でじっくり、没頭して計算したり、帳簿をつけたり、伝票を作成したりしないと、わけがわからなくなってしまいます。
それでも、ようやく会計処理がまとまったので、やれやれです。
次は、応援団会計をまとめなきゃ。
コメント(0)|Trackback()
21世紀の科学技術
阪大中之島センターで開催された環境リスクに関する研修会に出席しました。
講師は私の出身である阪大薬学部の平田教授で、「光合成生物の機能を利用した環境修復と食料増産」というテーマで講義と質疑で2時間ありました。
まずイントロダクションとして、21世紀の科学技術は環境保護と調和を保ちつつ、持続的な発展を保証するものでなければならない。だから、環境保全、環境管理、環境修復におけるバイオテクノロジーの活用が重要であるということです。
植物は動物と違い動けないので(だから動物とは言わないのだけれど)もし環境ストレスがかかっても、動いて逃げるわけにはいきません。だから、環境ストレスに耐える(耐性の獲得)、環境ストレスへの防御機能の発現、環境ストレスによる生物活性物質の生産がおこるという話でした。
そして、この植物の環境ストレスに対する反応を解析することによって、医療(医薬品原料、診断薬、予防薬)、環境(汚染物質浄化、汚染物質センサー、砂漠緑化)、食品・食料生産(高機能健康食品、安全な組み換え植物、環境調和型農薬)への応用、さらに実用化を考えていきたいという話でした。
これらの中で実際に実用化しているのは、ビスフェノールA(環境ホルモン)の浄化に有用とされている植物(ポーチュラカ)の販売ぐらいで、あとは、実用化に向けて試験プラントを海外で行っている緑藻を用いた余剰バイオマスを原料とする乳酸生産とのことでした。
講義の中身は化学式やDNA解析や濃度反応曲線グラフなど、まるで学生時代に戻ったような気分でした。(と言っても、私が学んだ頃よりもずっと高度な研究内容になっていますが)
平田教授が最後に、「研究者は実用化とか考えずに研究のための研究をしがちで、研究と実用化との間には大きなギャップがあるが、実用化を考えない研究ではなく、実用化を見据えた研究をしていきたい」と言われたと記憶しています。そういう繋ぐ役割が大事で、求められているのだろうなぁと思いました。
何事もそうですよね。理論と実践。理想と現実。その間は大きく深いけれど、それを繋ぐ人がいるから、前に進んでいくのだと思います。
講師は私の出身である阪大薬学部の平田教授で、「光合成生物の機能を利用した環境修復と食料増産」というテーマで講義と質疑で2時間ありました。
まずイントロダクションとして、21世紀の科学技術は環境保護と調和を保ちつつ、持続的な発展を保証するものでなければならない。だから、環境保全、環境管理、環境修復におけるバイオテクノロジーの活用が重要であるということです。
植物は動物と違い動けないので(だから動物とは言わないのだけれど)もし環境ストレスがかかっても、動いて逃げるわけにはいきません。だから、環境ストレスに耐える(耐性の獲得)、環境ストレスへの防御機能の発現、環境ストレスによる生物活性物質の生産がおこるという話でした。
そして、この植物の環境ストレスに対する反応を解析することによって、医療(医薬品原料、診断薬、予防薬)、環境(汚染物質浄化、汚染物質センサー、砂漠緑化)、食品・食料生産(高機能健康食品、安全な組み換え植物、環境調和型農薬)への応用、さらに実用化を考えていきたいという話でした。
これらの中で実際に実用化しているのは、ビスフェノールA(環境ホルモン)の浄化に有用とされている植物(ポーチュラカ)の販売ぐらいで、あとは、実用化に向けて試験プラントを海外で行っている緑藻を用いた余剰バイオマスを原料とする乳酸生産とのことでした。
講義の中身は化学式やDNA解析や濃度反応曲線グラフなど、まるで学生時代に戻ったような気分でした。(と言っても、私が学んだ頃よりもずっと高度な研究内容になっていますが)
平田教授が最後に、「研究者は実用化とか考えずに研究のための研究をしがちで、研究と実用化との間には大きなギャップがあるが、実用化を考えない研究ではなく、実用化を見据えた研究をしていきたい」と言われたと記憶しています。そういう繋ぐ役割が大事で、求められているのだろうなぁと思いました。
何事もそうですよね。理論と実践。理想と現実。その間は大きく深いけれど、それを繋ぐ人がいるから、前に進んでいくのだと思います。
コメント(0)|Trackback()
1月18日から25日までの予定
18日(日)10時~17時 環境リスクマネジメント講義(中之島)
18時半~ 吹田市薬剤師会新年互礼会(千里中央)
19日(月) 10時~16時 千里山まちかどサロン
13時半~15時半 おしゃべり・カフェ
参加費(お茶代)100円です。どなたでもご参加いただけます。
市政のこと、まちのこと、いろんなことおしゃべりしましょう。
19時~21時 環境リスクマネジメント講義(中之島)
20日(火) 15時~ 私用で外出
21日(水) 10時~ 編纂委員会(議会)
18時~ 新年互礼会(万博公園)
22日(木) 10時~16時 まちかどサロン(千里山まちかどサロン)
23日(金) 10時~16時 ソーイング・カフェ(千里山まちかどサロン)
18時半~ 地域コーディネーター懇親会(江坂)
24日(土) 15時~17時 応援団運営会(千里山まちかどサロン)
25日(日)
18時半~ 吹田市薬剤師会新年互礼会(千里中央)
19日(月) 10時~16時 千里山まちかどサロン
13時半~15時半 おしゃべり・カフェ
参加費(お茶代)100円です。どなたでもご参加いただけます。
市政のこと、まちのこと、いろんなことおしゃべりしましょう。
19時~21時 環境リスクマネジメント講義(中之島)
20日(火) 15時~ 私用で外出
21日(水) 10時~ 編纂委員会(議会)
18時~ 新年互礼会(万博公園)
22日(木) 10時~16時 まちかどサロン(千里山まちかどサロン)
23日(金) 10時~16時 ソーイング・カフェ(千里山まちかどサロン)
18時半~ 地域コーディネーター懇親会(江坂)
24日(土) 15時~17時 応援団運営会(千里山まちかどサロン)
25日(日)
コメント(0)|Trackback()
環境リスク講義
昨年春から受講している、環境リスクマネジメントの講義を朝から夜まで一日びっしり勉強しました。
今日は10時から13時まで「建設分野の環境への取り組み」と題して鹿島建設の環境本部長塚田さんのお話。
鹿島建設では環境方針として4つの重点項目を決めており
1.資源循環・有効利用
2.地球温暖化防止
3.有害物の管理
4.生態系の保全 とのことです。
また、さすが民間企業ということでしょうか。
環境を守るのは当然のこととだが、「財」が回らないといけないので、ビジネスになるものは積極的にやっていこうと思っているとのことでした。
とくに今日は土壌汚染についての鹿島の取り組み(ビジネス)について事例を含めて教えていただき、いくら汚染対策をきちんとしたとしても、情報の提供をどの時点でどのように、誰に対して行うか、など、リスクコミュニケーションが重要だということを教えていただきました。
2講目は、東電工業株式会社の顧問をされている初鹿さんが「電気事業における環境リスク管理」ということで、エネルギー問題と電気事業、地球温暖化問題とその対応について話していただきました。
今、2050年にCO2排出量を現状から半減させるという世界的な長期目標がありますが、今の状態ではCO2排出量は現在の2倍以上になると言われているので、2倍になるものを2分の1にするためには、先進国の排出量をほとんどゼロにして、かつ、発展途上国も現状よりも減らす必要があるということになり、到底、達成できないと考えられます。
でも、だからといって、いまのまま何もせずに手をこまねいていて、地球環境が徹底的に壊れてしまっては取り返しがつきません。
地球温暖化問題に関する日本の産業界の主張としては
日本の役割は下記の3点にあるとのことでした。
1.エネルギー資源に乏しい日本は、経済成長、エネルギー安定供給、環境保全の同時達成が最重要
2.低炭素社会の実現の鍵となる「原子力」「省エネルギー」「再生可能エネルギー」の具体的な推進が不可欠
3.技術こそが温暖化から地球を救う。
・世界最高水準のエネルギー効率の更なる向上
・日本の優れた省エネ・環境技術の途上国への移転・普及
・革新的な技術開発の促進
吹田市も環境世界都市を目指しています。今後、どのような先進的な取り組みを吹田市でも実現していけるか、見届けたいですし、提案していきたいと思います。
今日は10時から13時まで「建設分野の環境への取り組み」と題して鹿島建設の環境本部長塚田さんのお話。
鹿島建設では環境方針として4つの重点項目を決めており
1.資源循環・有効利用
2.地球温暖化防止
3.有害物の管理
4.生態系の保全 とのことです。
また、さすが民間企業ということでしょうか。
環境を守るのは当然のこととだが、「財」が回らないといけないので、ビジネスになるものは積極的にやっていこうと思っているとのことでした。
とくに今日は土壌汚染についての鹿島の取り組み(ビジネス)について事例を含めて教えていただき、いくら汚染対策をきちんとしたとしても、情報の提供をどの時点でどのように、誰に対して行うか、など、リスクコミュニケーションが重要だということを教えていただきました。
2講目は、東電工業株式会社の顧問をされている初鹿さんが「電気事業における環境リスク管理」ということで、エネルギー問題と電気事業、地球温暖化問題とその対応について話していただきました。
今、2050年にCO2排出量を現状から半減させるという世界的な長期目標がありますが、今の状態ではCO2排出量は現在の2倍以上になると言われているので、2倍になるものを2分の1にするためには、先進国の排出量をほとんどゼロにして、かつ、発展途上国も現状よりも減らす必要があるということになり、到底、達成できないと考えられます。
でも、だからといって、いまのまま何もせずに手をこまねいていて、地球環境が徹底的に壊れてしまっては取り返しがつきません。
地球温暖化問題に関する日本の産業界の主張としては
日本の役割は下記の3点にあるとのことでした。
1.エネルギー資源に乏しい日本は、経済成長、エネルギー安定供給、環境保全の同時達成が最重要
2.低炭素社会の実現の鍵となる「原子力」「省エネルギー」「再生可能エネルギー」の具体的な推進が不可欠
3.技術こそが温暖化から地球を救う。
・世界最高水準のエネルギー効率の更なる向上
・日本の優れた省エネ・環境技術の途上国への移転・普及
・革新的な技術開発の促進
吹田市も環境世界都市を目指しています。今後、どのような先進的な取り組みを吹田市でも実現していけるか、見届けたいですし、提案していきたいと思います。
コメント(0)|Trackback()
吹田市郷土史研究会の総会
 吹田市生まれの吹田市育ちではありませんが、これまで生きてきた人生の半分以上を吹田市で過ごしている私として、吹田市の歴史や文化を知りたい、学びたいと思っています。
吹田市生まれの吹田市育ちではありませんが、これまで生きてきた人生の半分以上を吹田市で過ごしている私として、吹田市の歴史や文化を知りたい、学びたいと思っています。それで数年前から吹田市郷土史研究会のメンバーに入れていただいています。
毎年、1月に総会と新年会を兼ねてメイシアターのレセプションホールで開かれます。今年も参加させていただきました。
総会だけでなく講演会や出し物もあります。今年の出し物は権六踊りでした。
この踊りは、歌い継がれてきた民謡に振りをつけたものとのことです。
コメント(0)|Trackback()
リスク管理学 集中講義
今日の夜3時間、明日6時間、明後日6時間の連続3日間で、リスク管理学の集中講義があります。たいていの講義は隔週1回ずつの受講なので、身体は楽ですが、頭は前に教えていただいたのが次に抜けていたりしています。
今回は、集中講義なので、体力も頭も大丈夫かな? ちょっと心配です。
さて、今日の講義は、リスクって何? 環境リスクって何? 危険とリスクの違いは? というようなオリエンテーション的、これまでいろいろ学んできたことのおさらい的な講義でした。
危険とリスクの違いってわかりますか?
危険は、たとえば「頭の上から物が落ちてきた」みたいに自分が何かをしたから起こるというものではなく、外界からもたらされるもので、自分ではコントロールできません。
リスクは、たとえば「建設現場を歩いているときに、上から物が落ちてくるリスク」というように、上から物が落ちてくる確率とそれによって生じる被害の大きさで表されます。
「建設現場を抜けると近道になる」「建設現場を抜けると物が落ちてくるかもしれない」という2つの中から、「建築現場を歩く」という意思決定をしたために、物が落ちてくるリスクが生じることになります。
ですから、リスクは大きさで表現でき、対比でき、影響を受ける主体があり、対策によって減らすこともできる(コントロールできる)ものなのです。
私は環境リスクマネジメントを学んでいるのですが、環境に限らずリスクはどこにでもあります。そのリスクを最小限にするためのマネジメントを学ぶことで、議員活動にも応用できるのではないかと考えています。
でも、まだまだ具体的には使えていませんけどね。
今回は、集中講義なので、体力も頭も大丈夫かな? ちょっと心配です。
さて、今日の講義は、リスクって何? 環境リスクって何? 危険とリスクの違いは? というようなオリエンテーション的、これまでいろいろ学んできたことのおさらい的な講義でした。
危険とリスクの違いってわかりますか?
危険は、たとえば「頭の上から物が落ちてきた」みたいに自分が何かをしたから起こるというものではなく、外界からもたらされるもので、自分ではコントロールできません。
リスクは、たとえば「建設現場を歩いているときに、上から物が落ちてくるリスク」というように、上から物が落ちてくる確率とそれによって生じる被害の大きさで表されます。
「建設現場を抜けると近道になる」「建設現場を抜けると物が落ちてくるかもしれない」という2つの中から、「建築現場を歩く」という意思決定をしたために、物が落ちてくるリスクが生じることになります。
ですから、リスクは大きさで表現でき、対比でき、影響を受ける主体があり、対策によって減らすこともできる(コントロールできる)ものなのです。
私は環境リスクマネジメントを学んでいるのですが、環境に限らずリスクはどこにでもあります。そのリスクを最小限にするためのマネジメントを学ぶことで、議員活動にも応用できるのではないかと考えています。
でも、まだまだ具体的には使えていませんけどね。
コメント(0)|Trackback()
マイバッグ一万人宣言署名カード
秋に北千里の池めぐりをした様子などを掲載した応援団ニュースができました。
今日はサロンの日でしたので、編集担当の方と一緒にニュースの印刷や紙折りや封筒入れをして、発送作業を行いました。
応援団の方といつも市議会通信を配布していただいている方に送らせていただきました。(ちょっとミスをしてしまって、まだ送れていない方がいます。ごめんなさい)
また、2月14日(土)10時からメイシアターの第1会議室で応援団総会を開きますので、そのご案内も入れました。応援団に入っておられない方で、入ろうかな?って思われる方は一度オブザーバー参加してみてください。
それからそれから、私が所属しているアジェンダ21すいたの資源部会が他の団体と一緒に作っているレジ袋を減らしましょうという団体のお知らせも同封しました。
「レジ袋をできるだけもらわないようにします」という意見表明をしていただくために署名をしてもらう「マイバッグ一万人宣言署名カード」を同封しています。
「レジ袋削減→スーパーはレジ袋作る必要なし→スーパー助かる」って思うと、なんかスーパーのためにしているみたいな気にならないこともないですが、
たかがレジ袋、されどレジ袋です。
レジ袋を削減することでごみがその分減るということもありますが、そういう直接的なことよりも、少しでもできるところからごみを減らそうという意識改革ということが大きな意味があると、私は思います。
これは3月までに1万人の署名カードを集めようとしているものですが、まだまだ1万人には遠いそうです。
ご関心のある方は市役所の環境部地球環境課や減量推進課に署名カードがありますし、私に言ってくださればお渡しします。ぜひ、お友達にも広めてください。
よろしくお願いします。
今日はサロンの日でしたので、編集担当の方と一緒にニュースの印刷や紙折りや封筒入れをして、発送作業を行いました。
応援団の方といつも市議会通信を配布していただいている方に送らせていただきました。(ちょっとミスをしてしまって、まだ送れていない方がいます。ごめんなさい)
また、2月14日(土)10時からメイシアターの第1会議室で応援団総会を開きますので、そのご案内も入れました。応援団に入っておられない方で、入ろうかな?って思われる方は一度オブザーバー参加してみてください。
それからそれから、私が所属しているアジェンダ21すいたの資源部会が他の団体と一緒に作っているレジ袋を減らしましょうという団体のお知らせも同封しました。
「レジ袋をできるだけもらわないようにします」という意見表明をしていただくために署名をしてもらう「マイバッグ一万人宣言署名カード」を同封しています。
「レジ袋削減→スーパーはレジ袋作る必要なし→スーパー助かる」って思うと、なんかスーパーのためにしているみたいな気にならないこともないですが、
たかがレジ袋、されどレジ袋です。
レジ袋を削減することでごみがその分減るということもありますが、そういう直接的なことよりも、少しでもできるところからごみを減らそうという意識改革ということが大きな意味があると、私は思います。
これは3月までに1万人の署名カードを集めようとしているものですが、まだまだ1万人には遠いそうです。
ご関心のある方は市役所の環境部地球環境課や減量推進課に署名カードがありますし、私に言ってくださればお渡しします。ぜひ、お友達にも広めてください。
よろしくお願いします。
コメント(0)|Trackback()
エコセン定例会
夜は、今年初めてのエコセンの会議。
エコセンというのはアジェンダ21すいたの広報担当の名称で、エコロジーと宣伝の合成語です。
1月25日発行予定のニュース原稿について校正作業を行いました。
昨年10月から始まっているFM千里でのアジェンダ21すいたの出演の様子も掲載しています。
ニュースをご覧になりたい方は、年会費1000円のアジェンダ21すいたの会員になっていただくのがいちばんありがたいですが、会員になる前にニュースを見たいなぁとおっしゃる方は、環境部地球環境課にありますから、声をかけてください。
また、アジェンダ21すいたのホームページからもこれまでのニュースをご覧いただくことができます。
余談ですけど、午前中は市民病院の耳鼻咽喉科に行ってきました。
実は、昨年お盆のころ、首の前の部分が痛くなって、もしかしたらガン?なんてびっくりして見てもらいました。
結果は、逆流性食道炎で喉仏の周りまで胃液の逆流で赤くなっていたためで、胃酸を押さえる薬を1月ほど飲んで、赤味がほぼ消えたので、経過観察しましょうということになっていたのです。
今日見ていただくと、すっかり治っていたので、「また、もし痛くなったらきてくださいね」ということで、一応完治でした。
夏ごろ、胃の調子が悪かったのと、疲れ気味で食べたらすぐに横になっていたのが悪かったみたいです。座っていると胃酸が喉まで上がってきにくいけれど、横になっていると簡単にあがってくるそうなんです。
みなさんも、疲れて胃の調子が悪いときは、食べた後30分~1時間ぐらいは横になりたくても我慢したほうがいいですよ。
エコセンというのはアジェンダ21すいたの広報担当の名称で、エコロジーと宣伝の合成語です。
1月25日発行予定のニュース原稿について校正作業を行いました。
昨年10月から始まっているFM千里でのアジェンダ21すいたの出演の様子も掲載しています。
ニュースをご覧になりたい方は、年会費1000円のアジェンダ21すいたの会員になっていただくのがいちばんありがたいですが、会員になる前にニュースを見たいなぁとおっしゃる方は、環境部地球環境課にありますから、声をかけてください。
また、アジェンダ21すいたのホームページからもこれまでのニュースをご覧いただくことができます。
余談ですけど、午前中は市民病院の耳鼻咽喉科に行ってきました。
実は、昨年お盆のころ、首の前の部分が痛くなって、もしかしたらガン?なんてびっくりして見てもらいました。
結果は、逆流性食道炎で喉仏の周りまで胃液の逆流で赤くなっていたためで、胃酸を押さえる薬を1月ほど飲んで、赤味がほぼ消えたので、経過観察しましょうということになっていたのです。
今日見ていただくと、すっかり治っていたので、「また、もし痛くなったらきてくださいね」ということで、一応完治でした。
夏ごろ、胃の調子が悪かったのと、疲れ気味で食べたらすぐに横になっていたのが悪かったみたいです。座っていると胃酸が喉まで上がってきにくいけれど、横になっていると簡単にあがってくるそうなんです。
みなさんも、疲れて胃の調子が悪いときは、食べた後30分~1時間ぐらいは横になりたくても我慢したほうがいいですよ。
コメント(0)|Trackback()
吹田市成人祭
 今日も昨日に引き続き快晴。でも晴れているので、よけいに空気が澄んでいて、冷え込みは強いです。
今日も昨日に引き続き快晴。でも晴れているので、よけいに空気が澄んでいて、冷え込みは強いです。10時半過ぎからメイシアターで成人祭が始まりました。
今年は下の息子が成人なので、昨夜のうちに「スーツとか靴とか用意しておきなさいよ」と言ってたのに、今朝になってから「やっぱりベルトがない」「靴はどこ?」ってな感じで、私も出かけなきゃいけないのに~とバタバタ。
結局、開催時間ギリギリにメイシアター大ホールに駆け込みました。
新成人の大ホール入場が結構もたもたしていたので、十分間に合いましたが、危ないところでした。
さて、今年の新成人対象者は3449人とのことで、男性1839人、女性1610人と、ここずっと女性のほうが少ないですね。
今年の運営実行委員さんたちのアイデアなのか、オープニングに吹田のまちの様子、生まれてから20歳になるまでの世界や日本の出来事、小学校や中学校のときの先生からのメッセージ、実行委員さんの二十歳になったメッセージ、先輩からのメッセージと映像で流れました。なかなか良かったです。
テレビや新聞では沖縄などで成人式が荒れたと書かれていましたが、吹田の場合は、少しざわついたりしていましたが、みんなマナーもほどよく、拍手もきちんとするし、落ち着いていたと思います。
式典終了後、外に出ると、ホールにも入りきれなかった新成人たちがたくさんいました。男性の羽織袴姿、シルバーの燕尾服、女性の振袖姿、びっくりしたのは肩を広く開けて着物を着ている女性がいたこと。また、ベビーカーに子どもを乗せて参加していた若い夫婦。一升瓶を持って歩いている男性も見ましたが、とくに混乱もなく終わったみたいです。
息子は同級生の友達に出会えたようで、午後1時ぐらいまではメイシアターで他に友達が来ていないか探したりして、後はまたお昼を一緒に食べてあそびに行ったとかで、夜になってようやく帰ってきました。
でも、若いときだからこそできることだから、精一杯このときを愉しんでくれたらいいなぁと思っています。
ただ、昨年、成人式を待つことなく19歳で亡くなった友人の息子さんのことを思うと、今日の成人式のニュースをどんな気持ちで見ておられるのかなぁ、お辛いだろうなぁと、なんだか申し訳なく思いました。
コメント(0)|Trackback()
出初式
 朝から快晴の日曜日。
朝から快晴の日曜日。例年通り、神崎川右岸河川敷(南高浜橋のたもと)で吹田市消防出初式がありました。
今年は財政総務委員長をしているので、来賓席に座っての出席です。
陽射しはあたたかいのですが、川面を吹く風が強く、カイロを貼って座っていてもしんしんと冷えてきます。温かいお茶をいただきましたが、置いているうちにすぐに冷たいお茶になってしまいました。
10時からの開催で、時間通り、分列行進、ヘリコプターからの消防庁長官メッセージの投下、と進んでいきました。
市長式辞、来賓(議長)祝辞があったのち、これも例年通り救助訓練があり、レスキュー隊員による高い場所でのバランスなど、高所恐怖症の私としては見ているだけでビクビクしてしまいます。
その後、一斉放水が行われ、出初式は滞りなく終わりました。
式典の後、希望者には「消防自動車をバックに写真撮影できますよ」とのアナウンスが流れ、子ども連れの市民の皆さんは消防車のほうに急いで行かれました。
出初式(式典)ですから堅苦しいところもありますが、こんなふうに市民が消防というものに身近に触れ合うことができるのは、とてもいいことだと思いました。
昨年は不審火による吉志部神社の焼失がありましたが、今年は大きな火事がないように願っています。
なお、当日参加した人員・車両は以下の通りです。
1.吹田市消防本部 160名 8台
2.吹田市消防団 151名 11台
3.自衛消防隊 5事業者 25名
4.家庭防火クラブ 26組織 79名
5.幼年消防クラ 4組織 480名
6.自主消火組織 7組織 43名
コメント(0)|Trackback()
| « 前ページ | 次ページ » |
?