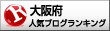GoogleはGoogleEarthの手法を生かして東日本の被災地に今も残る傷跡を公開した。「未來へのキオク」これは今も残る被災地の状況を映像に残すことによって後世に伝えようとするものでいまも片付けが手つかず残っている現地にカメラが入った。Wakiは3.11の東日本を襲った時の様子をDVDに収録して残しているが。できれば孫子の代と言わず末代まで伝えてほしいとおもっている。昔は残す術がなく後年人々は石碑に刻み後世の人に残した。大阪浪速区には安政大地震の時の津浪のすさまじさを刻んだ石碑が今も残されている。 嘉永七年(一八五四年)六月十四日午前零時ごろに大きな地震が発生した。大阪の町の人々は驚き、川のほとりにたたずみ、余震を恐れながら四、五日の間、不安な夜を明かした。この地震で三重や奈良では死者が数多く出た。 同年十一月四日午前八時ごろ、大地震が発生した。以前から恐れていたので、空き地に小屋を建て、年寄りや子どもが多く避難していた。地震が発生しても水の上なら安心だと小舟に乗って避難している人もいたところへ、翌日の五日午後四時ごろ、再び大地震が起こり、家々は崩れ落ち、火災が発生し、その恐ろしい様子がおさまった日暮れごろ、雷のような音とともに一斉に津波が押し寄せてきた。 安治川はもちろん、木津川の河口まで山のような大波が立ち、東堀まで約一・四メートルの深さの泥水が流れ込んだ。両川筋に停泊していた多くの大小の船の碇やとも綱は切れ、川の流れは逆流し、安治川橋、亀井橋、高橋、水分橋、黒金橋、日吉橋、汐見橋、幸橋、住吉橋、金屋橋などの橋は全て崩れ落ちてしまった。さらに、大きな道にまで溢れた水に慌てふためいて逃げ惑い、川に落ちた人もあった。・・・・・ 十分心得ておきなさい。犠牲になられた方々のご冥福を祈り、つたない文章であるがここに記録しておくので、心ある人は時々碑文が読みやすいよう墨を入れ、伝えていってほしい。安政二年(一八五五年)七月建立。いまも石碑は墨が入れられて大切に守られているそうだ。