■堕落刑事 2022.6.13
マンチェスタ市警 エイダン・ウェイツシリーズ 『 堕落刑事 』 を読みました。
シリーズ第一作目です。 デビューの時から詩情豊かなミステリー作家です。
美しい女だった。近ごろもてはやされるような、がりがりに痩せた美人ではない。“美”の本来の意味どおりの美人だった。陰りのない真っ白な肌は、それだけでセックスワークに向いていた。たとえ人生が悲しみのパレードであろうと、ダーシャはその肌のおかげで透明感を失わずにいたからだ。俺は、職業柄、少女たち、女たちが、ファックの対象かパンチの的として----あるいはガラス窓に投げつけるためのものとして----扱われた結果を繰り返し目の当たりにする。そのたびに、やるせない怒りを抱く。美が最悪を招く世界など、どこか狂っている。
ダーシャには自力でガラスを突き破るほどの力はなかったはずだ。しかし、彼女が転落した客室には誰もいなかった。........
金持ち連中からの苦情を受け、本部から警部補が来て、俺の捜査をやめさせようとした。俺は警部補を十九階の無人の客室に引っ張っていき、何が問題なのか説明した。
警部補は納得しなかった。そこで俺は部屋の入口まで下がって窓に狙いを定めた。その下に横たわる街をにらみ据えた。警部補は俺の意図を察し、やめろと怒鳴った。おれは何より警部補の顔に浮かぶ反応を見たいがために助走を開始したが、窓ガラスに突っこむ直前に阻まれた。
それは、俺のツーストライクの日だった。次のスリーストライクで俺は新聞の一面を飾り、俺の評判は地に落ちて、俺にもできる唯一の仕事を引き受けることになる。
ダーシャの死は自殺として処理され、その判断はいまも覆っていない。
以来、俺はビーサム・タワーには一度も行っていなかった。
この物語は、そんな俺、エイダン・ウェインのミステリー小説である。
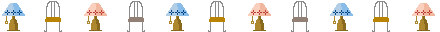
それまでの何週間か、ときおり深夜勤務を買って出ていた。本来は昼勤の日でも、深夜のシフトに交替してもらうためなら何だってした。夜の九時から朝の五時、ふだん見慣れた街が別物に変わっていく様子は、何度見ても見飽きることがなかった。街のネオンサインに照らし出される、満面の笑みを車のウィンドウに押しつけた子供。
夜の街を行く人々もいい。
みな若く、酒に酔い、恋を謳歌していた。女は稲妻、男は有言不実行。トランスセクシュアルやゴス、ゲイは夜を取り戻し、目抜き通りに多様性を添え、俺には意味さえわからない言葉を一斉に叫ぶ。夜の街は効果を発揮した。夜は俺をいくらかしらふに保つ。トラブルからいくらか遠ざける。
困ったことがあるとすれば、上司だった。ピーター・サトクリフ警部補。......
サティからたくさんのことを学んだとはいえ、ろくでもない知識も多かった。俺が深夜勤を始めたのは、夜の街にロマンチックな幻想を抱いてのことだったが、現実があっという間にそれを追い散らした。
「迎えの車を行かせる」ロシターは言った。坐ってノックを待つあいだずっと、前の晩にバーで見た落書きが脳裏にこびりついて消えなかった。
これから始まる夜を忘れよ
「この件に関してデヴィッドからアドバイスを求められたとき、きみの経歴を調べさせてもらったよ、ウェイツ。そのうえで、きみには関わらないほうがいいと彼に進言した。きみの経歴は、まもなくそのまま死亡記事になりそうだな」
俺は口を開きかけた。
「言い訳はけっこう」タリーは病気の感染源を避けるように距離を置いて俺を迂回した。
「自己紹介がまだだったな」キャサリンの肩に腕を回した男が言った。険悪な表情をまるで仮面のように顔に張りつけていた。過酷な人生を歩むうちに脱ぎ捨てるのが難しくなっていく種類の仮面。いまこの瞬間、この男にしてはおそらく理性的な状態でいるのだろうに、やはりその仮面を脱ぎ捨てることはできない。その表情のせいで目の前のことしか考えられないように見え、本当はもっと賢い人間なのかもしれないが、知性と縁遠い印象を与えた。
「シェルドン・ホワイトだ」男は空いたほうの手を誰にともなく差し出した。
『 堕落刑事/ジョセフ・ノックス/池田真紀子訳/新潮文庫 』
マンチェスタ市警 エイダン・ウェイツシリーズ 『 堕落刑事 』 を読みました。
シリーズ第一作目です。 デビューの時から詩情豊かなミステリー作家です。
美しい女だった。近ごろもてはやされるような、がりがりに痩せた美人ではない。“美”の本来の意味どおりの美人だった。陰りのない真っ白な肌は、それだけでセックスワークに向いていた。たとえ人生が悲しみのパレードであろうと、ダーシャはその肌のおかげで透明感を失わずにいたからだ。俺は、職業柄、少女たち、女たちが、ファックの対象かパンチの的として----あるいはガラス窓に投げつけるためのものとして----扱われた結果を繰り返し目の当たりにする。そのたびに、やるせない怒りを抱く。美が最悪を招く世界など、どこか狂っている。
ダーシャには自力でガラスを突き破るほどの力はなかったはずだ。しかし、彼女が転落した客室には誰もいなかった。........
金持ち連中からの苦情を受け、本部から警部補が来て、俺の捜査をやめさせようとした。俺は警部補を十九階の無人の客室に引っ張っていき、何が問題なのか説明した。
警部補は納得しなかった。そこで俺は部屋の入口まで下がって窓に狙いを定めた。その下に横たわる街をにらみ据えた。警部補は俺の意図を察し、やめろと怒鳴った。おれは何より警部補の顔に浮かぶ反応を見たいがために助走を開始したが、窓ガラスに突っこむ直前に阻まれた。
それは、俺のツーストライクの日だった。次のスリーストライクで俺は新聞の一面を飾り、俺の評判は地に落ちて、俺にもできる唯一の仕事を引き受けることになる。
ダーシャの死は自殺として処理され、その判断はいまも覆っていない。
以来、俺はビーサム・タワーには一度も行っていなかった。
この物語は、そんな俺、エイダン・ウェインのミステリー小説である。
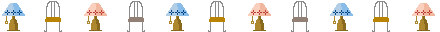
それまでの何週間か、ときおり深夜勤務を買って出ていた。本来は昼勤の日でも、深夜のシフトに交替してもらうためなら何だってした。夜の九時から朝の五時、ふだん見慣れた街が別物に変わっていく様子は、何度見ても見飽きることがなかった。街のネオンサインに照らし出される、満面の笑みを車のウィンドウに押しつけた子供。
夜の街を行く人々もいい。
みな若く、酒に酔い、恋を謳歌していた。女は稲妻、男は有言不実行。トランスセクシュアルやゴス、ゲイは夜を取り戻し、目抜き通りに多様性を添え、俺には意味さえわからない言葉を一斉に叫ぶ。夜の街は効果を発揮した。夜は俺をいくらかしらふに保つ。トラブルからいくらか遠ざける。
困ったことがあるとすれば、上司だった。ピーター・サトクリフ警部補。......
サティからたくさんのことを学んだとはいえ、ろくでもない知識も多かった。俺が深夜勤を始めたのは、夜の街にロマンチックな幻想を抱いてのことだったが、現実があっという間にそれを追い散らした。
「迎えの車を行かせる」ロシターは言った。坐ってノックを待つあいだずっと、前の晩にバーで見た落書きが脳裏にこびりついて消えなかった。
これから始まる夜を忘れよ
「この件に関してデヴィッドからアドバイスを求められたとき、きみの経歴を調べさせてもらったよ、ウェイツ。そのうえで、きみには関わらないほうがいいと彼に進言した。きみの経歴は、まもなくそのまま死亡記事になりそうだな」
俺は口を開きかけた。
「言い訳はけっこう」タリーは病気の感染源を避けるように距離を置いて俺を迂回した。
「自己紹介がまだだったな」キャサリンの肩に腕を回した男が言った。険悪な表情をまるで仮面のように顔に張りつけていた。過酷な人生を歩むうちに脱ぎ捨てるのが難しくなっていく種類の仮面。いまこの瞬間、この男にしてはおそらく理性的な状態でいるのだろうに、やはりその仮面を脱ぎ捨てることはできない。その表情のせいで目の前のことしか考えられないように見え、本当はもっと賢い人間なのかもしれないが、知性と縁遠い印象を与えた。
「シェルドン・ホワイトだ」男は空いたほうの手を誰にともなく差し出した。
『 堕落刑事/ジョセフ・ノックス/池田真紀子訳/新潮文庫 』

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます