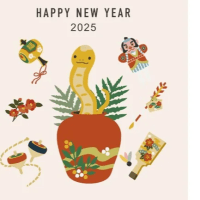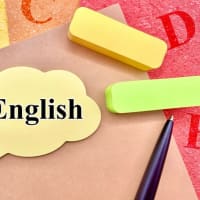100分de名著 新渡戸稲造 武士道 『正義・日本人の美徳』 Part1 瀧口友里奈 押尾正明 山本博文 毎週水曜日 100ぷんで名著
一昨日の夜NHKEテレの「知恵泉」で放送されていた、新渡戸稲造の「武士道」
新渡戸稲造については、旧5千円札に登場していた時、WHYこの人?という意識だった。
それ以上、調べることもなく。
しかし、一昨日の放送で、この本は私はまだ、読んだことがないが、日本人にとってとっても重要な本だと思ったので、youtubeで動画を探し4回分のこの100分で名著を見てみた。
そして、はっきりとこの本は日本の桜と同じように日本人の精神やアイデンティティーを描き出した名作だと思った。
「武士道」に入る前に新渡戸稲造についてウィキペディアを基に少し書いておくと、
新渡戸稲造は、1862年9月に現在の盛岡市で三男として生まれ、小さいときから英語を医師から学んだ。13歳で現在の東京英語学校に入学し、その後札幌農学校(現在の北海道大学)に入学。その後目を悪くして盛岡に帰る。
22歳でアメリカへ私費留学。札幌農学校の助教授としてドイツへ留学。アメリカ人のメアリーと結婚。
体調を崩してカリフォルニア州で療養している時に書いたのが、「武士道」(1899年か1900年に英文で書かれた)
それは、ドイツ語、フランス語などへも翻訳され、ベストセラーになり、時のルーズベルト大統領も感銘したという。
1920年には国際連盟設立時に事務次長として選ばれ、エスペラント語を広める活動やバルト海のオーランド諸島の帰属問題でスウェーデンとフィンランドが対立する中、帰属は元々のフィンランド、言語はスウェーデン語、オーランドの自治を認めるという裁定をし、現在まで喜ばれているという。
まさに、「太平洋の架け橋になりたい」という夢を実現した人であった。
前置きが長くなったが、「武士道」については、この動画を含めて4本をyoutubeで見てもらいたい。
聞いた中で印象に残った所だけを書き出すと、
1 武士道には7つの徳がある。中心は「忠義」それを支えるのが「義」と「礼」(おもいやり)
その2つを支えるのが、「勇」「智」「仁」「信」
「忠義」は殿様のような人に仕えることだが、失敗すれば(いや成功しても相手を切れば)
「切腹」するのが当たり前。これには、「名誉」がかかっていた。
「名誉」の裏返しは「恥」
「世間」からどう思われるかも考え、決して「名誉」を損なわぬように行動した。
行動するには、「勇」が必要で「忍耐」を重んじた。
2 日本人は西洋から見て、「遠慮しすぎる」「謙遜しすぎる」
「謎の微笑み」などと言われるが、
それは誤解で、日本人が「克己」(こっき)して「静かなる威厳」を保っているから、東日本大震災のような時にでも対処できた。泣いているだけではない。
3 明治維新の推進役になったのはこの「武士道精神」
しかし、それは戦争へも導くことになる。
戦後、この「武士道精神」は誤解されて、尊ばれなくなったが、
この精神は「高貴な身分の人が持つ品格」(ノブレス・オブリージュというらしい)を表しており、
笑われるのが恥ずかしくて英語もしゃべれない内向きな日本人が模範にすべきもの。
恥ずかしがっているだけでは良くない。空気を読んでいるだけでは良くない。
時には、激しくぶつかる勇気で、世界を引っ張っていく気概がないと。
◎以上、新渡戸稲造氏があの当時に日本人の誤解を解くために、ギリシャの哲学者やドイツの哲学者などの 言葉を引用して、「武士道」の精神をかみくだいて、しかも日本語でなく英語で出版されたこの本。
これからの日本人が活躍するうえでの大きな指針となるだろう。
そして、思うのだ。タイトルのようなことを。
「新渡戸稲造に続け!」と叫んでいる気がする。
一昨日の夜NHKEテレの「知恵泉」で放送されていた、新渡戸稲造の「武士道」
新渡戸稲造については、旧5千円札に登場していた時、WHYこの人?という意識だった。
それ以上、調べることもなく。
しかし、一昨日の放送で、この本は私はまだ、読んだことがないが、日本人にとってとっても重要な本だと思ったので、youtubeで動画を探し4回分のこの100分で名著を見てみた。
そして、はっきりとこの本は日本の桜と同じように日本人の精神やアイデンティティーを描き出した名作だと思った。
「武士道」に入る前に新渡戸稲造についてウィキペディアを基に少し書いておくと、
新渡戸稲造は、1862年9月に現在の盛岡市で三男として生まれ、小さいときから英語を医師から学んだ。13歳で現在の東京英語学校に入学し、その後札幌農学校(現在の北海道大学)に入学。その後目を悪くして盛岡に帰る。
22歳でアメリカへ私費留学。札幌農学校の助教授としてドイツへ留学。アメリカ人のメアリーと結婚。
体調を崩してカリフォルニア州で療養している時に書いたのが、「武士道」(1899年か1900年に英文で書かれた)
それは、ドイツ語、フランス語などへも翻訳され、ベストセラーになり、時のルーズベルト大統領も感銘したという。
1920年には国際連盟設立時に事務次長として選ばれ、エスペラント語を広める活動やバルト海のオーランド諸島の帰属問題でスウェーデンとフィンランドが対立する中、帰属は元々のフィンランド、言語はスウェーデン語、オーランドの自治を認めるという裁定をし、現在まで喜ばれているという。
まさに、「太平洋の架け橋になりたい」という夢を実現した人であった。
前置きが長くなったが、「武士道」については、この動画を含めて4本をyoutubeで見てもらいたい。
聞いた中で印象に残った所だけを書き出すと、
1 武士道には7つの徳がある。中心は「忠義」それを支えるのが「義」と「礼」(おもいやり)
その2つを支えるのが、「勇」「智」「仁」「信」
「忠義」は殿様のような人に仕えることだが、失敗すれば(いや成功しても相手を切れば)
「切腹」するのが当たり前。これには、「名誉」がかかっていた。
「名誉」の裏返しは「恥」
「世間」からどう思われるかも考え、決して「名誉」を損なわぬように行動した。
行動するには、「勇」が必要で「忍耐」を重んじた。
2 日本人は西洋から見て、「遠慮しすぎる」「謙遜しすぎる」
「謎の微笑み」などと言われるが、
それは誤解で、日本人が「克己」(こっき)して「静かなる威厳」を保っているから、東日本大震災のような時にでも対処できた。泣いているだけではない。
3 明治維新の推進役になったのはこの「武士道精神」
しかし、それは戦争へも導くことになる。
戦後、この「武士道精神」は誤解されて、尊ばれなくなったが、
この精神は「高貴な身分の人が持つ品格」(ノブレス・オブリージュというらしい)を表しており、
笑われるのが恥ずかしくて英語もしゃべれない内向きな日本人が模範にすべきもの。
恥ずかしがっているだけでは良くない。空気を読んでいるだけでは良くない。
時には、激しくぶつかる勇気で、世界を引っ張っていく気概がないと。
◎以上、新渡戸稲造氏があの当時に日本人の誤解を解くために、ギリシャの哲学者やドイツの哲学者などの 言葉を引用して、「武士道」の精神をかみくだいて、しかも日本語でなく英語で出版されたこの本。
これからの日本人が活躍するうえでの大きな指針となるだろう。
そして、思うのだ。タイトルのようなことを。
「新渡戸稲造に続け!」と叫んでいる気がする。