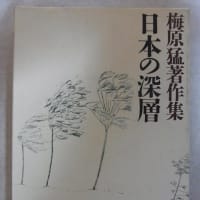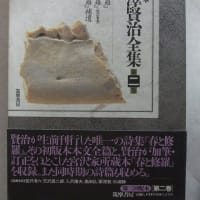前回の「写経」で、『好きになる数学入門 第6巻』の「フリードリッヒ大王」へ行く、と予告したが、順番を変えて、タイトルの書を先にする。
理由は、新聞に、「われわれが出会う人びとは、われわれの人生の脚本家であり、舞台監督である。」という、エリック・ホッファーの言葉が紹介されていたからだ。(『2013.7.1 東京新聞 けさのことば 岡井隆』)
岡井氏は、“今日偶然会った人がわたしの人生の筋書きを書いたり、わたしの行動をきめてしまうなんて、そんなことはあるわけないと思うかもしれない。しかし、よく考えると「他人の目に映り、他人の言葉に反響する自分」を意識して行動しているのがわかる。人間とはそういうものだ”
と書かれている。そうかもしれない。
中世へさかのぼりゆく一群をおくりて暑き午後へ降りたつ
海こえてかなしき婚をあせりたる権力のやわらかき部分見ゆ
マルコ伝第七章に栞おき一日を決めむ今朝のやすらぎ
“「シリア・フェニキアの女の信仰」 イエスはそこを立ち去って、ティルスの地方に行かれた。ある家に入り、だれにも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女が、すぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足もとにひれ伏した。 女はギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであったが、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。イエスは言われた。「まず、子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って、子犬にやってはいけない。」ところが女は答えて言った。「主よ、しかし、食卓の下の子犬も、子供のパン屑はいただきます。」そこで、イエスは言われた。「それほど言うなら、よろしい。家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。」 女が家に帰ってみると、その子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。”
“外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出て来るものが、人を汚すのである。(中略)これらの悪はみな中から出て来て、人を汚すのである。”
紅(くれない)にマッチにわずか燃ゆる芝問いかえしつつ党のその後
わが髪の長きを笑い編まんとせし少女らのため聖句選びぬ
また一歩ジャーナリズムは右へ寄る読み捨てて出づあつき靴履き
仮説をたて仮説をたてて追いゆくに くしけずらざる髪も炎え(もえ)立つ
一国がきらめく匕首(ひしゅ)にかわるとき誰かが誰かの戦争にゆくとき
荒海を見る十幾組のことごとく愛ありて来し 沖はとどろく
『岡井隆歌集』、『聖書(新共同訳)』
そして、エリック・ホッファーの書。
2013.6.26の記事に書いたように、「ユダヤ」を考える座標軸を私が得るために、この書からそれを中心に読み、学んでいく。
It is perhaps not superfluous to add a word of caution. When we speak of the family likeness of mass movements, we use the word “family” in a taxonomical
sense. The tomato and the nightshade are of the same family, the Solanaceae. Though the one is nutritious and the other poisonous, they have many morphological, anatomical
and physiological traits in common so that even the nonbotanist senses a family likeness. The assumption that mass movements have many traits in common dose not imply that
all movements are equallly beneficent or poisonous. The book passes no judgments, and expresses no preferences. It merely tries to explain; and the explanations―all of them
theories―are in the nature of suggestions and arguments even when they are stated in what seems a categorical tone. I can do no better than quote Montaigne: “All I
say is by way of discourse, and nothing by way of advice. I should not speak so boldly if it were my due to be believed ”
『THE TRUE BELIEVER Thoughts on the Nature of Mass Movements』「Preface」 ERIC HOFFER
理由は、新聞に、「われわれが出会う人びとは、われわれの人生の脚本家であり、舞台監督である。」という、エリック・ホッファーの言葉が紹介されていたからだ。(『2013.7.1 東京新聞 けさのことば 岡井隆』)
岡井氏は、“今日偶然会った人がわたしの人生の筋書きを書いたり、わたしの行動をきめてしまうなんて、そんなことはあるわけないと思うかもしれない。しかし、よく考えると「他人の目に映り、他人の言葉に反響する自分」を意識して行動しているのがわかる。人間とはそういうものだ”
と書かれている。そうかもしれない。
中世へさかのぼりゆく一群をおくりて暑き午後へ降りたつ
海こえてかなしき婚をあせりたる権力のやわらかき部分見ゆ
マルコ伝第七章に栞おき一日を決めむ今朝のやすらぎ
“「シリア・フェニキアの女の信仰」 イエスはそこを立ち去って、ティルスの地方に行かれた。ある家に入り、だれにも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女が、すぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足もとにひれ伏した。 女はギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであったが、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。イエスは言われた。「まず、子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って、子犬にやってはいけない。」ところが女は答えて言った。「主よ、しかし、食卓の下の子犬も、子供のパン屑はいただきます。」そこで、イエスは言われた。「それほど言うなら、よろしい。家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。」 女が家に帰ってみると、その子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。”
“外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出て来るものが、人を汚すのである。(中略)これらの悪はみな中から出て来て、人を汚すのである。”
紅(くれない)にマッチにわずか燃ゆる芝問いかえしつつ党のその後
わが髪の長きを笑い編まんとせし少女らのため聖句選びぬ
また一歩ジャーナリズムは右へ寄る読み捨てて出づあつき靴履き
仮説をたて仮説をたてて追いゆくに くしけずらざる髪も炎え(もえ)立つ
一国がきらめく匕首(ひしゅ)にかわるとき誰かが誰かの戦争にゆくとき
荒海を見る十幾組のことごとく愛ありて来し 沖はとどろく
『岡井隆歌集』、『聖書(新共同訳)』
そして、エリック・ホッファーの書。
2013.6.26の記事に書いたように、「ユダヤ」を考える座標軸を私が得るために、この書からそれを中心に読み、学んでいく。
It is perhaps not superfluous to add a word of caution. When we speak of the family likeness of mass movements, we use the word “family” in a taxonomical
sense. The tomato and the nightshade are of the same family, the Solanaceae. Though the one is nutritious and the other poisonous, they have many morphological, anatomical
and physiological traits in common so that even the nonbotanist senses a family likeness. The assumption that mass movements have many traits in common dose not imply that
all movements are equallly beneficent or poisonous. The book passes no judgments, and expresses no preferences. It merely tries to explain; and the explanations―all of them
theories―are in the nature of suggestions and arguments even when they are stated in what seems a categorical tone. I can do no better than quote Montaigne: “All I
say is by way of discourse, and nothing by way of advice. I should not speak so boldly if it were my due to be believed ”
『THE TRUE BELIEVER Thoughts on the Nature of Mass Movements』「Preface」 ERIC HOFFER