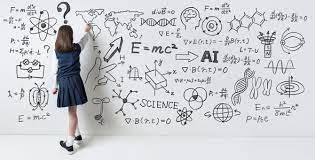腹痛はよくある症状だが、「腹痛が続く。食べ過ぎだろうか」と思っていたら、もしかしたら重大病のサインかもしれない。
「患者が訴える症状の6割前後が腹痛」とのデータもある膵がんについて、がん感染症センター都立駒込病院院長の神澤輝実医師(胆膵疾患専門)に聞いた。
膵がんは非常に予後が悪いがんだ。理由として、早期発見が難しいことが挙げられる。 「膵がんは特異的な症状に乏しく、多くが進行してから発見されます。しかし、膵がんのリスクが高い人というのが分かっています。まずは自分がどうなのかを知っておくべきです」
(1)家系に膵がん患者がいる 「この場合、膵がんのリスクが高くなります。近親者であるほどリスクは高くなり、両親、兄弟姉妹、子供の第一度近親者に膵がん患者が1人いれば4・5倍、2人いれば6・4倍、3人以上では32倍と高くなります」 第一度近親者に2人以上の膵がん患者がいる家系を家族性膵がん家系と言い、50歳未満発症の患者がいると発症リスクが9・31倍になる。
(2)糖尿病がある 2型糖尿病は膵がんのリスクを上げる。発症リスクは1・94倍だ。 「特に発症から1年未満が5・38倍と高い。新規発症時や急激に血糖値が上昇した時は膵がんを警戒すべきです」
(3)肥満がある 肥満度を示すBMI〈体重(キログラム)÷身長(メートル)の2乗〉が「5」増えると膵がんの発症リスクが1・1倍、ウエスト10センチ増加で1・11倍になる。
(4)慢性膵炎がある 本来は食べ物を溶かす消化酵素が持続的に活性化されて、ゆっくりと自分の膵臓組織を溶かしてしまう病気が慢性膵炎だ。大量飲酒を続けることで起こるアルコール性慢性膵炎が、特に男性では多い。ほかには胆石、脂質異常症、膵管の形態異常などが原因として挙げられる。 「慢性膵炎での膵がんの発生リスクは13・3倍と非常に高率。慢性膵炎は膵がんの前がん病変と考えられています」 ただし、禁酒などで膵がんの発症は減少する。
(5)膵嚢胞がある 膵臓の内部や周囲にできる「袋」で、膵嚢胞の多くは良性である。しかし、膵管上皮から発生し粘液を産生して膵嚢胞を作る膵管内乳頭粘液性腫瘍は要注意。悪性のものもあり、また最初は良性だが次第に大きくなり、やがてがんになるものが出てくる。ほぼ無症状で、粘液で膵液の流れが妨げられたり、大きくなると、腹痛や背部痛が生じることがある。 「同じ膵管内乳頭粘液性腫瘍であっても、形態によって悪性化リスクが異なります。検査で形態を分類し、経過観察となります」
(6)喫煙習慣がある 「喫煙による膵がんの発症リスクは1・68倍で、1日の喫煙本数や喫煙期間によってリスクが高くなります。一方、禁煙してからの期間が長いほどリスクが減少します」 糖尿病や肥満、遺伝性膵炎に喫煙が加わると、発症リスクはより高くなる。
(7)大量飲酒 大量飲酒は慢性膵炎とともに膵がんのリスクも上げる。
(8)歯周病がある 最近の研究で、歯周病や歯肉炎があると膵がんのリスクが1・54~1・74倍高くなると報告されている。 「リスク要因の中には、糖尿病、肥満、喫煙、大量飲酒、歯周病のように対策を講じられるものもあります。それらを減らすことが大事です」
さらに、腹痛、背部痛、早期膨満感、体重減少があれば、放置しないで病院で検査を受けることだ。