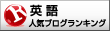擂鉢山の山頂には写真撮影のポイントが多くあります。
碑も多いですし展望も一番の標高島内で最高点です。
海側では、眼下に広がる海、崩れている斜面が海に
落ち込んでいる様子などを見ることができます。
今年で、定年退職で、私たちの訪問の時の解説を
ご担当いただくのが最後となる、
親切で愉快な、私たちの班担当してくれた自衛隊隊員の方とメンバーで、
海側を臨む地点で、記念撮影をしました。
その後、米軍の碑、星条旗を立てた跡、父親たちの星条旗の著者訪問の
石版などがある島全体を臨む方に来て、この写真を撮りました。
その地点から左側を撮ると、前回の記事に掲載の、釜岩・おが丸繋留場所
方面で、右側を撮ると、この写真の、島の東側半分になります。
眼下に、米軍が上陸した鶉石のある海岸で、
左側には、自衛隊施設が写っています。
この場所で同様の角度で、毎年、写真を撮影していますが、今年は、
同じ班でご一緒いただいた小笠原村村議会副議長が、
「あの、縞模様を見てください。隆起の様子が、浜に
刻まれているのが分かりますよ。」と、解説してくださいました。
一昨年も昨年も見て写真撮っているのにいるのに気がつきませんでしたが、
確かに海岸に海岸線と並んで、数本の縞があります。
大木の年輪のようです。
この縞模様から、
戦後の数十年で、数度の、わりと大きな隆起となった地殻変動(火山)活動が
あったことが分かるのだと、初めて知りました。
一昨年の記事などで、「繋留場所、正面の沈船群のコンクリート船が昨年より
また上がって見えるという声があった。」 「上陸海岸の突起している岩が
隆起を示している。」などと、書いてきましたが、
潮の干満もあったでしょうし、ちょっと見た目の、それらの高さが
1年での隆起をしめすというような、戦後の硫黄島の隆起だったというよりは、
これまでに数回、「年輪」を浜に刻むような、上がり方をした、と考える方が
正しそうだな、と思いました。
訪問するたびに、発見がある、硫黄島です。
碑も多いですし展望も一番の標高島内で最高点です。
海側では、眼下に広がる海、崩れている斜面が海に
落ち込んでいる様子などを見ることができます。
今年で、定年退職で、私たちの訪問の時の解説を
ご担当いただくのが最後となる、
親切で愉快な、私たちの班担当してくれた自衛隊隊員の方とメンバーで、
海側を臨む地点で、記念撮影をしました。
その後、米軍の碑、星条旗を立てた跡、父親たちの星条旗の著者訪問の
石版などがある島全体を臨む方に来て、この写真を撮りました。
その地点から左側を撮ると、前回の記事に掲載の、釜岩・おが丸繋留場所
方面で、右側を撮ると、この写真の、島の東側半分になります。
眼下に、米軍が上陸した鶉石のある海岸で、
左側には、自衛隊施設が写っています。
この場所で同様の角度で、毎年、写真を撮影していますが、今年は、
同じ班でご一緒いただいた小笠原村村議会副議長が、
「あの、縞模様を見てください。隆起の様子が、浜に
刻まれているのが分かりますよ。」と、解説してくださいました。
一昨年も昨年も見て写真撮っているのにいるのに気がつきませんでしたが、
確かに海岸に海岸線と並んで、数本の縞があります。
大木の年輪のようです。
この縞模様から、
戦後の数十年で、数度の、わりと大きな隆起となった地殻変動(火山)活動が
あったことが分かるのだと、初めて知りました。
一昨年の記事などで、「繋留場所、正面の沈船群のコンクリート船が昨年より
また上がって見えるという声があった。」 「上陸海岸の突起している岩が
隆起を示している。」などと、書いてきましたが、
潮の干満もあったでしょうし、ちょっと見た目の、それらの高さが
1年での隆起をしめすというような、戦後の硫黄島の隆起だったというよりは、
これまでに数回、「年輪」を浜に刻むような、上がり方をした、と考える方が
正しそうだな、と思いました。
訪問するたびに、発見がある、硫黄島です。