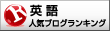医務課壕の中から、たてに地表に向けて掘られた穴の写真です。
医務課壕には訪問の度に行っています。
入り口から、このたての穴のあたりまではそんなに暑くないですが、
ここから奥に進むとどんどん暑くなります。
戦闘で傷ついたり重病だったりした兵士が運ばれた壕だとうことですが、
風通しが良い壕の入り口付近にはには、
比較的軽症な患者が入って、重症で治癒の見込みがほとんどない
兵士が壕の奥の暑い場所に収容されたという話を聞きました。
調査とご遺骨収集が終わった壕で、
慰霊墓参の私どもが中に入れるようにしてくれている壕の中では
この医務課壕と栗林壕(兵団司令部壕)は、
簡易的な配線ですが、中ま電気の敗戦をしてくれてランプの照明をつけてくれています。
班ごとに、いろいろな場所をまわりますので、前の人たちがバスに戻ってくる途中だったり、ちょうど見ているところだったりします。
一昨年は、この医務課壕入り口に着いた時には別のグループがいませんでしたので、私が外に置いてある発電機を起動させました。
発電機の燃料などのチェックやメンテナンスなどはは事前にしてくれています。
最後のグループが終わり発電機を切るとランプが消えます。
栗林壕は途中で、中腰で低くしゃがまない進めない場所がありますので、
前のグループが入っている場合には皆さんが
出たことを確認してからでないと、次のグループは入れません。
一報のこの医務課壕は幅も広く中ですれ違えるので前の人たちを待たずに入れます。
今年は、中学生のグループが前に入っていて、ちょうど、このたて穴を過ぎたあたりで、すれ違いました。
中学生たちが
「ものすごい暑さだった。ここまで来ると、やっと
涼しくなってきて生き返る感じがするね。」と話しているのを聞いて、
「この地点でももう、十分に地熱、熱気で息苦しい暑さなのに、
ここが涼しいと感じるというぐらいにこの奥は暑いんだったっけ。」
と思いました。
一昨年も昨年も入っていて知っている私が、
「この地点は、もう、たまらない熱気だな。」と
思った地点で、今年初めて入った中学生たちは、
「この奥の暑さからここに戻ると、安心する涼しさだ。」と
言っていたのです。
中学生たちは外へ、
私たちグループは奥の進みました。
照明があって行ける一番奥にまで着くと、
息苦しい暑さでした。サウナの暑さとも違う地熱の熱気の暑さです。
そして、入り口に向かって戻る時に、
さっきすれ違っていた中学生と同じように、
さっきは「このあたりの暑さでも、もう、たまらないな。」という
写真のたて穴の近くまで来て、
「このあたりまで来ると、外の涼しさがやっと感じられてくるな。」
と思うのですから、不思議でした。
どのような傷、病気だったか、分かりませんが、
助かる見込みがないという程度から、想像することができる、
重症の人ほど、奥にいたというのは、本当に残酷な
言語を絶する辛さだったろうと思います。
当時と今と、地熱の関係などで、同じ暑さだったかは
分かりません。別の壕でも、1年違うと、硫黄の蒸気の具合が
全く違ったりします。
ですが、換気のためのたて穴より入り口近くと、奥とで
全然違っていたのは確かだと思います。
短期間に島中にあれだけの壕を掘った作戦。
まだ、米軍が来る前の、壕掘削でも、
十分な水がない中での作業の苦しみは
言葉であらわせないものだったそうです。
1日に500mlが一人に与えられた水だったそうです。
医務課壕は、一つの例で、島中が壕だらけの島です。
辛い辛い、戦争があった島で、私たちは手を合わせて
ご冥福をお祈りすることしかできません。
このブログをご覧いただき、硫黄島についても紹介してくださっている、
「おがししょ」さんの「おがさわらちいさなとしょしつ」に
NHKが硫黄島から皆既日食の放送をする、と紹介していただいています。
http://www.nhk.or.jp/live0722/index.htmlがNHKの番組紹介の
URLで、
「第二次世界大戦の激戦地、硫黄島。この島も最良の観測地点のひとつ。」の
皆既になる時間は 11:25だそうです。
だそうです。
「おがししょ」さん、いつもありがとうございます。
貴重な情報をありがとうございます。
おかげで見逃さずに済みます!
医務課壕には訪問の度に行っています。
入り口から、このたての穴のあたりまではそんなに暑くないですが、
ここから奥に進むとどんどん暑くなります。
戦闘で傷ついたり重病だったりした兵士が運ばれた壕だとうことですが、
風通しが良い壕の入り口付近にはには、
比較的軽症な患者が入って、重症で治癒の見込みがほとんどない
兵士が壕の奥の暑い場所に収容されたという話を聞きました。
調査とご遺骨収集が終わった壕で、
慰霊墓参の私どもが中に入れるようにしてくれている壕の中では
この医務課壕と栗林壕(兵団司令部壕)は、
簡易的な配線ですが、中ま電気の敗戦をしてくれてランプの照明をつけてくれています。
班ごとに、いろいろな場所をまわりますので、前の人たちがバスに戻ってくる途中だったり、ちょうど見ているところだったりします。
一昨年は、この医務課壕入り口に着いた時には別のグループがいませんでしたので、私が外に置いてある発電機を起動させました。
発電機の燃料などのチェックやメンテナンスなどはは事前にしてくれています。
最後のグループが終わり発電機を切るとランプが消えます。
栗林壕は途中で、中腰で低くしゃがまない進めない場所がありますので、
前のグループが入っている場合には皆さんが
出たことを確認してからでないと、次のグループは入れません。
一報のこの医務課壕は幅も広く中ですれ違えるので前の人たちを待たずに入れます。
今年は、中学生のグループが前に入っていて、ちょうど、このたて穴を過ぎたあたりで、すれ違いました。
中学生たちが
「ものすごい暑さだった。ここまで来ると、やっと
涼しくなってきて生き返る感じがするね。」と話しているのを聞いて、
「この地点でももう、十分に地熱、熱気で息苦しい暑さなのに、
ここが涼しいと感じるというぐらいにこの奥は暑いんだったっけ。」
と思いました。
一昨年も昨年も入っていて知っている私が、
「この地点は、もう、たまらない熱気だな。」と
思った地点で、今年初めて入った中学生たちは、
「この奥の暑さからここに戻ると、安心する涼しさだ。」と
言っていたのです。
中学生たちは外へ、
私たちグループは奥の進みました。
照明があって行ける一番奥にまで着くと、
息苦しい暑さでした。サウナの暑さとも違う地熱の熱気の暑さです。
そして、入り口に向かって戻る時に、
さっきすれ違っていた中学生と同じように、
さっきは「このあたりの暑さでも、もう、たまらないな。」という
写真のたて穴の近くまで来て、
「このあたりまで来ると、外の涼しさがやっと感じられてくるな。」
と思うのですから、不思議でした。
どのような傷、病気だったか、分かりませんが、
助かる見込みがないという程度から、想像することができる、
重症の人ほど、奥にいたというのは、本当に残酷な
言語を絶する辛さだったろうと思います。
当時と今と、地熱の関係などで、同じ暑さだったかは
分かりません。別の壕でも、1年違うと、硫黄の蒸気の具合が
全く違ったりします。
ですが、換気のためのたて穴より入り口近くと、奥とで
全然違っていたのは確かだと思います。
短期間に島中にあれだけの壕を掘った作戦。
まだ、米軍が来る前の、壕掘削でも、
十分な水がない中での作業の苦しみは
言葉であらわせないものだったそうです。
1日に500mlが一人に与えられた水だったそうです。
医務課壕は、一つの例で、島中が壕だらけの島です。
辛い辛い、戦争があった島で、私たちは手を合わせて
ご冥福をお祈りすることしかできません。
このブログをご覧いただき、硫黄島についても紹介してくださっている、
「おがししょ」さんの「おがさわらちいさなとしょしつ」に
NHKが硫黄島から皆既日食の放送をする、と紹介していただいています。
http://www.nhk.or.jp/live0722/index.htmlがNHKの番組紹介の
URLで、
「第二次世界大戦の激戦地、硫黄島。この島も最良の観測地点のひとつ。」の
皆既になる時間は 11:25だそうです。
だそうです。
「おがししょ」さん、いつもありがとうございます。
貴重な情報をありがとうございます。
おかげで見逃さずに済みます!