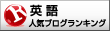小笠原海洋センターのウミガメの「里親制度」、
先日、申込用紙を送付いただき、申込んだ結果を
ご確認いただけたと、メールで連絡いただきました。
無事に里親になり、里子の名前も決まりました。
二人のチビちゃんガメの里親になりました。
一人の子は、私ではなく、6月に一緒に海洋センター見学を
した同行者たちが名前をつけました。
「たわし」という名前です。
カメの子 だから、ということらしいです。
もう一人の子は、
私が、「雄優(ゆうゆう)」と名づけました。
優しさで守られた小笠原の自然、雄大な海を
元気に泳げ!
たくましく優しいウミガメになって、帰ってくるように!
そして、雄と優という字を、使いたかったのでこの名前にしました。
硫黄島での激戦での戦没者のご冥福を祈り、
平和が続くようにとの心からの祈念の気持ちをこめるために
どうしても、使いたかった二文字が、
「優」と「雄」でした。
海洋センターのスタッフの方からのご報告では、
子ガメたち、みんな、いよいよ食欲旺盛で、大きくなっている
そうで、
順番に、海に戻し始めるとのことです。
希望としては、
この記事の写真の子ガメのような赤っぽい色のを「雄優」、
前に子ガメの休憩の姿勢という紹介の時に写真を載せた
黒っぽい色のを、「たわし」に、とお願いしました。
そして、海に旅立たせる候補の日も
お知らせいただきました。
7月26日の、「貞頼神社例大祭」で、代理放流していただける
そうです。
雄優!
それまでに、たっぷり食べて、大きくなって、
元気で海に出て行くように!
あ、
もう一人の たわしも 元気に旅立つように!
<script type="text/javascript" src="http://xima.jp/p/bprt.php?p=1xBt468cBffg"></script>
先日、申込用紙を送付いただき、申込んだ結果を
ご確認いただけたと、メールで連絡いただきました。
無事に里親になり、里子の名前も決まりました。
二人のチビちゃんガメの里親になりました。
一人の子は、私ではなく、6月に一緒に海洋センター見学を
した同行者たちが名前をつけました。
「たわし」という名前です。
カメの子 だから、ということらしいです。
もう一人の子は、
私が、「雄優(ゆうゆう)」と名づけました。
優しさで守られた小笠原の自然、雄大な海を
元気に泳げ!
たくましく優しいウミガメになって、帰ってくるように!
そして、雄と優という字を、使いたかったのでこの名前にしました。
硫黄島での激戦での戦没者のご冥福を祈り、
平和が続くようにとの心からの祈念の気持ちをこめるために
どうしても、使いたかった二文字が、
「優」と「雄」でした。
海洋センターのスタッフの方からのご報告では、
子ガメたち、みんな、いよいよ食欲旺盛で、大きくなっている
そうで、
順番に、海に戻し始めるとのことです。
希望としては、
この記事の写真の子ガメのような赤っぽい色のを「雄優」、
前に子ガメの休憩の姿勢という紹介の時に写真を載せた
黒っぽい色のを、「たわし」に、とお願いしました。
そして、海に旅立たせる候補の日も
お知らせいただきました。
7月26日の、「貞頼神社例大祭」で、代理放流していただける
そうです。
雄優!
それまでに、たっぷり食べて、大きくなって、
元気で海に出て行くように!
あ、
もう一人の たわしも 元気に旅立つように!
<script type="text/javascript" src="http://xima.jp/p/bprt.php?p=1xBt468cBffg"></script>