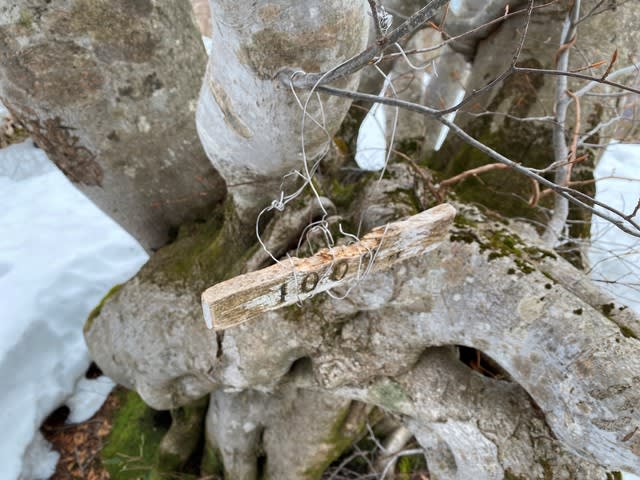今日はジャガイモの植え付けをした。ジャガイモも今話題のウィルスにかかっているイモがあることから、昨年収穫したイモは使えない(このウィルスを媒介するのはアブラムシということだ)ので、ウィルスフリーのイモを買ってこなければならない。昨日は小学生の地区分団児童会が開かれたが、4月からの新入生はわずか1名、6年生まで合わせても10数名しかいない。揖斐祭りの子ども神輿は中学生が中心となり、この年代は多いのでなんとかつることができそうだ。

庭のクリスマスローズ、植えたのは黄色、あとは鉢のクリスマスローズの種をばらまいた
自然と交配するのもありそうで変わった色の品種が出てくる
一方で高齢者の数は増えるばかりで、高齢者のみの世帯がどんどん増えてきている。問題はやはり80歳以上の一人暮らしの方で、日頃の買い物、医者通いにも困るし、ましてや災害があったときに自力で避難することは難しい。このため、当地区では支援が必要だと思う方に申し出ていただいて、その方の近隣に住まいの方に支援をしてもらう制度を作った(社協や区長会の指導もある)。近隣の方と当該者が日頃からお付き合いがある方はすぐに支援者が見つかるが、お付き合いがあまりない方はそうはいかない。仕方がないので、当面の措置としてその班の班長や社会福祉推進委員に支援者になってもらうことにした。
その支援制度を作る中で、地区全体の災害に備えた防災計画が必要だと感じた。しかし、この防災計画だが、作っても実際には動かないことが多いことから、その必要性を感じていなかった。しかし、今回災害時等の高齢者の支援体制を作ったことから、地区の防災計画について班長会の議題としてあげた。残念ながら、それに対する意見はほとんど出ずに、私の案がそのまま4月から実施されることとなった(この地区は比較的災害の恐れが少なく、住民に防災意識が薄いのだと思う)。東北大震災特に原発事故の時、自治会は機能しなかったと聞いている。日頃からの防災意識を高めることをしていかないと災害時には機能しない。引き継ぎで次期の区長に強調しておきたいところである。

普通種が自然に落ちて、小さな苗が出てくる。しかし、この手前の黒は小苗ができない
2月22日の最終の班長会でこんなことがあった。消防団団員のなり手(かつては20代、30代が中心であったが、今や40代がどんどん増えている)が少なくて、私の地区でも40代後半ですでに団員を10数年やっている方と昨年入団した方の2名(定数は4名、かつて6名出している時もあった)となっている。そうした現状を班長会で説明した。たまたまある班長の息子さんが20代ということで息子さんに消防団のことについて話していただけないかとお願いした。しかし、その返事は否定的で話してもムダ、なるくらいなら息子は町外に転出すると。彼は消防署があれば十分と思っているのかもしれない。もちろん消防団は強制ではないが、非常時に地域を守るのは消防団をおいてほかなく誰かがその役割を果たす必要があると思う。

これももとは採取した種から育った
職場では上司の命令に逆らうことは難しいので、命令一下で所属の者が動くし、会議でも結論が早く出る。しかし、自治会では基本は対等の関係であることから、異論がでるとなかなか物事が進まない。かつての肩書きなどはなんの役にも立たない。とにかく、気長に説得するしかない。ここでこそ人間の力量が少し試されるのかもしれない。

庭のクリスマスローズ、植えたのは黄色、あとは鉢のクリスマスローズの種をばらまいた
自然と交配するのもありそうで変わった色の品種が出てくる
一方で高齢者の数は増えるばかりで、高齢者のみの世帯がどんどん増えてきている。問題はやはり80歳以上の一人暮らしの方で、日頃の買い物、医者通いにも困るし、ましてや災害があったときに自力で避難することは難しい。このため、当地区では支援が必要だと思う方に申し出ていただいて、その方の近隣に住まいの方に支援をしてもらう制度を作った(社協や区長会の指導もある)。近隣の方と当該者が日頃からお付き合いがある方はすぐに支援者が見つかるが、お付き合いがあまりない方はそうはいかない。仕方がないので、当面の措置としてその班の班長や社会福祉推進委員に支援者になってもらうことにした。
その支援制度を作る中で、地区全体の災害に備えた防災計画が必要だと感じた。しかし、この防災計画だが、作っても実際には動かないことが多いことから、その必要性を感じていなかった。しかし、今回災害時等の高齢者の支援体制を作ったことから、地区の防災計画について班長会の議題としてあげた。残念ながら、それに対する意見はほとんど出ずに、私の案がそのまま4月から実施されることとなった(この地区は比較的災害の恐れが少なく、住民に防災意識が薄いのだと思う)。東北大震災特に原発事故の時、自治会は機能しなかったと聞いている。日頃からの防災意識を高めることをしていかないと災害時には機能しない。引き継ぎで次期の区長に強調しておきたいところである。

普通種が自然に落ちて、小さな苗が出てくる。しかし、この手前の黒は小苗ができない
2月22日の最終の班長会でこんなことがあった。消防団団員のなり手(かつては20代、30代が中心であったが、今や40代がどんどん増えている)が少なくて、私の地区でも40代後半ですでに団員を10数年やっている方と昨年入団した方の2名(定数は4名、かつて6名出している時もあった)となっている。そうした現状を班長会で説明した。たまたまある班長の息子さんが20代ということで息子さんに消防団のことについて話していただけないかとお願いした。しかし、その返事は否定的で話してもムダ、なるくらいなら息子は町外に転出すると。彼は消防署があれば十分と思っているのかもしれない。もちろん消防団は強制ではないが、非常時に地域を守るのは消防団をおいてほかなく誰かがその役割を果たす必要があると思う。

これももとは採取した種から育った
職場では上司の命令に逆らうことは難しいので、命令一下で所属の者が動くし、会議でも結論が早く出る。しかし、自治会では基本は対等の関係であることから、異論がでるとなかなか物事が進まない。かつての肩書きなどはなんの役にも立たない。とにかく、気長に説得するしかない。ここでこそ人間の力量が少し試されるのかもしれない。