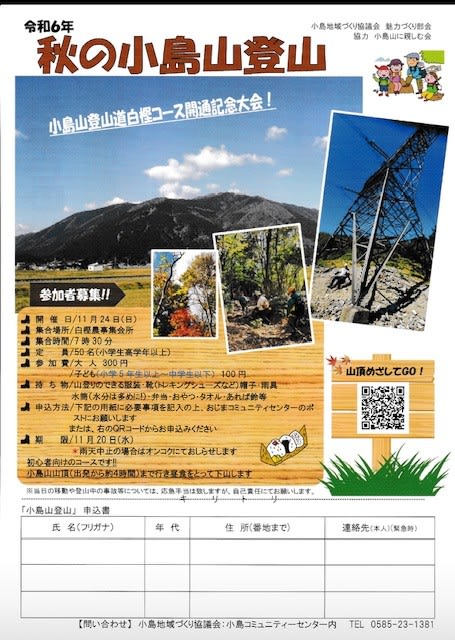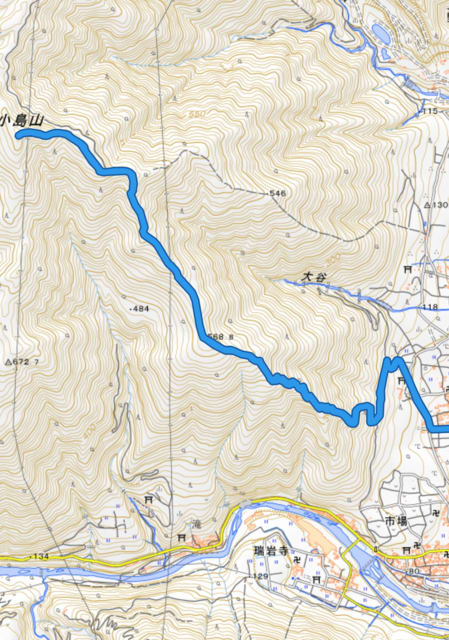今朝は久し振りの寒さであった。一心寺のモミジも半分程度赤くなってきた。昼頃から冬のはじめを告げるような時雨が降ってきた。

中央には城ヶ峰(下の部分をカットした)
しかし、今まで晩秋としては暖かい日が続いていたので、一部のバラはまだつぼみが立ち上がってきている。伸びてきてもつぼみがないもの(ブラインドという)や伸びるのをやめている品種もある。

ジーンレックス 新芽が出てきている このバラ少なくとも5回は咲いた

アンブリッジローズ つぼみをたくさんつけている 果たして咲くか(寒くなるとつぼみのままで越冬)

本来咲かないはずのつるバラ 11月29日

ザ・ワイフ・オブ・バース 11月29日
他の晩秋のバラ この時期のバラは花持ちが大変良い

ジーンレックス 11月23日

カルトナージュ 11月23日

ペッシュボンボン 11月23日

レイニーブルー 11月23日

セシルブルンナー 11月23日

同上 アップ
この時期のバラは茎がかなり伸びている(夏剪定を強くしなかったせいもあるが)

大きく伸びているのは右つるバラ、左半つる

いずれも11月23日
かつては12月ともなれば、ほとんどの葉は落ちていた。ところがこのところ暖冬の影響で葉は落ちないどころか、成長し、花をつけることさえある(冬が寒くないところでは、年中バラは咲く。そのうちに日本もそうなるかもしれない。)
では、この伸びたままで正月を越すのか。それとも切った方が良いのか。
切らないのが正解である。
冬の剪定は、1月中下旬から2月上旬に行うので、それまでは切らずにおき、少しでも成長させる(根に栄養を蓄えさせる)。
ただし、つるバラについては12月~1月に剪定と誘導を行う。
伸び放題のバラ、見てくれは悪いけれど、しばらく我慢しよう

中央には城ヶ峰(下の部分をカットした)
しかし、今まで晩秋としては暖かい日が続いていたので、一部のバラはまだつぼみが立ち上がってきている。伸びてきてもつぼみがないもの(ブラインドという)や伸びるのをやめている品種もある。

ジーンレックス 新芽が出てきている このバラ少なくとも5回は咲いた

アンブリッジローズ つぼみをたくさんつけている 果たして咲くか(寒くなるとつぼみのままで越冬)

本来咲かないはずのつるバラ 11月29日

ザ・ワイフ・オブ・バース 11月29日
他の晩秋のバラ この時期のバラは花持ちが大変良い

ジーンレックス 11月23日

カルトナージュ 11月23日

ペッシュボンボン 11月23日

レイニーブルー 11月23日

セシルブルンナー 11月23日

同上 アップ
この時期のバラは茎がかなり伸びている(夏剪定を強くしなかったせいもあるが)

大きく伸びているのは右つるバラ、左半つる

いずれも11月23日
かつては12月ともなれば、ほとんどの葉は落ちていた。ところがこのところ暖冬の影響で葉は落ちないどころか、成長し、花をつけることさえある(冬が寒くないところでは、年中バラは咲く。そのうちに日本もそうなるかもしれない。)
では、この伸びたままで正月を越すのか。それとも切った方が良いのか。
切らないのが正解である。
冬の剪定は、1月中下旬から2月上旬に行うので、それまでは切らずにおき、少しでも成長させる(根に栄養を蓄えさせる)。
ただし、つるバラについては12月~1月に剪定と誘導を行う。
伸び放題のバラ、見てくれは悪いけれど、しばらく我慢しよう