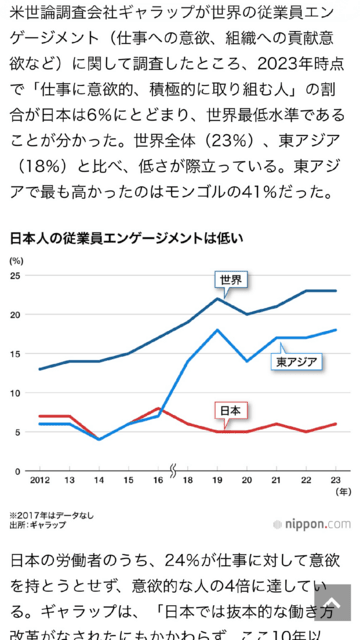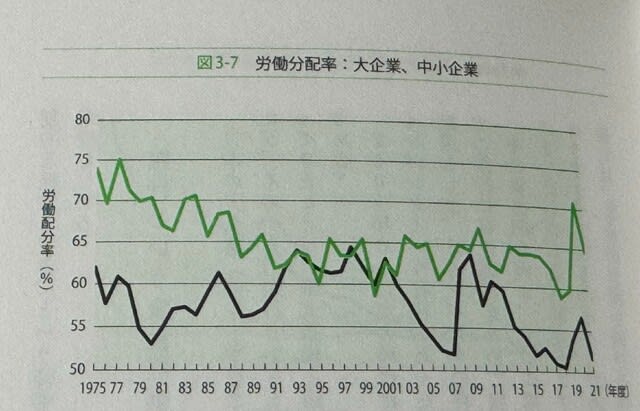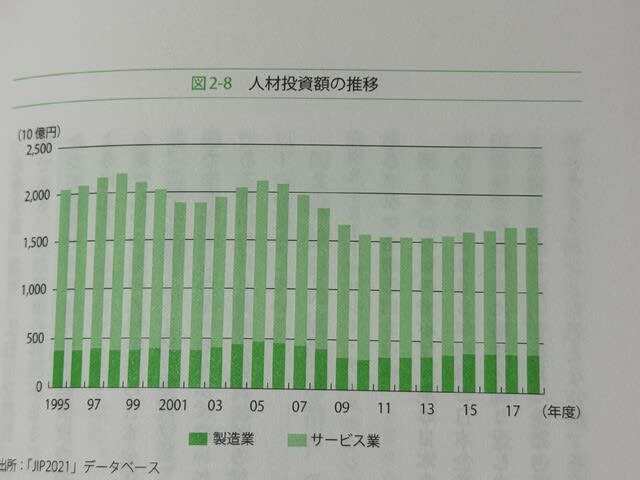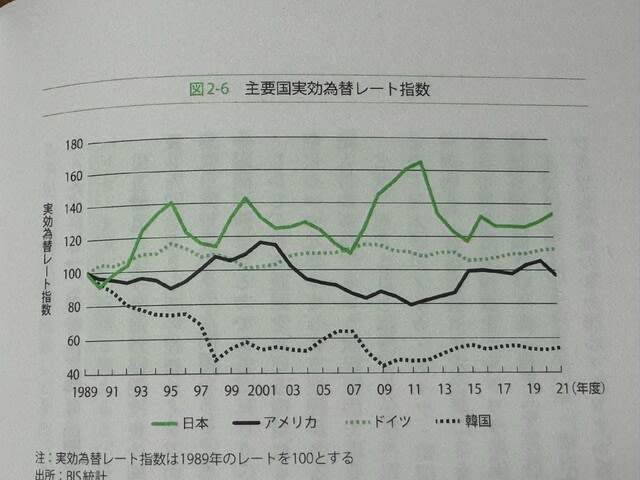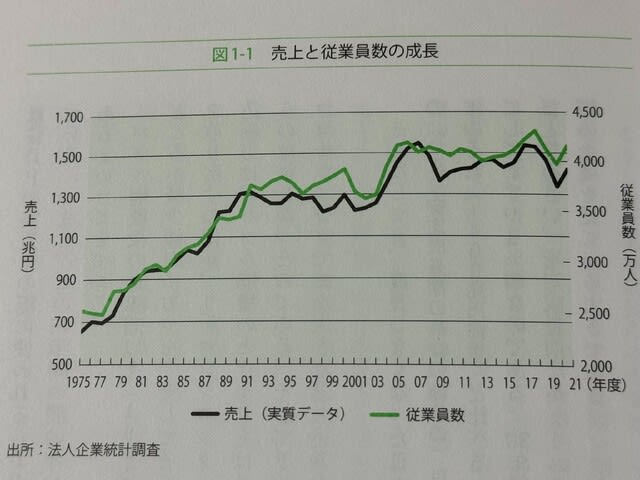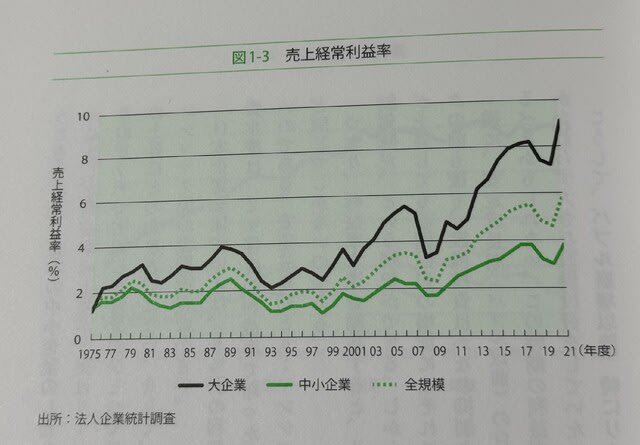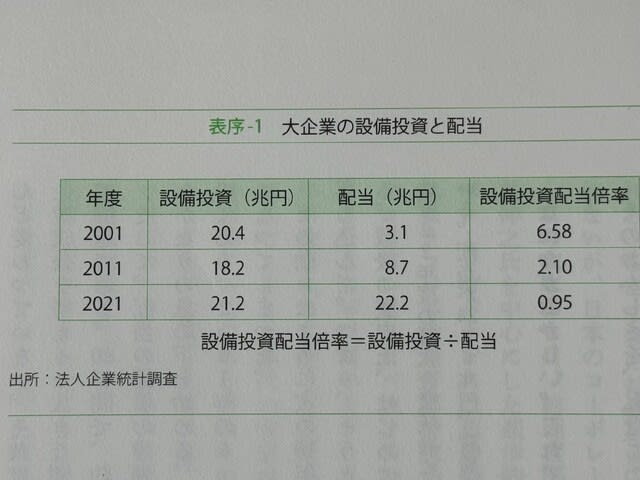水曜日頃に台風10号がやってきそうである
この台風に備えて、昨日ナス、ピーマン、甘トウガラシを支柱にしっかりと結わえ、トマトの雨除けビニールを撤去した。さらに、その夕方ここのところの雨でにわかにのびた草を草刈り機で刈った。
今朝は夏剪定前で枝が伸びたバラに支柱を立ててむすんだ。
今日は、浅田次郎の「流人道中記」と戸森麻衣子「仕事と江戸時代」を取り上げる。
歴史小説あるいは時代小説では江戸時代が舞台となることが多い。だから、小説家は当然のことながら江戸時代のことを相当勉強する必要がある。史実を学んだうえで、想像力を最大限働かせて、小説を書くことになる。
読み手である我々は、史実について勉強しなくても(知らなくても)楽しめるようにはなっているが、少し史実も学んでおくと、今以上に楽しむことができると思うが、いかがか。
まずは、「流人道中記」のあらすじから。中心人物は、不義密通(普通なら死罪となる)で切腹を迫られたが、それを拒んだ結果、蝦夷の地の領主松前伊豆守に永年お預けとなった旗本の青山玄蕃。そしてかれを蝦夷の地まで送り届ける役に任命された見習い与力の石川乙次郎。かれは青山が流人とされた訳を詳しくは知らない。奥州街道をたどる旅の途中様々なこと起こり、世間に通じた青山はこれらの事件をこれ以上の解決方法はないのではないかと思われるような見事な方法で解決していく。仙台藩では伊達のお殿様が玄蕃が来ることを知って大歓待する。石川は青山の流人らしからぬ言葉や行動に反抗したりするのだが、次第に認めることになっていく。
終盤になって、青山玄蕃の身分とその不義密通とされた事件のあらましが青山自らの口から明らかになってくる。青山の上司(石数では下)が出世さらには邪魔となる青山を陥れたが、青山は上役にその詳細を語ろうとしないし、また弁明もしない。評定の結果、下った裁決、自裁すなわち切腹を「痛いからやだ」と言って拒んだ。青山が世間を良く知っているのは、その出自からであった。青山家に仕える女中を母とし、母共々捨てられた。残飯をもらって、日々の糧とするような暮らしの中で武士という世界以外のことを知ることになる。ところが青山家の跡継ぎがいなくなって、急遽旗本という殿様になったのである。彼が切腹を拒むのは、言われなき罪と「武士が命を懸くるは戦場ばかりぞ」という信念があるからである。青山の言われなき罪に対し、最もするどく反応し、仇討ちの準備をさせたのが奥方であった。まさに忠臣蔵のような光景だ(このシーンがこの小説の中で最も感激する箇所である)。奥方をぎゅっと抱きしめ、感謝するとともに裁決を受け入れることを彼女にささやく。こうして青山家3250石は闕所となった。
一方、押送人の石川さん、そのうちに流人から乙さんと呼ばれた見習い与力。彼の実家は御家人で、彼の兄が父親から家督を譲られて同心を務める。彼は次男坊であり、同心という職には就けない。何らかの職に就くには、他家の婿になるか養子縁組しかない。彼は、武芸と学問に励み、兄が急になくなった石川家の婿に選ばれる。妻は15歳、半年経つがあまりに幼く、抱くことさえできないという事情がある。義父は与力について、何も教えてくれない。
以上があらすじ。
ここからは、「仕事と江戸時代」を紹介するが、この本では江戸時代の武士、町民、百姓、女性の働き方について書かれているが、ここでは上の小説との関連から武士のみについて書くことにしたい。
まずは江戸時代について。戦乱の時代から平和な時代となり、耕地面積の増加(新田開発)から人口が増加した。必要な基本的食料である米、麦ばかりでなく生活を豊かにするための作物、農産物を加工した商品が作られた。水陸の遠距離輸送が発達し、米や各地の産物が流通した。また、問屋、仲買、小売りといった商人の分業体制が発達した。こうした経済のベースとなった貨幣の普及があった。
江戸時代の人口の大多数8~9割が百姓として村方で生活した。彼らは自給自足ではなく、生活に必要な商品を買うために、何らかの手段で銭を得ていた。幕府や藩は定期的に戸籍調査(人別改)を実施し、一戸ごとに戸主ならびに家族全員の名前と年齢を名主、組頭といった村役人が調査した。人別帳には百姓が所持する田畑の面積、石高、漁師、猟師、大工などの稼業も書かれることがあった。江戸時代後期になると、年貢の金銭による支払いが増えるとともに、大工、鍛冶屋、染め物屋、質屋、酒屋、宿屋、湯屋、居酒屋など副業が主たる生業となる百姓が増えていった。半年、一年、長期の出稼ぎが増え、金銭による雇用契約が行われた。関東地方やその周辺では武家屋敷や商家の下働きとして雇われた。しかし、出稼ぎの彼らは村方の戸籍であり、町方の戸籍をとるにはハードルがあった。町方との婚姻や養子縁組により町方の戸籍を得ることができた。
武士家臣団の階層
①真性の「士分」②「徒士(かち}と呼ばれる準士分③「足軽層」④「中間・小者層」に分かれ、①と②が一般的に武士となる。①については何らの査定もなく、その地位が子どもに継承されるが、自らその立場を放棄できない(家督を子に譲って隠退することは可能)。武士上層ほど古典教養やマニュアル通りに職務にあたっていたが、これでは問題が解決しない分野が多くなってきた。そこでこうした分野(能楽、数学、経済学、土木工学)に精通した人物の登用、例えば二宮尊徳を行った。有能な人材を登用した分、家臣を減らすことはできないので、仕事のない武士を「小普請」と称した(この名称を持つ武士が時代小説の中で多く登場する)。彼らは俸禄を受けているが仕事はしない。
最後に上記の小説で登場する「旗本」と「御家人」。旗本はおよそ5000家。半数は知行と呼ばれる領地を与えられた。残り半分は蔵米取。青山玄蕃は3250石の知行取だが、そのうち約4割が彼の収入となる(これが四公六民)。御家人は人数が1万5000人~1万8000人で、9割5分が蔵米取。江戸居住の旗本・御家人は浅草御蔵と呼ばれる幕府の米蔵でその俸禄米を受け取ることになる。実際には、受け取りや現金化は札差が行う。米は約5年ほど蓄えられるので、相当の古米を大部分の武士達は食べることになる。現金支出で最も額が大きいのは、使用人の給金。禄高30俵2人扶持の同心でも奥方だけで家事は回らないので下働きの少女一人か下人が必要となる。旗本となると、武家奉公人や奥女中などが加わり、収入の2割が取られる。彼らにとって、お付き合いが最大の関心事となあり、冠婚葬祭、季節のイベント、親戚とのやりとり、職場の上司や同僚への贈答にお金が必要となる。

浅草御蔵

[剣客商売」道場というHPがあった ここに武士の俸禄についてわかりやすい説明がある
単位が多く、これを見るまでは頭がくらくらするような状態だった
家計の苦しい御家人は、傘張り、提灯張り、版木彫り、屋外で植木作り、鈴虫、こおろぎ、金魚の養殖を行った。同心については、様々な勤務形態があるが、おおむね3~5日に一日出勤すればよいので、暇は一杯あった。御家人株は100両以上、現在の価値で言えば2000万円で買うことができた(勝海舟の先祖の例が有名である)。
この台風に備えて、昨日ナス、ピーマン、甘トウガラシを支柱にしっかりと結わえ、トマトの雨除けビニールを撤去した。さらに、その夕方ここのところの雨でにわかにのびた草を草刈り機で刈った。
今朝は夏剪定前で枝が伸びたバラに支柱を立ててむすんだ。
今日は、浅田次郎の「流人道中記」と戸森麻衣子「仕事と江戸時代」を取り上げる。
歴史小説あるいは時代小説では江戸時代が舞台となることが多い。だから、小説家は当然のことながら江戸時代のことを相当勉強する必要がある。史実を学んだうえで、想像力を最大限働かせて、小説を書くことになる。
読み手である我々は、史実について勉強しなくても(知らなくても)楽しめるようにはなっているが、少し史実も学んでおくと、今以上に楽しむことができると思うが、いかがか。
まずは、「流人道中記」のあらすじから。中心人物は、不義密通(普通なら死罪となる)で切腹を迫られたが、それを拒んだ結果、蝦夷の地の領主松前伊豆守に永年お預けとなった旗本の青山玄蕃。そしてかれを蝦夷の地まで送り届ける役に任命された見習い与力の石川乙次郎。かれは青山が流人とされた訳を詳しくは知らない。奥州街道をたどる旅の途中様々なこと起こり、世間に通じた青山はこれらの事件をこれ以上の解決方法はないのではないかと思われるような見事な方法で解決していく。仙台藩では伊達のお殿様が玄蕃が来ることを知って大歓待する。石川は青山の流人らしからぬ言葉や行動に反抗したりするのだが、次第に認めることになっていく。
終盤になって、青山玄蕃の身分とその不義密通とされた事件のあらましが青山自らの口から明らかになってくる。青山の上司(石数では下)が出世さらには邪魔となる青山を陥れたが、青山は上役にその詳細を語ろうとしないし、また弁明もしない。評定の結果、下った裁決、自裁すなわち切腹を「痛いからやだ」と言って拒んだ。青山が世間を良く知っているのは、その出自からであった。青山家に仕える女中を母とし、母共々捨てられた。残飯をもらって、日々の糧とするような暮らしの中で武士という世界以外のことを知ることになる。ところが青山家の跡継ぎがいなくなって、急遽旗本という殿様になったのである。彼が切腹を拒むのは、言われなき罪と「武士が命を懸くるは戦場ばかりぞ」という信念があるからである。青山の言われなき罪に対し、最もするどく反応し、仇討ちの準備をさせたのが奥方であった。まさに忠臣蔵のような光景だ(このシーンがこの小説の中で最も感激する箇所である)。奥方をぎゅっと抱きしめ、感謝するとともに裁決を受け入れることを彼女にささやく。こうして青山家3250石は闕所となった。
一方、押送人の石川さん、そのうちに流人から乙さんと呼ばれた見習い与力。彼の実家は御家人で、彼の兄が父親から家督を譲られて同心を務める。彼は次男坊であり、同心という職には就けない。何らかの職に就くには、他家の婿になるか養子縁組しかない。彼は、武芸と学問に励み、兄が急になくなった石川家の婿に選ばれる。妻は15歳、半年経つがあまりに幼く、抱くことさえできないという事情がある。義父は与力について、何も教えてくれない。
以上があらすじ。
ここからは、「仕事と江戸時代」を紹介するが、この本では江戸時代の武士、町民、百姓、女性の働き方について書かれているが、ここでは上の小説との関連から武士のみについて書くことにしたい。
まずは江戸時代について。戦乱の時代から平和な時代となり、耕地面積の増加(新田開発)から人口が増加した。必要な基本的食料である米、麦ばかりでなく生活を豊かにするための作物、農産物を加工した商品が作られた。水陸の遠距離輸送が発達し、米や各地の産物が流通した。また、問屋、仲買、小売りといった商人の分業体制が発達した。こうした経済のベースとなった貨幣の普及があった。
江戸時代の人口の大多数8~9割が百姓として村方で生活した。彼らは自給自足ではなく、生活に必要な商品を買うために、何らかの手段で銭を得ていた。幕府や藩は定期的に戸籍調査(人別改)を実施し、一戸ごとに戸主ならびに家族全員の名前と年齢を名主、組頭といった村役人が調査した。人別帳には百姓が所持する田畑の面積、石高、漁師、猟師、大工などの稼業も書かれることがあった。江戸時代後期になると、年貢の金銭による支払いが増えるとともに、大工、鍛冶屋、染め物屋、質屋、酒屋、宿屋、湯屋、居酒屋など副業が主たる生業となる百姓が増えていった。半年、一年、長期の出稼ぎが増え、金銭による雇用契約が行われた。関東地方やその周辺では武家屋敷や商家の下働きとして雇われた。しかし、出稼ぎの彼らは村方の戸籍であり、町方の戸籍をとるにはハードルがあった。町方との婚姻や養子縁組により町方の戸籍を得ることができた。
武士家臣団の階層
①真性の「士分」②「徒士(かち}と呼ばれる準士分③「足軽層」④「中間・小者層」に分かれ、①と②が一般的に武士となる。①については何らの査定もなく、その地位が子どもに継承されるが、自らその立場を放棄できない(家督を子に譲って隠退することは可能)。武士上層ほど古典教養やマニュアル通りに職務にあたっていたが、これでは問題が解決しない分野が多くなってきた。そこでこうした分野(能楽、数学、経済学、土木工学)に精通した人物の登用、例えば二宮尊徳を行った。有能な人材を登用した分、家臣を減らすことはできないので、仕事のない武士を「小普請」と称した(この名称を持つ武士が時代小説の中で多く登場する)。彼らは俸禄を受けているが仕事はしない。
最後に上記の小説で登場する「旗本」と「御家人」。旗本はおよそ5000家。半数は知行と呼ばれる領地を与えられた。残り半分は蔵米取。青山玄蕃は3250石の知行取だが、そのうち約4割が彼の収入となる(これが四公六民)。御家人は人数が1万5000人~1万8000人で、9割5分が蔵米取。江戸居住の旗本・御家人は浅草御蔵と呼ばれる幕府の米蔵でその俸禄米を受け取ることになる。実際には、受け取りや現金化は札差が行う。米は約5年ほど蓄えられるので、相当の古米を大部分の武士達は食べることになる。現金支出で最も額が大きいのは、使用人の給金。禄高30俵2人扶持の同心でも奥方だけで家事は回らないので下働きの少女一人か下人が必要となる。旗本となると、武家奉公人や奥女中などが加わり、収入の2割が取られる。彼らにとって、お付き合いが最大の関心事となあり、冠婚葬祭、季節のイベント、親戚とのやりとり、職場の上司や同僚への贈答にお金が必要となる。

浅草御蔵

[剣客商売」道場というHPがあった ここに武士の俸禄についてわかりやすい説明がある
単位が多く、これを見るまでは頭がくらくらするような状態だった
家計の苦しい御家人は、傘張り、提灯張り、版木彫り、屋外で植木作り、鈴虫、こおろぎ、金魚の養殖を行った。同心については、様々な勤務形態があるが、おおむね3~5日に一日出勤すればよいので、暇は一杯あった。御家人株は100両以上、現在の価値で言えば2000万円で買うことができた(勝海舟の先祖の例が有名である)。