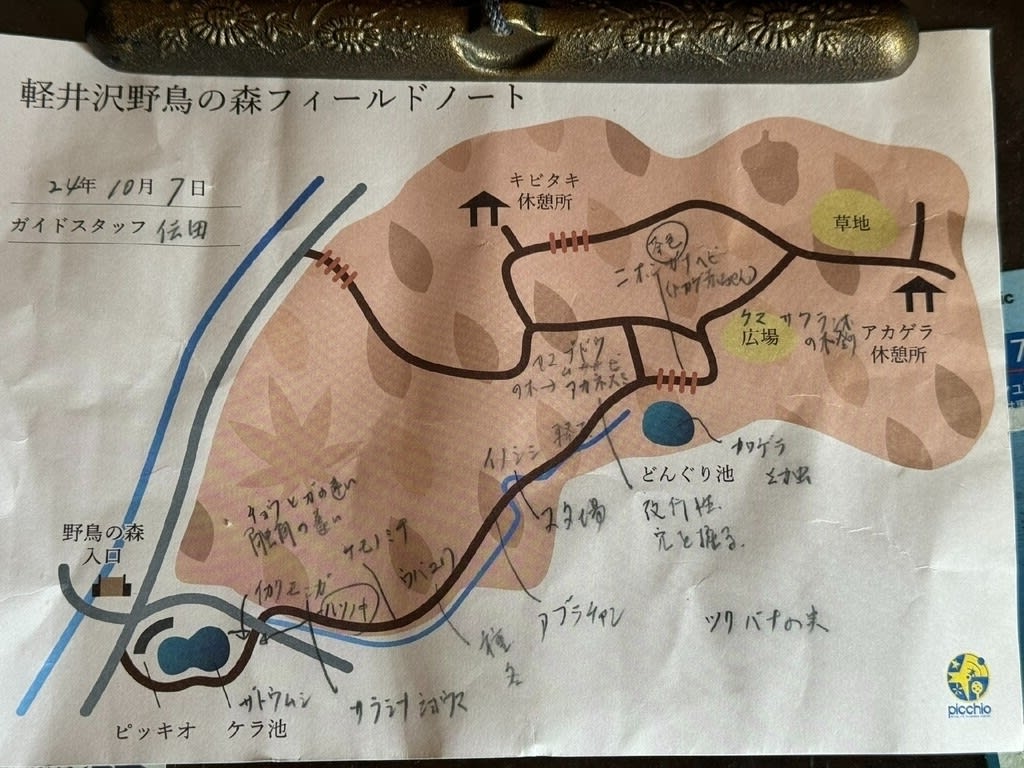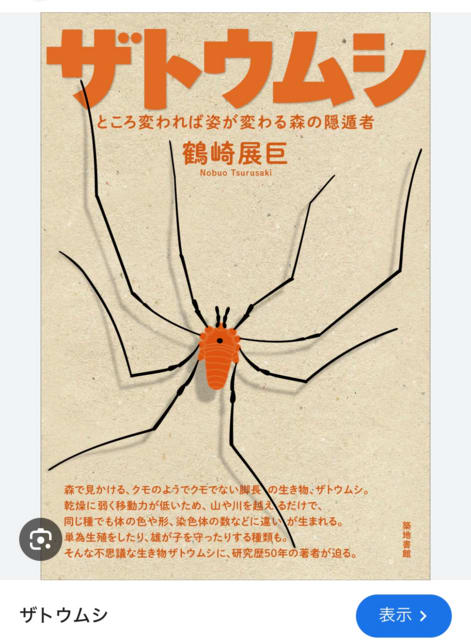あけましておめでとうございます
大変暖かい元日となりました

元旦の恒例行事

三輪神社にお参り
そこでいただいた熱々の甘酒、量も多く、飲めないのでかみさんに預けて、城台山に向かう

今日の城台山

一心寺 いつも通り過ぎるだけだが、今朝はお賽銭をあげ、しばし祈りを捧げる
このブログを書いていると一心寺の鐘の音が聞こえてくる

城台山から見る名古屋方面 揖斐川が今年の干支のように流れる 4279回目の城台山

我が地区の神社 白山神社 この名を持つ神社がそこら中にある
行くと10時からの神事が終わったところだった 昨年までは色々な役員を務めいつも参列していた
本年も引き続きよろしくお願いします
大変暖かい元日となりました

元旦の恒例行事

三輪神社にお参り
そこでいただいた熱々の甘酒、量も多く、飲めないのでかみさんに預けて、城台山に向かう

今日の城台山

一心寺 いつも通り過ぎるだけだが、今朝はお賽銭をあげ、しばし祈りを捧げる
このブログを書いていると一心寺の鐘の音が聞こえてくる

城台山から見る名古屋方面 揖斐川が今年の干支のように流れる 4279回目の城台山

我が地区の神社 白山神社 この名を持つ神社がそこら中にある
行くと10時からの神事が終わったところだった 昨年までは色々な役員を務めいつも参列していた
本年も引き続きよろしくお願いします