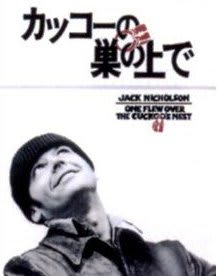
前回のブログに書いた「ヒポクラテスたち」と同じく
楽天レンタルの期間限定無料で借りました。
この映画は私が高校生の時に公開され
その年のアカデミー賞を総ナメにした
あまりにも有名な作品です。
なのに今まで一度も観たことがありませんでした。
生きているうちに一度は観とかなあかんやろ~と
常々思っていたので、いい機会でした。
観る前の予備知識といえば
精神病院が舞台であり
精神病を装ったジャック・ニコルソン扮する主人公が入院、
婦長とことごとく対立する…ぐらいでした。
展開もラストもあえて知らないようにしてたわけです。
なんとなく重い内容だろうとは予想してましたが。
ああ、やはり重い映画でした。
でも
どどどっーっと疲れる重さではありません。
「映画を観たぞっ!」という重厚感と表現すればいいでしょうか。
非常によくできた作品だと思いました。
アカデミー賞総ナメも納得、っつーか
「これが賞をとらなオカシイやろ」
的な映画でした。
観る前は
「患者を管理されたシステムに押し込む婦長 vs 患者に自由を勝ち取らせようとする主人公」
の構図を想像してたんですが
見事に裏切られました。
このふたりをどう思うかは
観客ひとりひとりに委ねられているんですね。
決して「わるもん」と「ええもん」の二分割ではないんです。
水戸黄門じゃないんですよ。
婦長はあくまでクールですが
それは婦長としての任務をまっとうしているからだと受け取れます。
ただ、そのベクトルが少しずれていたんでしょう。
患者の意志や自由をコントロールして
平穏な病棟を保つことが善だと信じる彼女にとって
マクマーフィは「悪」以外の何者でもありません。
マクマーフィは刑務所での労働からエスケープしたいがために
精神病を装って入院してきた、「おっさんの不良」です。
労働しなくてラッキー、と思ったのもつかの間
退屈な空間の中で生活している患者たちや
何の薬か尋ねても「そんなこと聞かずに飲んでりゃいいんだ」的な病院の態度に耐えきれず
「ルールは破るためにある」と言わんばかりに
ことごとく婦長に反抗するようになります。
その反抗たるや
まるで中学2年生のようです。
しかし
彼が掟破りの遊びを実行したおかげで
患者たちは生き生きとしていきます。
船に乗り込んで釣りをする場面
職員たちとバスケットボールをする場面
見られないワールドシリーズをマクマーフィが実況する場面
そしてあのクリスマスパーティ。
婦長主催の何の治療にもなってないグループセラピーより
どれだけ患者の回復に功を奏したことでしょう。
私が疑問に感じているのは
病院側がマクマーフィを仮病だと判断し
刑務所へ送還しようと話し合った時
婦長が「刑務所へ責任転嫁することになる。彼をここで矯正するのが私たちの役目だ」と反対したことです。
彼女の意図は何だったのか?
発言通り、婦長としての使命感からマクマーフィを入院させておこうとしたのか
あるいは、個人的な憎しみから彼を痛めつけるつもりだったのか
そこのところは
「観客のご想像にお任せします」
なんでしょうか。
冷静な彼女が取り乱し、人間らしい言動をとったのは
皮肉にもビリーを自殺へ追い込むシーンでした。
ビリーは自殺しましたが、彼女が殺したも同然です。
あれはひどい。あんまりだ。
母親が原因で発症したビリーに、母親のことを持ち出すとは。
おまえ死ぬしかないよ、と言ってるようなもんですね。
ラストは何というか、切ないですね。
そ、それでええんかい!と語りかけてしまうような。
観てない方にオチを言ってしまってはいけないので多くは書きませんが
それってアリかいな…と考え込んでしまいました。
とまあ、内容もさることながら
出演者たちの演技力の凄いこと!
ジャック・ニコルソンはもちろん
婦長役のルイーズ・フレッチャーが圧巻です。
特にマクマーフィに首を絞められている時の表情は
鳥肌が立つほど凄かったです。
患者を演じた脇の俳優たちも素晴らしかった。
「金ピカでまぶしい映画」とでも表現しましょうか。
で、結局
チーフが主役ってことでOK?










