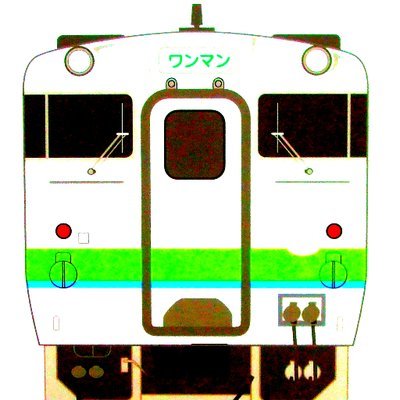冒頭の写真は幌延駅のキハ54の並び。3月のダイヤ改正で見られなくなる
まともな説明も無く、こんな一方的な事ばかりしていたら、財政的にも人的にも沿線自治体の協力なんて得られない。
北海道新聞の2月2日朝刊、JR北海道に関する報道が載った。
「保線業務、天塩中川と幌延両駅から撤退 JR北海道方針」
概要は以下の通りである
「宗谷線の保線業務について、天塩中川駅と幌延駅の20人の工務系(保線)職員を4月付で名寄、音威子府、稚内の各駅に集約する方針を中川、幌延の両町に伝えていた。音威子府―稚内には常駐の工務系職員がいなくなる。
若手職員への技術継承や業務管理の強化が理由だという。
保線拠点がなくなる音威子府―稚内間は札幌―旭川間に匹敵する距離。地元ではシカ衝突など事故対応や除雪の遅れを不安視する声が強い。
川口精雄中川町長は「減便以上に大きな問題」と受け止め、野々村仁幌延町長は「これで安全確保ができるのか」と疑問を呈している。
野々村町長と川口町長は2日、宗谷本線活性化推進協議会長の加藤剛士名寄市長と対応を協議。
両町はJRに対して「減便対策を検討している最中の急な通告で承服できない」と答えたという。
JRは4日、普通列車減便や工務系職員の集約について説明に訪れる予定で協議会としてJR側に反対の意向を伝えたい考え。」
以上が概要だ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
普通列車の削減のみならず(連関したものだろうが)保線分野の合理化とは、JR北は安全の確立が急務と言いながら、思考は逆の方向に向いていると感じざるを得ない。
*単に保線作業という面から見れば、事業所の集約によるメリットもあり、広義における平時の安全性はしっかり確保されるとは思う。
しかし、音威子府・天塩中川間などは春先の融雪期に大増水する天塩川の川縁を走るので、同時期は減速運転をやむなくされる。さらに、全線で動物の出没も多く接触事故は日常のことだ。また、大雨による潅水も頻繁に起き、路盤のバラストが流されることも多い区間である。
にもかかわらず、常駐の工務系職員がいなくなることは、非常に心配が残る。統廃合による利点には一定程度は理解できなくもないのだが、交通機関として万一の場合の利便性というか復旧対応の遅れなど、一面では利用者が享受する待遇条件が悪化するのは間違いないわけだから、事前に沿線自治体と話し合いをして、理解を得てからでもよかったと感じる。
減便が打ち出された、このタイミングでは地元自治体としても感情的に受け取らざるを得ないだろう。
この間、JR北はこのような点への対応が下手だと感じる。
さらに、ほんの数年前に極端な保線管理費の削減から脱線事故を招いた反省はどこへ行ったのか。合理化を取り違えるなとまで言いたくなる。
目的は保線拠点集約と技術の継承と言うこともあるが、ベテラン職員と若手職員を配置転換して交代させればかなり解決されることではないのか。JR北海道は勤務地が支社や事業所単位で決まり、基本的には決められた地域での異動しかないという話を聞いたことがある。たとえば、釧路付近に居たければ、退職まで職場の異動も釧路管内だけということだ。
もし、このことが人材交流の妨げの原因の一つならば労使で協議するべきだろうし、全社で再建に取り組む今は、期間限定にしてでも遠隔地への転勤も受け入れるべきではないだろうか。
推測は、このくらいにするが、現段階、このタイミングで保線分野を縮小統合すると言うのは突然すぎて、とても各方面が素直に理解するとは思えない。
結局、民営化以来続けてきた無理な省力化を継続することしか考え付かないのかなとと皮肉も言いたくなる。
残念だが、東日本からの応援社員からの助言はこの程度なのかと言わざるを得ない。
今は様々な面で、地元自治体の協力が必要なときだ。自治体を説得すると言う術を見につけたほうが良い。
聞く耳持たぬといった感じのする一方的施策ばかり打ち出していたら、協力を得ることは、とても無理な話だろう。
今回の事業所統合が原因と思われるようなトラブルが万一発生したとき、どのように釈明するのか聞いてみたいものだ。
まともな説明も無く、こんな一方的な事ばかりしていたら、財政的にも人的にも沿線自治体の協力なんて得られない。
北海道新聞の2月2日朝刊、JR北海道に関する報道が載った。
「保線業務、天塩中川と幌延両駅から撤退 JR北海道方針」
概要は以下の通りである
「宗谷線の保線業務について、天塩中川駅と幌延駅の20人の工務系(保線)職員を4月付で名寄、音威子府、稚内の各駅に集約する方針を中川、幌延の両町に伝えていた。音威子府―稚内には常駐の工務系職員がいなくなる。
若手職員への技術継承や業務管理の強化が理由だという。
保線拠点がなくなる音威子府―稚内間は札幌―旭川間に匹敵する距離。地元ではシカ衝突など事故対応や除雪の遅れを不安視する声が強い。
川口精雄中川町長は「減便以上に大きな問題」と受け止め、野々村仁幌延町長は「これで安全確保ができるのか」と疑問を呈している。
野々村町長と川口町長は2日、宗谷本線活性化推進協議会長の加藤剛士名寄市長と対応を協議。
両町はJRに対して「減便対策を検討している最中の急な通告で承服できない」と答えたという。
JRは4日、普通列車減便や工務系職員の集約について説明に訪れる予定で協議会としてJR側に反対の意向を伝えたい考え。」
以上が概要だ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
普通列車の削減のみならず(連関したものだろうが)保線分野の合理化とは、JR北は安全の確立が急務と言いながら、思考は逆の方向に向いていると感じざるを得ない。
*単に保線作業という面から見れば、事業所の集約によるメリットもあり、広義における平時の安全性はしっかり確保されるとは思う。
しかし、音威子府・天塩中川間などは春先の融雪期に大増水する天塩川の川縁を走るので、同時期は減速運転をやむなくされる。さらに、全線で動物の出没も多く接触事故は日常のことだ。また、大雨による潅水も頻繁に起き、路盤のバラストが流されることも多い区間である。
にもかかわらず、常駐の工務系職員がいなくなることは、非常に心配が残る。統廃合による利点には一定程度は理解できなくもないのだが、交通機関として万一の場合の利便性というか復旧対応の遅れなど、一面では利用者が享受する待遇条件が悪化するのは間違いないわけだから、事前に沿線自治体と話し合いをして、理解を得てからでもよかったと感じる。
減便が打ち出された、このタイミングでは地元自治体としても感情的に受け取らざるを得ないだろう。
この間、JR北はこのような点への対応が下手だと感じる。
さらに、ほんの数年前に極端な保線管理費の削減から脱線事故を招いた反省はどこへ行ったのか。合理化を取り違えるなとまで言いたくなる。
目的は保線拠点集約と技術の継承と言うこともあるが、ベテラン職員と若手職員を配置転換して交代させればかなり解決されることではないのか。JR北海道は勤務地が支社や事業所単位で決まり、基本的には決められた地域での異動しかないという話を聞いたことがある。たとえば、釧路付近に居たければ、退職まで職場の異動も釧路管内だけということだ。
もし、このことが人材交流の妨げの原因の一つならば労使で協議するべきだろうし、全社で再建に取り組む今は、期間限定にしてでも遠隔地への転勤も受け入れるべきではないだろうか。
推測は、このくらいにするが、現段階、このタイミングで保線分野を縮小統合すると言うのは突然すぎて、とても各方面が素直に理解するとは思えない。
結局、民営化以来続けてきた無理な省力化を継続することしか考え付かないのかなとと皮肉も言いたくなる。
残念だが、東日本からの応援社員からの助言はこの程度なのかと言わざるを得ない。
今は様々な面で、地元自治体の協力が必要なときだ。自治体を説得すると言う術を見につけたほうが良い。
聞く耳持たぬといった感じのする一方的施策ばかり打ち出していたら、協力を得ることは、とても無理な話だろう。
今回の事業所統合が原因と思われるようなトラブルが万一発生したとき、どのように釈明するのか聞いてみたいものだ。