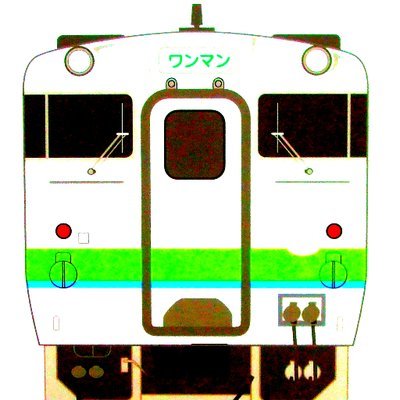5月11日日立製作所笠戸事業所からJR北海道の新型軌道検測車が甲種輸送されてきました。
5月8日に山口県の下松を出た車両は10日に北海道に上陸、11日早朝に東室蘭のJR貨物操車場に到着し、その日の深夜遅くに札幌運転所に納車されました。
JR北海道は1978年に製造されたマヤ34-2008(マヤ検)を40年にわたり使用してきました。さらに毎年、初夏のころには東日本からキヤE193(Easti-D)を借用して線路の保守を行ってきました。
(キヤE193(Easti-D)2016 5月 函館本線朝里駅にて)

(マヤ34-2008 ウィキペディアより)

3年前の函館本線、大沼駅構内での貨物列車脱線事故や石勝線でのキハ283の火災事故の原因が軌道保守の不備が原因であることがわかり、老朽化したマヤ34-2008に代わる測定車の導入が必要と判断されていました。
当初、開発を中止したキハ285の転用も検討されましたが、新規に制作することと大きく費用が変わらないとの判断で、この度の新製に至ったようです。
積雪期でも測定でき来るという事で、その活躍が期待されます。
11日に雨の中を室蘭まで3時間半かけて(●^o^●)ドライブして東室蘭操車場に到着。
なお、母の家が近いので、母の様子を見るとともに父の仏壇にお線香は上げてきました(*^。^*)
すでにネット上で輸送中の姿がアップされていたので、あまり驚きはなかったのですが、窓が無い姿は一風変わったもので、いかにも測定車両といった印象でした。
発表されている新車両のデザインでは白を基調とした太い横帯が入るはずですが、札幌で施工するのか、ベースの緑色一色というバッタ(●^o^●)のような姿に目を引かれました。







今年度は各種試験等で車両の性能確認、検測装置のデータ検証等を行い平成30年4月から正式に運行が開始されます。
したがって当分の間は、きれいに整備塗装しなおされた旧マヤ検・マヤ34が従来通りに軌道の検測を行います。
ただ、新車には架線の検査の設備は見当たらず、検査をどうするのかが気になるところです。
今後も高架橋の耐震工事、老朽化した隧道や橋梁等々、30年放置してきたに等しい鉄道関連設備の補修を一気に行うことになる上に、キハ40や183等の車両の更新など巨額の費用が必要となり、自治体への負担を言い出すJR北海道ですが、JR他社では一部の災害復旧を除いては、そのような自治体による負担はほとんど行われていません。自らが放置してきたにもかかわらず、今になって利用者につけを回すことを当然のこととしているJR北海道と株主の国の不作為は、やはり許すことはできません。

基本的に、国民は国土のどこに住もうとも公的サービスを平等に享受できる権利があり、その対価が場所によって極端に異なるのは憲法で保障された生存権にも関わる問題だと思います。
これは首都圏に住む人たちが、過酷ともいえる通勤電車の混雑に耐えて暮らしていることにも言えることなのです。この二つには基本的に違いはないのです。
過疎と高齢化にばかり目が行きますが、人口が集積した都市部の交通は万全かというと、必ずしもそうではないのです。
新幹線やリニア、航空機、さらに高速道路という都市間交通には熱心な政治が、国民の日常生活の足の確保を疎かにしているということの現れです。