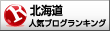「ない。一度も聞いたことがない。大体鉄さんは自分のことは何も話さない人だし、あやさんが
知らないことを俺が知っているはずもないよ」
「そうよね。ただね、近頃の鉄さんの様子が少こし変なのは、間違いなくあの手紙が関係してい
ると思うの。そう思わない」
「確かに、ぼくもそうだと思うよ」
コーヒーが運ばれて来た。
まだ千恵とたいして変わらない年に見える娘が、束ねた髪を揺らしながら、ぎこちなくカップを
置いた。
あやはコーヒーをブラックで口にした。
それを見ながら高志は、スプーンで三分の一杯だけ入れた。
二人ともミルクには手を出さない。
あやは二口目もゆっくりと香りを嗅いでから眼を細めて言った。
「こんな美味しいコーヒーが飲める店があるなんて、知らなかったわ」
「店のイメージとは大分違う」
高志も同意して笑った。
再び無地の白いカップに唇を寄せてから、少こし改まってあやが言った。
「この際だから話すけれど、鉄さんが私達の家に来たのは私が6歳の時の冬で、その後父と母が
亡くなったのは10歳の時、そのことはもう知っているでしょう。
両親が亡くなってからは、私達の間に会話は無くなってしまった。
それであの人のことは、父から聞いたことだけなの。父の話しではあの人はジャコシカで、北海
道内だけでなく樺太までも流れ歩いていたということだけなの。