食いが止まる正午頃には、千恵も清子も存分に船釣りを堪能していた。
お昼は納竿の時刻だ。高志の合図で皆が仕掛けを片付け終わる頃には、船は早くも港に入ってい
た。
港では赤間猛が、手際良く調達したクーラーに、氷を詰めて待っていた。
「鉄さんの船で行くんじゃ、これくらいの準備をして待つのは、当然と言うもんだろう」
猛は船べりから引き上げられた網袋を見て満足気に笑った。
その後あやと高志は姉妹と別れて、そのまま船を返して帰路についた。
二人きりになると船の上は、またいつもの漁師の仕事場の気配になった。
それでも二人の頭の中には、千恵が口火を切った、この海を出て行く日の近いことに、引き戻さ
れていった。
思いは相通じ合うのか、互いが去った後の入江の家のことに捉えられていった。
十九
千恵は婦人雑誌の頁を繰りながら、テ―ブルのカップに手を伸ばした。
白磁のカップの中身は、既にすっかり冷めている。
僅かな一口でコーヒーは終わった。それでも未練らしく中を覗きこんでから、テーブルの受け皿
に少こし苛立って置いた。
他に客のいない広くもない店内に、その音が響く。カウンターでドリップのコーヒーを淹れてい
た、50歳代のマスターがチラリと視線を向けたが、直ぐにまた漏斗の上から、ケトルの湯をゆっ
くりと注ぐ。
古い民家の廃材を活かした、くすんだインテリアの店内は、ウオールランプの明かりに照らされ
て、千恵には少こし重苦しい。










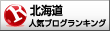

 の分はネットで上手く行ったが
の分はネットで上手く行ったが










