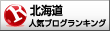それでもここ「しおん」は、この街で唯一の本格的な味のコーヒを楽しめる店だ。
千恵は柱の時計に眼を走らせ、それから肘かけ椅子脇の出窓から通りを見た。
駅前通りの痩せたアカシア並木越しに見える人影はまばらだ。
約束の時間より10分が過ぎていたが、姉の清子の姿はまだ現われない。
しおんは姉が高校を卒業後、漁協に勤め始めてから、二人で良く利用している。
昼食時や仕事帰りの姉を、良くここで待った。
強いコーヒーの香りに包まれながら、通りを行き交う人々を眺めていると、ふと自分が都会暮ら
しをしているような、錯覚に陥る。
そんな時は急に大人になった気分に捉われ、つい白いカップを物思わし気に、指先で回してみた
り、婦人雑誌のグラビア頁を、見るともなくめくったりしてみる。
そんな時間がたまらなく楽しい。
あと少こし、あと一年半も経てば本当に、自分は都会に出て、そんな時間を過ごしているのだ。
取り留めもなくそんなことを考えていると、この店の剝き出しのくすんだ梁や、柱に掛けられた
ランプ型の明かり、生真面目そうなマスターの顔、そして季節ごとに出窓に飾られる鉢の花や通り
の並木の移ろいなども、しっかりと目蓋の奥に、残しておきたいと思ってしまう。
まどろみに似た時間の流れの中で、突然、不安な黒い人影が行き過ぎる。
「どこに流れて行くか分からない。いつだって風の吹くままだよ」
彼の言葉はきちんと考えた上での、言葉には思えない。
軽いその場限りの思いつきか、あるいは定まらぬ身を取り繕った、軽口なのかも知れない。聞い
ている時は恰好付けているのかと、反発心が湧いてきたが、その後で妙に耳の奥に残った。